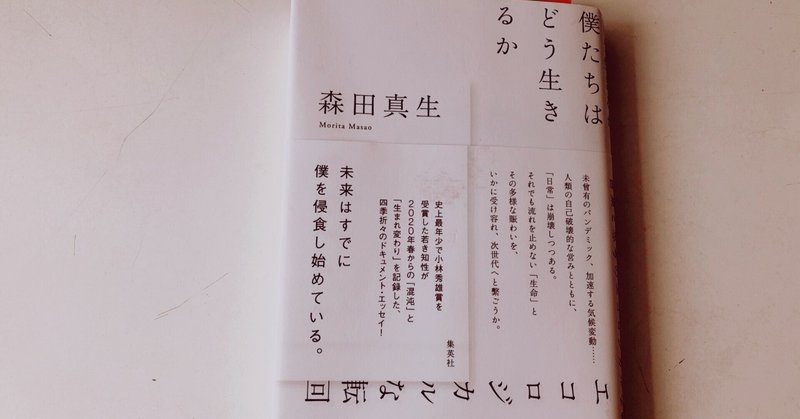
#6 新しいピアノ教室のヒント
こんにちは。ピアノ教室を主宰しているきっこです。
今回は森田真生著「僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回」をヒントに時代にフィットした音楽教室はどのようなあり方がいいのか模索していきます。
森田真生著「僕たちはどう生きるか 言葉と思考のエコロジカルな転回」
こちらは数学を専門とし学びについて研究を続けている森田真生さんが、2020年の春から1年間雑誌「すばる」での連載をまとめたものです。
2020年といえばまさに新型コロナウィルスが蔓延し始めた頃で、目まぐるしく容赦ない日常の変化を日記とともに語っていきます。今生きているということと、未来を生きる子どもに接していることを考える視点が詰まっています。
タイトルに「エコロジカル」という言葉があるように、著者はコロナ禍をきっかけに環境に目を向けます。環境問題というとかつては道徳や理科の時間に学んだ分野という方も多いと思いますが、今やどんな分野とも切り離すことができない、今ここにいるということが全て環境を無視できない状況になっていることに現代では気がつかされています。
環境との関わりについて哲学者であるティモシー・モートンの著者をきっかけに2020年の変化を著者が捉えていきます。
ティモシー・モートンは音楽や芸術と環境の重要性をその著者で語っています。また音楽教室を「教育」という視点から捉えればなおさら「環境」との関係はより深まります。
コロナ・学び・環境・生きることをテーマとしたこの本を、ピアノ教室という視点から捉えます。
過去と現在の生活の手触り
私がピアノ教室で扱っている分野は主にクラシックです。「クラシック音楽」と言われるものは主に17世紀〜20世紀に活躍した作曲家の音楽を扱います。その時代について世界史や音楽史で学んではきましたが、実際に生きる人たちは今とどのような違いがあるのかは、我が事のようによう考えることがこれまでありませんでした。
コロナ禍をきっかけにより明らかになった現在の状況から、かつての人々との違いが浮き彫りにされていきます。過去と、現在の両方が鮮明になります。
はじめにその部分を紹介します。
疫病が神の怒りや悪魔の仕業とされていた時代、くしゃみとともに放たれるわずかな飛沫のなかに、死に至る病を引き起こす微小な粒子が、無数にひしめいていることなど誰に想像できただろうか。
かつて、自力を信じることができる時代があった。そこでは、知の目指すところは「正しさ」であった。誤謬に汚染されない清潔な場所に立ち、高みからすべてを曇りなく見張らせるような視点があり得ると、素朴に信じることができる時代があった。
かつて、人間活動とは独立の地盤を持つ所与として、その中で人間活動の「成長」を目標とできた時代があった。ところがいまや、人間活動を支えられる環境は決して所与ではないことが明らかになってきている。
私たちがピアノ教室で主に扱っている作品が作られた時代は、いまとはこうも違う基盤があったことに改めて驚きます。
つまり、かつては神や悪魔が自らの健康と近く結びついていて、自信を信じて「正しさ」という高みを目指して「成長」することを目標とすることができた。
しかし、今では自分の健康には「ウィルス」など目では捉えられないけれど確かに存在するものが関係していることを知り、異質な他者なしに自分は存在し得ないことを知り、「高み」という考えが機能しないことを手触りとして知ってしまいました。
音楽作品そのものを魅力的に感じるかどうかはそれぞれの人に任されていて自由であっていいと思うのでここでは特に取り上げません。作品そのものをどうするかではなく、音楽がある場所について、つまり私がいる音楽教室や演奏会、発表会などのあり方が、曲が作られた時代を理想としたりそのままを再現しようと目指すこといかに難しいかということを感じます。
私たちが作る音楽の場は、今生きている人たちの求める形で作ることが理想的です。今を生きる子どもの感性を否定することは逆行していることになるし、感性を矯正しようとすることも過去を拠り所にしているように思えます。
自己を閉じずに弱くいること
#4で紹介した「ミュージッキング」によれば、クラシック音楽の現場は、多くの孤立、分断が見られると言います。
観客と奏者の分断、観客同士の孤立。ピアノのソロコンサートではまさに、自分一人で完璧になろうとしているように見えます。椅子の高さ、座る位置、靴底の厚さ、気温湿度、ピアノの角度。脆く繊細な調整をして実現しようとする首尾一貫した世界。
そこには統制不可能な他者の侵入をできるだけ拒もうとする姿勢があるように見えてなりません。
しかし、
エコロジカルな自覚のもとでは、僕が僕であるという「A=A」という「自己同一性」は、もはや当たり前のことではなくなる。
というのも、そもそも私たちの身体は他者とともに成り立っています。
人体の約37兆個の細胞にはそれぞれ何百ものミトコンドリアがいて、遠い過去に細胞の祖先と共生を始めた彼らが、今もせっせと細胞にエネルギーを供給している。僕の身体の中には、無数の僕でないものたちがいる。その力を借りて初めて、僕は僕であり続けることができる。
同一性に先立ち、他者との混淆がある。
純粋に、清潔に、首尾一貫した「自己」という発想自体が、すでに現実味を失っている。自己と非自己、人間とそれ以外と、ものごとを図と地にきれいに分けられると信じるにはもはや、僕たちはあまりにも深く、他者が自分に浸みこんでいることを学んでしまっている。
順調に首尾一貫した行動ができなくなったときに、自閉的であることから他者との調整が始まる。自分ではないものに支えられている弱さを受け入れる。その他者を受け入れる「弱さ」が私たちが心を壊さずに生きるために避けられないことだと言います。
そこで脆い閉鎖的な音楽の場ではなく、異質な他者といつも調子を合わせて行くような場のあり方をすることはできないでしょうか。
病気によって、事故によって、思わぬひらめきによって、それまで順調に作動していたはずの生の流れがにわかにストップする瞬間がある。その刹那、人は思わずその場で立ち止まってしまう。
だが、立ち止まることは、単に「停止」することではない。今まで深く省みることのなかった人生の前提条件が揺さぶられるとき、人は立ち止まり、自分でないものの声に耳を傾け始める。(中略)
全ては順調に作動しているとき、そこにはしばしば、他者への想像力が欠落している。そもそも、順調な作動は、案外脆い。「順調な作動」という観念自体が、作動の順調さを測るためのひとつの尺度に依存しているからである。
順調さと、前提の崩壊を繰り返しながら、他者への想像力を広げることができる場の在り方とはどういうものでしょうか。
順調な作動という自閉的な枠組みが破れ、そこに異質な他者が訪問してくる。ここから、自分ではないものと付き合い、それと調子を合わせていこうとする営みが始まる。
異質な他者の存在を許し、それと付き合いながら少しずつ調子を合わせていくこと。これをモートン(ティモシー・モートン)は「attunement」と呼ぶ。「attunement」とは、音楽の文脈では「調音」を意味する言葉だが、波長を合わせていくこと、適応していくこと、自分ではないものに少しずつ慣れていくことなどが含意する豊かな意味の広がりを持つ言葉である。他者を排除するのでも、ただ服従するのでもなく、他者に耳を傾け、付き合っていくこと。自分でないものと共存しながら、それでいて容易に一体化してしまわないこと。「attunement」にモートンは、こうした繊細なニュアンスを吹き込んでいくのである。
自己の内部に閉じこもるだけでなく、他者と調子を合わせていく人間の能力。これを支えているのは、人間の「弱さ」だとモートンは語る。弱さとは、自力だけでは立てないことである。
すべてのものは、自分でないものに支えられている。だから、自力だけで立てるものなどない。
ピアノは特に一人で音楽を完結できる楽器です。伴奏を必要とせずソロで演奏が可能で、まるでいくつもの楽器が鳴っているかのように多彩な音色で演奏できることが一つのピアノの目指すところでもあります。
放っておくと自閉的になりやすく他者との調子を合わせる機会が極端に減っていきます。それは先ほど触れたような、ピアノが完成した時代的背景とも一致しています。
他者と調子を合わせる弱さを持って人生を切り開いていく。
それとは逆の状態、つまり閉鎖的に高みを目指し自分一人で順調な作動を作り上げていくという場所にピアノ教室は陥りやすいのではないでしょうか。
他の楽器になりたいピアノ
著者は、多様性が低く人間以外の生物種がほとんどいない学校という場をより深い学びの場とするために、校庭にジャングルを作るというプロジェクトを考えます。
校庭をジャングルに変えるためには、スポーツを作り変えないといけないといい、スポーツを開発する澤田智洋さんと話をします。
「すべてのスポーツは、ある意味で障害者体験なんです」と澤田さんは語る。サッカーは、手が使えない障害。ラグビーは、後ろにしかパスを出せない障害。バスケは、ドリブルしている間しか動けない障害・・・。不自由を楽しむことがスポーツだとすれば、様々なスポーツの開発と体験を通して、僕たちはもっと不自由を想像できるようになるかもしれない。
他者への想像力を育む実践としてのスポーツという発想は、僕にとっても目から鱗だった。(p.124)
「○○をできない」ということは不自由を想像することにつながると言います。先ほどピアノはいくつもの楽器になろうとするということも、その捉え方をすれば、「いくつもの楽器を使えない」という不自由を体験していることでもあります。
「ここはヴァイオリンのように弾きたい」「ここはクラリネットのような音で」「バリトン歌手のように」など他の楽器や声を想像して演奏することは、他者への想像でもあります。
そのように考えると、ピアノはどんな楽器よりも他の楽器を想像し不自由を感じながら、できる範囲で実践しようとする楽器であるとも言えます。
学びを変えるために、場を変える
校庭をジャングルに変える、という構想についてすでに書いた。これを、ある建築家の方とお話ししたとき、彼が、「校庭をジャングルにするなら、スポーツを変えないといけないでしょうね」と言った。人間以外の生き物が排除された近代的な景観のなかで、近代のスポーツは生まれた。これが普及していくことで近代的なランドスケープが、あちこちに作られていくことになった。(p.125)
著者のいう学校と同じように、多くの場合ピアノ教室も、外部との交流をほぼ断たれた空間で、あらかじめ決められた手順で知識や技術を注入される。
ピアノ教室も調子が狂わされる他者が存在し、そこからより学びの深い場にすることはできないでしょうか。
校庭を変えるためにスポーツを変える必要があるということを参考にすれば、もっと開かれて他者との共存を目的とした、自分でないものとの「attunement」する音楽の場所に変えるのならば、音楽を変える必要があるとも考えられます。もっと多様で開かれた音楽を扱う必要があります。
レッスンと遊びのジレンマ
最後にこれからの時代は「遊び」がキーワードになると言うティモシー・モートンと人類学者のボイヤーとの共著から解説しています。
「遊び」とは既知の意味に回帰することではなく、まだ見ぬ意味を手探りしながら、未知の現実と付き合ってみることである。それは、みずから意味の主宰者であり続けようとする強さを捨てて、まだ意味のない空間に投げ出された主体としての弱さを引き受けることである。意味の全貌を見晴らせないなかで、それでも現実と付き合い続けようとする行為は、自然と「遊び」のモードに近づいていく。
ピアノを習い事として始める時期が低年齢化していることで「遊び」のなかで音楽を学ぶ方法が試行錯誤されています。同時に「遊び」と「学ぶ」の共存の難しさを感じます。
大人と子どもが同じ場を共有するとき、しばしばその場を支配するのは子どもたちだ。大人は自分が意味の主導権を握っているつもりである。椅子は座るもので、テーブルは食事をするためのものだ。意味を一望できる「ハイパーサブジェクト」として、大人は子どもたちの前に君臨している。
ところが子どもたちはその同じ場にいて、全てを思わぬ仕方で遊び始める。椅子にのぼり、コップを落とし、食事をするはずの場で追いかけっこを始める。子どもたちは大人が構築した世界に対抗するのでも、自分たちの「正しさ」を振りかざすのでもなく、ただ大人と同じ世界を、その与えられた配置のまま、それを構成するあらゆる要素を別の意味で使い始める。子どもたちの果てしない遊び心に、大人は翻弄されてしまう。強い主体であるはずの大人が、まだ意味がないことを受け入れる子どもたちの主体性の弱さに、すっかり振り回されてしまう。
ここに書かれていることは小さな子どもがレッスン室にやってきたとき、よく見られます。子どもは大人が構築した環境をまず自分なりの仕方で使い始めます。ピアノという新しいものを前にして、大人が用意した意味とは無関係に自分なりに試します。
そこで、私たち大人はピアノの使い方を教えることになります。そこにはルールがあり、使い方があるということを伝えます。
そのルールを受け入れられないとレッスンが成立しなくなってしまいます。
ピアノに乗ろうとしたり、弦の間に消しゴムを落としてみようとしたり。
それをやってみたらどうなるのだろうという気持ちはとても興味深くはあるものの、残念ならがらもはやクラシック音楽を扱う時間ではなくなってしまいます。
現状のピアノのレッスンは根本的にルールの中で行うことしかできません。
遊びには、二つの側面があるように感じます。1つは既存の意味に固執せず曖昧な状態を受け入れている側面で、もう1つはルールを理解しその中で競争や偶然性を楽しむ遊びです。
現状のピアノレッスンの中で可能なのは後者で、ルールを受け入れその中で遊びを通して学ぶことはできます。
ルールの意味を受け入れることができる以前の遊びは、「レッスン」という教えたいものがある場合は難しく、相容れないのではないかと感じます。それはピアノに限らず、リトミックであっても同様です。こちらが導きたい答えを用意している時点で、モートンのいう「遊び」の側面は失われてしまっています。
(略)遊戯的であることは現実からの離脱ではなく、むしろ遊戯的であることこそが現実的なのではないか。
既存の意味に固執する生真面目さよりも、あらゆる可能性を試す遊び心の方が「精緻(細かな点まで行き届いている)」だとモートンがいうのは、それが意識や生命すらないとされる、あらゆるものたちに共通する根本的なあり方だからである。
一つの動かぬ正しさよりも「精緻」な認識を求めて動き続ける。
「遊び」を最優先した音楽の時間とするとき、扱う音楽の種類も、場所のあり方も、レッスンという「教える人」と「習う人」という構図も全て変わる必要があります。
今のところ、そのレッスンにかわる音楽の時間がどんなものなのか想像ができませんが、ピアノのレッスンというものが近代学校が抱えている問題と同様に変化を余儀なくされているように見える今、これから多様なピアノの場が受け入れられ増えていくのではないでしょうか。
お読みいただきありがとうございます。いただいたサポートは書籍や楽譜の購入にありがたく使わせていただきます。応援したいと思っていただけたらサポートしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします!
