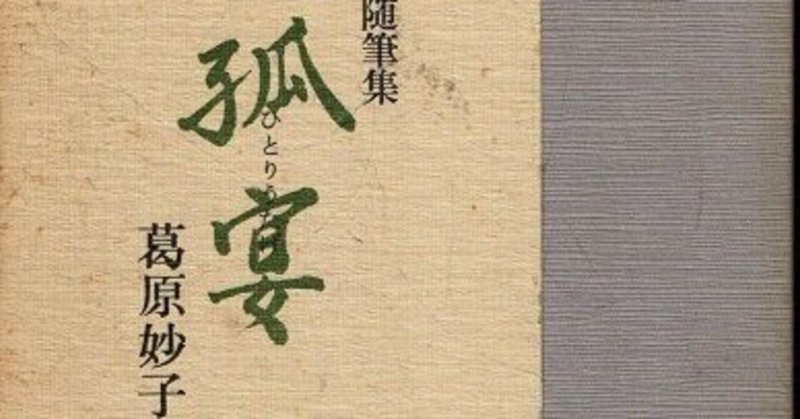
戦争を読む/『孤宴』葛原妙子
戦争を読む。
終戦の日、戦争の日々を、詩人や歌人たちはどう書いていたのか。ふと思い立ち、まず最も好きで最も遠い歌人、葛原妙子からはじめようと決める。遠いとは、好きだけれども入っていけない、入ってこないという意味だ。凄いな、良いなとは思いながら、肌感覚としてフィットしきれない歌。合わないものを合わせる必要はないのだけれど、すっと身体に入ったら素敵だなと。
無理してどうにか理解するというのは、自分は駄目で、ましてや解説本を読まないと近づけないものは、もう止めておこうと。
葛原妙子も好きなだけに、無理は絶対に禁物…それで諦めかけていたのだが、随筆集『孤宴』を見つけた。歌を身体に淹れ愉しむには最適の一冊だろう。
そこで戦争を読む。
「萱の火」
1945年8月15日。
火山礫の切り通しを歩いていた。余り遠くないところでピアノを弾いている。崖の上には鋭い薊が群生していた。更にその上をちぎれ雲が西の方に動いていた。秋が夏を殺しつつある——だれかが言った確かにそのような印象の昼であった。『孤宴』葛原妙子に納められている「萱の火」の冒頭部分。
[だれか]とはおそらく宮沢賢治。『風の又三郎』にもある『春と修羅』にもある、樺太の空、東北の空。一日にして風景の変わる、夏から秋の空の変異。余りに明るい樺太の靑空の下では、地上は密やかに昏くなる。
敗戦、空は解放され青く、地上はこれから秋になる冬になる。厳しい時が巡ってくる。
戦時中は、樹木繁り放題で、養魚場へ通う一本の道を昼夜の別なく呑み込んでしまっていた、その渾沌…眼下の雑木の谷に孤燈をあった、それが停戦を確認した唯一のもの。
白雲はしづかに在りき火を挙ぐるひとむら黄櫨の赫さ目に燃ゆ
葛原妙子はそう書き綴る。終戦、其の時の歌。赫は赤より盛んに明るく輝く赤である。孤燈を見て目が霞み錯覚におちいったとある。歌はそのように生まれる。終戦の日も変わらずに…。戦時中独り山家で、独り寝台に寝て夜に溺れて歌を詠んだ。言葉は、物は幻想であるかも現実であるかも知れず、ただくっきりと輪郭も鮮やかに。
+
随筆集『孤宴』葛原妙子
「薔薇玉」「歌人日乗」「木の間道」という大きな章立ての中に随筆が並んでいる。「歌人日乗」のうち「萱の火」をはじめとする何片かに、終戦の日が書かれている。
さてどこから、もっと踏み込むか。
カミュの「ヨナ」を読書することからだかろうか。
『孤宴』巻頭二つ目の「白い朝顔」は、カミュの引用からはじまる。
ある種の人はひとりで眠ることが出来る。
召命によって、或いは不幸によって——
一人の寝床は死のようなもの (カミュ)
さてそこで私は今、この作歌のいう深淵のごときひとりの寝床のかたわらにいるのだが、カミュは召命者を除いてひとりで眠るべからず、と言っているかに思われる。
ときにほかならぬ私はここ数十年一人きりの夜を過ごし一人で眠っている。
不可解な光景や、ありうべき経験や、現象の不可解を、短歌という信ずべき日本古来の詩の形にするのが私の夜の時間であり役目なのである。
歌は帰するところ私の独語に過ぎない。ただ独語にするためには精選したもっともてきとうなことばが選ばれなければならないのである。
歌とは独語の形をとるときにもっとも美しいと信じている。
返事無用の歌、天涯にまた心中に、孤独を完うする歌があってもよいのである。 (葛原妙子)
カミュが、『異邦人』や『ペスト』を書いた後に、戦争の影と友人からの裁きを受けて、陰鬱な世界、冥府巡りのような…聖書によって考察される信仰無きキリスト教者のような…そして『ヨナ』の屋根裏部屋に独り籠るような…孤独に入っていく。その孤独をある種の規範に葛原妙子は歌を作っていた——ように思われる。
さて、作歌のやり方を、いやその覚悟を、孤独を語っている、「白い朝顔」の最後は、こんな風に終わっている。
どうやら枕もとにいる人形は女の子であったようだが人形の性別などは実はどちらでもよいのである。
目がさめた私はこの部屋のあるじの常なるめざめと同じ位置によこたわり、しばらくもの言わぬ人形とむきあっていた。
雛という人形。
ところで、『孤宴』のタイトルとなった『ひとりうたげ』という随筆が、終りのほうに納められている。
40年前に預けたままになっていた雛人形を、代替わりになって返却された話が、出ているが、ここでの雛人形が、その人形であるかは定かでない。
要約的引用をすると。(是非とも全文を読まれたく。葛原妙子の魂に触れることができる。)
暗い雛壇があるが雛はいない。強い風が吹いている。男雛や女雛やその他大勢は、大きな風の中心に舞いあがり、冠や瓔珞(ようらく)の類いはぐっと離れた風の尻尾に乗ってゆらゆら動いている。私の雛達ははるか上空へ、上へ上へと吹き上げられ飛散しつつあるのだ。
おりしも枕元の時計が鳴った。
もちろん、雛不在の雛壇などはありようはずがなく、風の音だと思ったのは、近くを走る始発の電車であったらしい。
三月の雛節句の前の晩にやる。一組の雛がいるほか、人間の列席者はいない。
一対の紙雛の前にワイングラスを置き、その中に白酒を少し注ぐ。桜の花を挿す。むろ咲きの紅白をとりまぜてちくちくと挿してゆくと、大甕の水はあふれそうになる。花もあふれる。
見回すと点々と桃の蕾がころがっている。ちっちゃい赤い首、白い首の様に。
ある家の中の暗がりに預けてから四十年近い私の雛の櫃は今もあるだろうか。
ただたった一度、この雛たちの幻影をみたことはある。ある早春のこと、乗っている列車が碓氷峠を越え、蕭々とした浅間高原の冬景色に入って行った時、私の雛たちはとつじょ現われた。てらてらと顔は白く、袴は緋であった。
紙雛の白く平たい顔はいよいよひらたく、私は桃の花の蔭に座布団を敷き、その上にぱたりとすわってたばこを吸う。茫々と何本も吸う。その時灰色の髪の毛の私もまた桃色の花の色のスェーターを着ている。
わたしのひとりうたげとはこの様なものである。
++
戦争からカミュから人形に惹かれて読んでいく。雛が男の欲望を載せるものであることをさらりと知らないふりをして、雛という女性性と、葛原は孤独を媒介に共棲している。孤独をまっとうし過ぎると、孤独はある種の華やかさが、風たち、凡人が見れば淋しいものたちも、饗宴者となる。
雛は段にのるもの、こちらから眺めるもの。男が娘に対する願いを込めるもの。葛原の雛壇は空白にあって、雛は旦那たる夫も、従える従者も侍女もなく、葛原の身の脇にそっと居る。そのときはじめて葛原は独り寝ではない時を、過ごす。ほんの少しの時だけれども。
カミュの「ヨナの部屋」では空白のキャンバスだけが、あって、ヨナは、実に細かい文字で、やっと判読できる一語を書き残していたが、その言葉はsolitalire(孤独)と読んだらいいのか、solidaire (連帯)と読んだらいいのか、分からなかった。葛原は『孤宴』に『ヨナの部屋』を書き写すように引用している。もちろんこの最後の部分も。
孤独という姿勢にたって、尚且、連帯の可能性も希求していたカミュである。そしてその絶望も味わっている。まさに小説という形態が、孤独と連帯の矛盾の中に、あるいはダブルバインドにあるという運命を、身をもって体験したカミュ。葛原妙子の歌も、また孤独であり連帯でもあろうとした。葛原の後半生はカミュの後半生に重ね合わされる。信仰無き基督教を描いたということもまた酷似している。葛原妙子は身をカミュに寄せて独り寝の寝台を選択した。
人は孤独であったが、歌は宴の華やかさと凛々しさをもっていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
