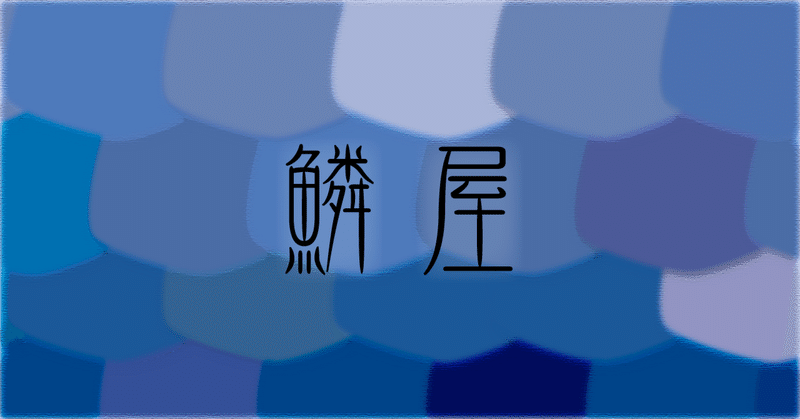
『鱗屋』
ここ数日、一気に過去作や衝動を投稿しています。そのどれか一つでも、あなたの目に止まれば嬉しいです。
今回の作品を書いたのは、もう二年前、受講していた大学の演習にて、課題として提出したものです。確かボクはこの作品を、旅行帰りの飛行機内で書き始め、書き終えたはずです。なんとも大学生らしい愚かな初速のみで組み上がった本作の初稿は、もちろんうまくオチませんでした。けれど、すこし組み直して、まあ酸化させてもいいかな、と思えるようになったので、今日があるわけです。というわけで、短編、お楽しみください。
鱗屋
怪しげな洋燈の吊るされた扉を開けば、錆び付いたカウベルの音が響く。店内は少し薄暗く、塗装のはげた木製のショーケースがいくつか。その中には丸く薄べったい、ビードロのように様々な色で光るものが陳列されていた。
「いらっしゃい。何か、お探し物でも?」あたりを物色していると、奥から老人が現れ、声をかけてきた。
「いえ、歩いていたらふと目につきまして、少し立ち寄っただけなのですが。貴方が、ここの店主さんで?」
「ええ、お察しの通りでございます。この店は初めてですかな?」
私はうなずく。店主は喉を鳴らしながら低く笑い、私にこの店について説き始めた。
「ここは、鱗屋でございます。」
「鱗屋?」
「ええ、人の目から取れる鱗を、私が採集して販売しているんですな。ああ、人の目には、薄く鱗が張っておりまして、これを私が先代より受け継ぎました講釈を耳に打ちますと、少しずつ、少しずつ眼球から浮いてくるんでございます。これをその持ち主に気づかれませんようにすっと拭い取りますと、彼らのその目や、頭にこびりついておりました、いわば考えや言葉のフィルタというものが色濃く現れまして、これがもう、どうにも美しいものでございますから、収集家のお方や学者のお方、あるいは、絵や彫刻をお作りになられるお方などが買い求めるんでございます。」
なるほど、普段からその特殊な講釈を流しているであろうその口からは、しゃがれていながらもすらすらと言葉が溢れ出る。しかしながら、あまりにも特殊なその店の概要に、私は首を傾げる他なかった。すると、店主は一つの青い鱗を指して言葉を続けた。
「こちらは、先先代が採取しました、ある西洋人のものでございます。彼は元来、国のためと、容赦無く莫大な税、あるいは、人手。様々なものを貧しき人々より巻き上げておりましたが、講釈によりまして、鱗が取れました際には、彼の頭の中にありました、弱きことに対します憂と言いますか、冷血なその目がこの鱗に吸われまして、こうも深海魚のような色をしているんでございますな。」
店主の話を聞いているうちに様々なそのフィルタに魅せられるようになった私の目は、ふと、鮮血のような鱗にたどり着く。
「では、こちらの鱗は?」
「こちらは貴方、目が肥えていらっしゃる。この前採れた上物で御座います。これはとある少女の鱗なのでございますが、彼女は十六、まだ嘘も怨みも知らぬ子でございました。ええ、ええ、彼女がその男を愛するのは当然のことだったのでございますよ。つまりはその男の軽薄なその笑顔に気が付けない歳頃だったってことでございましょう。彼女がその男の本性を知ったのは、彼女の愛がようやく彼女の思う形に、あるいは、その男の望まぬ形になった時でございます。そうです、もう一つの命を彼女は得て、得たからこそ彼女は棄てられたのでございます。もちろん彼女にその子を産み、育てる余裕はございません。彼女にはもう講釈の必要もありませんでした。嘘を、怨みを知りました。さすれば鱗が落ちるのでございます。私が思うに、この紅は怨みの色であり、命の色なのではござませんでしょうか? 悲しきことと思われますか? 許されざる男とおっしゃいますか? ええ、そうでしょう。私もそう思います。しかしながら、彼女の純然も、無知もまた悪でございます。命は元来悪を持って生まれるのでございます。鱗はその自らの悪を見て剥がれるのでございますから、彼女の紅はその男へ、ではなく、自らに向けられているのだと、それだけは伝えさせてくださいませ。まあ、彼女の出来事を、他人事として同情する、私どもへの紅かも知れませんが。ああ、では、ありがたく、その鱗頂戴致します。」
©︎Kaname Tamura 2022
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
