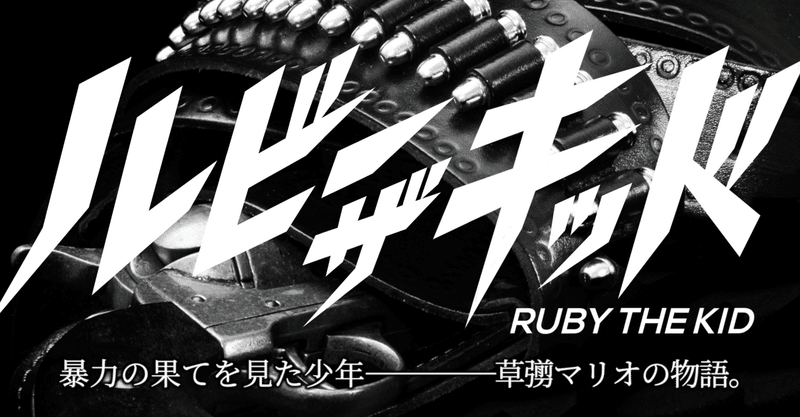
ルビー・ザ・キッド Dead Bullet : ミッション・オブ・ガルシア・アズール
ガルシア・ガブリエル・アズールは、アメリカ南北戦争に南軍の少尉として参戦し、北軍との戦闘に敗れて、灼熱の荒野を彷徨っていた。
二十一歳のときだった。
二メートル近いがっしりとした体躯に三発のライフル弾をぶち込まれ、銃剣でえぐり出された左の眼球を頬からぶら下げ、大量の血液を垂れ流しながらふらふらと足を運んでいた。残された右目の朦朧とした視界に途切れることなく入ってくるのは、友軍の兵士たちの死体だった。蝿にたかられ蛆をわかせて膨らみながら腐っている、かつての仲間たちを見下ろしながら、
虚無だ、
と彼は思った。
色んなものがあるように見えて、実はこの世界には何もない。
兵士たち、将軍たち、政治家たち、農場主たち、黒人奴隷たちやネイティブたち───奪い合いと殺し合いのつかの間に愛し合う人間たちの営みは、すべて小さな粒子の流れと、うねりが作り出す波にすぎない。喜びも悲しみも憎しみも苦しみも、快楽も痛みも生も死も、すべては滔々と流れすぎてゆく大河の表面のきらめきで、実体もなければ意味もない。
きらきらきらきら、きらきらきらきら。
ひび割れた大地の上を幻の河が流れるのをガルシアは見た。地面が回って空と入れ替わり、土埃にまみれて彼は倒れた。
気がつくと数メートル上空から自分自身を見下ろしていた。
この男はもう死ぬ、と彼は思った。
ヒメコンドルに腹わたを、ジャッカルの群れに肉と骨を、虫たちに皮と筋を食べられ、干からびて塵になり、風に舞う。
流れの中の波がひとつ、虚無へ沈んで還るんだ───。
その時、背後で何かが大きく裂けたような衝撃を感じ、霧散していた彼の意識のピントが急速に結ばれた。彼は頭上を振り仰いだ。そしてそこにありえないものを見た。
判読できない巨大な文字が、重なり合って空に浮いていた。
死に際に目にする幻覚にしてはディティールがあまりにも鮮やかすぎた。
ぐじゃっ、
とそれが混ざり合い、爆散してスコールのように降ってきた。
空が言葉を排泄した、と驚愕しながら彼は思った。
数え切れない文字の破片が、倒れ伏した彼の体に降り注ぎ、物理的な要素を削ぎ落としていった。服、皮、筋、肉、血、神経、骨を失い、魂だけになり果てた彼は、存在の芯としての『世界の本質』に直面した。
それは破壊の車輪だった。
古くなり傷んで壊れる前に、先立って壊して取り除くことで、世界のバランスを保っている新陳代謝のサイクルが、輝きを放ちながら彼の前で廻っていた。破壊がなければ虚無の大河すら腐れて澱んでしまうのだった。
作る前に壊すこと、
産み出す前に間引くこと、
殺すことが生かすことだと、慄きながら彼は理解した。
死にたくない、という生き物の願いが世界を地獄に堕とすと知った。
それでも動物や植物たちはまだ理に従っていた。人間だけが破壊を拒絶し、世界の巡りを鈍らせていた。この鈍さ、重さ、重力の強さが、破壊の車輪にブレーキをかけ、回転の働きそのものを妨げているのは明らかだった。
───誰かが調整しなければ。
「死にたくない」「生きたい」という衝動を上回る、「死にたい」「消えたい」「殺したい」という衝動を、すべての人間に抱かせることで、世界のバランスを守らないといけない───。
そう考えた瞬間、周囲に浮いていた異形の文字のいくつかが組み合わさって文字列となり、ぴったりと彼に貼りついた。
狂おしい衝動が膨れ上がった。
自分に何が刻まれたのか、知りたい、読みたい、と強く願った。
その願いに答えるように、異形の文字列が英語に変わった。
『汝の魂が続くかぎり、世界に殺戮を広め続けろ』
おお───そうか!
読んで理解すると同時に、それが彼の存在の目的と化した。世界そのものから託された神聖なミッションを実行するため、肉体の死を乗り越えてでも生き続けることを彼は誓った。
そうしてガルシアの魂は死にかけている肉体に戻った。痛みと乾きと息苦しさが一気に襲いかかってきた。
激痛をこらえ、大きく息を吸って、身を起こした。
左の眼窩からぶら下っていた眼球をつかんで引きちぎり、口へ押し込み、それを食べた。撃たれた傷口に手を当てて、流れ出す血をぬぐって舐めた。体を動かす糧になるものは何一つ無駄にできなかった。
よろよろと彼は立ち上がり、屍の大地を歩き始めた。
「死なない」
とかすれ声で言った。
使命を刻印された自分を、私は決して死なせない。
死体を喰らい、尿を飲み、灼熱の荒野を渡り切って、南軍の部隊に合流し、体の傷を癒やすのだ───そして世界を維持するための神聖な仕事に取りかかろう。
隻眼をきらきら輝かせて瀕死のガルシア・アズールが笑った。彼の中で底なしの虚無が豊穣さに裏返っていた。
十日荒野を歩き通して南軍の部隊に合流した。医療施設へ送られてそこで二ヶ月療養した。ガルシアはよく眠りよく食べた。出された病院食を綺麗に平らげ、調理場から豚や馬や七面鳥の骨をもらって髄をすすり、猟師に頼んで捕まえさせたガラガラヘビを捌いて血を飲んだ。銃創がみるみるうちに塞がり、日焼けの痕は速やかに治り、脂肪と筋肉がどんどんついて、医師に退院を許可された時には、赤子のようにつるつるとした健康的な容貌になっていた。特注した義眼を入れてから彼は病院を後にした。嵌めるとどうしても斜視のようになってしまったが気にしなかった。
前線に復帰してからのガルシアの働きは凄まじかった。遊撃部隊の指揮を任され、移動中や野営中の北軍の部隊をゲリラ戦法で次々に襲い、着実に戦力を削り落とした。見つかって激しい銃撃戦になると、無造作に敵陣へ近づいていって戦った。一発も撃たれることはなかった。
「使命を持った人間に、銃弾が当たることはない」
と部下たちに言って爽やかに笑った。
敵の戦意を挫くためにどんな残酷なこともやってのけた。
送られてきた捕虜の頭皮を部下たちに命じてすべて剥がさせ、袋に詰めて馬に積んで敵の陣地へ送りつけた。降伏してきた小隊全員の体の皮をまるごと剥がし、軍旗のかわりにポールに結びつけ、戦場ではためかせて敵に見せた。休戦を申し入れにきた指揮官と護衛兵たちの首を斬り落とし、幌馬車の周りにランプのようにずらりと吊るして戻してやった。五百人の大隊がそれで逃げた。戦わずして勝つやり方でガルシアは手柄を上げ続け、一年で中佐に昇進した。『皮剥ぎガルシア』の悪名は、敵と味方両方の兵士たちを震え上がらせた。
南軍の敗北で戦争が終わると北軍がガルシアをスカウトに来た。各地の南軍の残党を狩り立て、アウトローの集団を取り締まり、治安維持のために働いてくれれば戦犯にはしないと持ちかけた。大佐への昇格を条件にガルシアは北軍の依頼を引き受け、旅団を組んで旅をしながらかつての仲間たちを狩りまくった。
連邦政府の走狗として働きながら、殺戮の連鎖を広めるための新しい方法を彼は探していた。大きな戦争が終わった今、ただ残虐に振る舞うだけでは使命を果たせないと分かっていた。
旅の途中で土地土地のネイティブとガルシアは交流を持つようになった。白人を狩る白人、敵の敵ということで、彼の旅団は歓迎された。特にナバホと懇意になった。頻繁に情報をもらったり、ガイドを頼んだりしているうちに、土地の精霊祭に招待された。何世代も前の祖先たちが抱いていた感情を、その場の人間全員で共有するという儀式だった。確かに見知らぬ誰かの感情がガルシアの中に入ってきた。何をしたのかメディスン・マンに訊いた。
『魂の傘』の中に全員を入れた、ということだった。
『魂の傘』には祖先が生前に抱いていた感情が染み込んでおり、その中に入った人間の魂は同じ感情で染められる。
見つけた、これだ、とガルシアは思った。
日を改めてメディスン・マンを訪ね、多くの人間を入れることができる『魂の傘』の作り方を教えてくれと頼み込んだ。積まれた金塊を半眼で見ながらメディスン・マンが静かに答えた。
「お前は黒魔術を行うスキン・ウオーカーと同じ目をしている───帰ってくれ」
その夜、ガルシアは旅団の部下たちに命じてメディスン・マンを誘拐し、岩場の洞窟に閉じ込めて、言ったとおりにしなければ家族の頭の皮を剥ぐと脅した。
「多くの人間とは、何人だ?」
仕方なしにメディスン・マンは訊いた。
「数万人、数十万人───もっともっと大勢だ。今生きている人間だけでなく、未来に生まれてくる者たちにも、殺戮の衝動を植えつけたい」
謳うようにガルシアが答えた。
メディスン・マンは真っ青になったが、家族を守るために『大きな魂の傘』の作り方を教えてしまった。
「・・・まず、我々ネイティブの女と契って、息子を産ませ、二人とも捨てろ」
「女にお前を深く恨ませ、息子をアウトローに仕立て上げろ」
「息子に犯罪をたくさん犯させ、その間に母親をお前が殺し、息子に恋人や妻ができたら、その女も奪うか殺すかしろ」
「そうして傷つけるだけ傷つけた上で、息子を捕らえてお前が殺せ。考えられるかぎり無惨なやり方で絶望させながら処刑しろ」
「そうして死んだ息子の血を、息子の拳銃に吸わせるのだ。息子の魂と、息子の拳銃を、血の糸でしっかり結んでおけ。そしてその拳銃を戦場に放り込んでやれ」
「息子の呪いで守られて、百年くらいは壊れることなく、その拳銃は大勢の人間を殺し続けることだろう」
「悪霊と化した息子の魂は、時とともに空の高みへ昇り、世界を覆う『大きな魂の傘』になっていくだろう───そうするためには、荒れ地の真ん中で、大きな岩を処刑台に使い、そこに息子の怨念を刻みつけておくといい」
「血の糸で結ばれた拳銃が戦場で人間を殺すたびに、『大きな傘』となった息子の魂に、死の瞬間の恐怖が伝わる」
「その恐怖と憎悪の感情は、さらに息子の魂を傷つけて穢すだけでなく、『大きな傘』の下に入った数え切れない人々の魂も、同じように傷つけ穢すだろう」
「殺す感情と、殺された経験を、意識の底に刷り込まれることで、人々は知らず知らずのうちに大きな戦争へと向かっていき、果てしない殺し合いのループを作り出すことになるだろう」
「この『大きな傘』を悪用した魂の大量殺戮は、お前が年老いて死んでしまったずっと後の世において、息子の拳銃が壊れてしまうまで、数百年は続くだろう───これでいいか?満足したか?汚らわしく愚かなスキン・ウォーカーよ」
一息に喋り終えてからメディスン・マンはガルシアを見つめた。その目には勝ち誇った光があった。自分の語った壮大な計画を、たった一人の人間に実行できるはずがない───と強く確信していたからだ。
ガルシアは目を閉じ、黙っていた。
長い間動かなかった。
やがてぱっちり目を開けた。ぎゅるり、と義眼が正面を向いた。心の底からの笑顔を見せて、彼はメディスン・マンに向かって言った。
「ありがとう、すばらしい計画だ。すべてお前の言う通りにしよう!」
呆然として口を開けたメディスン・マンを撃ち殺し、息子を産ませる女を探すため、ネイティブの居留地へとガルシアは馬を走らせた。
*
ガルシアは様々な部族の女たちと関係し、十三人の子供を作った。
ナバホやホピやズニやアパッチやタオスの部族の人々は、白人の色を体に持った赤ん坊を嫌って迫害した。三ヶ月で六人の子供が命を落とし、七組の母子が村を追われた。無法者たちを雇ってガルシアはその後を追わせた。守るためでなく『傘』を作るためのマテリアルとして監視させた。病もうが飢えようが怪我をしようが命を落とそうが助けなかった。十歳を超えて生き残ったのはナバホの少年だけだった。その母親にルビーの原石を戯れに与えたことを覚えていた。ユタの荒野で獣のように少年は一人で生きていた。
使えそうだ、とガルシアは思った。
十一歳で殺人を犯し、賞金首として手配され、アウトローたちのリーダーになり、強盗旅団の頭目となった少年を、さらに十年観察した。膨れ上がった旅団の討伐が連邦議会で決議されたことで、時が満ちたとガルシアは判断し、討伐隊に志願して部下を率いて荒野へ走った。二十一歳の息子の姿を双眼鏡越しに初めて見たとき、『大きな魂の傘』の下で殺戮衝動に支配された人々が果てしなく殺し合うヴィジョンに襲われ、使命の成就を確信した。
焦らすように追跡し、息子が自分を餌にして罠を仕掛けてくるよう仕向けた。各地に散った手下たちは軍隊を派遣して捕らえさせた。それから息子にあてがって骨抜きにするための女を探した。
人選には苦労した。魂が飢えていて、情が深く、無垢でありつつ男を扇る女でなければならなかった。南西部の売春宿を徹底的に探させた。連れてこられた少女は完璧にニーズを満たしていた。息子を虜にしろと命じ、逆らえば家族を殺すと脅した。
女は仕事を完璧にこなした。息子を癒やし、去勢した上で、本気で彼を愛してもくれた。
あっけなく捕まり、銃殺隊の前に引き出された息子に対して、自分がお前の父親であること、犯罪者に仕立てて処刑するためにお前を産ませたと教えてやった。
なぜそんなことを、と驚愕の表情で息子が訊いた。
仕事だからだ、とガルシアは答えた。
世界を敵と味方に切り分け、豊かさを作り出すという使命を、息子であるお前にも手伝ってもらう───私を呪い、世界を呪い、敵対と分断の連鎖をつなぐ『呪いのバトン』になってくれ。
死に際の頭でこの話が理解できたかどうかは分からなかったが、
もっとこの女と一緒に生きたい、
という激しい生への執着が息子の顔に浮かんだのを見て、初めて息子を愛しいと思った。執着を抱けば抱くほど『魂の傘』としての邪悪さが高まり、殺戮の連鎖のスケールを大きくできるからだった。
「アディオス、ルビー」
使命に貢献してくれたことに対して感謝しながら射撃命令を出した。
爆散するように息子は死んだ。
その血をかぶった彼の拳銃───真紅に塗装されたピースメーカーが、彼の魂と結びつけられた。ガルシアは紅い拳銃を回収した。あとは息子の魂が空へ昇って世界を覆うのを待てばよかった。
これで物理現実世界における仕込みは終わった、と晴れ晴れした気持ちで彼は思った。
次は自分が死を乗り越えるための「手続き」を踏まなければ───。
息子を処刑した一年後にガルシアは軍を退役した。妻を娶り、男の子と女の子を一人づつもうけた後、四十三才でアリゾナ州の代議士に立候補し、当選して政治家の肩書を手に入れた。
当選した記念という名目で一挺の拳銃を作らせた。
ボディがブルースティールになるように焼き締めたさせた一品だった。
その青い拳銃を、紅い拳銃と一緒に、荒野に住まうホピ族のスキン・ウォーカーのところへ持っていき、二丁に呪術的なリンクをかけさせ、紅い拳銃に宿った力が青い拳銃に流れ込むようにした。そうしておいて紅い拳銃を部下の将校に譲り渡し、数年後にスペインやフィリピンで始まる大きな戦争に持って行かせた。
自らは戦場へ赴くことなく、他人の命をふんだんに使い、『魂の殺戮兵器』とその『スペア』を育て上げるシステムを構築した上で、ガルシアは体から魂を切り離すための訓練に入った。
手始めにピヨーテという幻覚作用のあるサボテンをスキン・ウォーカーからもらって使っていたが、すぐにドラッグを使わなくて魂を外へ出せるようになった。たった一センチや二センチであっても、体の輪郭から魂がはみ出すことで、ものの見え方や聞こえ方が大きく変わり、世界と自分との関係が激変した。距離と時間───特に時間が、体の外では意味を持たなくなった。時間とは肉体の新陳代謝のスピードであることをガルシアは知った。
家の中の食卓に座って妻や子供たちと食事をとりながら、まるでパン生地や蜂蜜のように魂を伸ばす練習をした。空を飛び、湖の上を滑り、裏山を超えて隣り町まで行ったりした。時間の流れを感じながら、時間が止まった状態にいる、という感覚の階層化を繰り返して経験することで、別々の場所に同時に存在するテクニックを身につけた。市議会の議事堂や、銀行のカウンターや、自宅のバスタブや、教会の懺悔室や、荒野の真ん中や、谷底の岩場や、山の頂上や、湖の底に、同時を魂を存在させてそこから情報の得ることができた。偏在性を手に入るなんて神のようだと思ったが、肉体の檻から解き放たれれば誰にでもできることだと分かった。体は馬や驢馬のような乗り物であり、自我の重心は魂にある、と繰り返し自分に言い聞かせながら、偏在する訓練を毎日続けた。五年後には十数ケ所に魂の触手を伸ばしたままで生活することができるようになった。ときどき肉体の中に触手を戻すと、一ケ所に存在してることの重さと硬さと鈍さに驚き、自分の濃さにショックを受けて、吐き気を催すことすらあった。
もう十分に精霊のようだとスキン・ウォーカーのお墨付きをもらったところで、ガルシアは次のステップ───物や植物や動物に憑依するための訓練に入った。ワタリガラスやコンドルやコヨーテやヘビに取り憑いてみたり、木の幹や岩の中に潜り込んでみたりした。最初の頃は憑依すると同時に意識を失ってしまったり、動物や物の状態に自分の方が乗っ取られていたが(犬のように吠えたり、馬のように嘶いたり、鳥のように羽ばたいたりして、家族や隣人たちを驚かせた)、少しずつ乗り物として「乗りこなす」ことができるようになった。それから鉱物や金属に憑依する練習に移った。動物よりはるかに難しかった。意識を持たない存在に宿ると自分の意識も飛ぶことが分かった。気を抜くとすぐに失神した。
五十代半ばで青い拳銃に自分を保ったまま憑依できるようになった。
拳銃の中で眠ってしまうとあっという間に時間がすぎた。金属の時間感覚にシンクロするせいか、ほんの一瞬まどろんだだけで一日たっていたこともあった。肉体を失って本格的に拳銃の中で眠りにつけば、一晩の体感で数百年を飛び越せるだろうとガルシアは思った。
*
七十代の半ばで代議士を引退し、八十二才で老衰で死ぬまで、ガルシア・ガブリエル・アズールは平穏で安逸な余生を過ごした───と周囲の人たちからは見えていた。殺戮者『皮剥ガルシア』のイメージは完全に消えていた。どうしてもあらぬ方を向いてしまう左目の義眼だけが、かろうじてその面影を残していた。彼にまつわる軍隊時代の噂を、家族や友人や後援者たちは作り話だと考えていて、葬儀に訪れた数少ない戦友や、かつての部下だった者たちの口から、事実であったことを聞かされても信じる者はいなかった(戦友や部下たちの大半に痴呆がきていたせいもあった)。幸せな結婚と家庭生活が故人の魂を入れ替えたのでしょう、と安らかな表情で棺の中に横たわるガルシアに花を添えながら、息子の討伐に同行した最年少の部下だった男が言った
それは違う、
と彼の隣りで自分の死体を見下ろしながら、ガルシアの魂が愉快そうに語った。
私の人格の大半は私の肉体の外にあり、体に残っていたものは影のように薄かった。だから妻や子供や隣人は、私と一緒に生きることができた。もしも『皮剥ガルシア』がひとつの肉体に収まったままで、この半生を過ごしていたなら、ここにいる人間は誰一人として生きていないし、生まれてくることすらなかっただろう───。
肉体の軛から解き放たれて亡霊となったガルシアの魂は、暴力的で若々しい生命力に溢れていた。葬儀場から離れた彼は、自宅の書斎の壁にかけてある青い拳銃の中に宿り、異国の戦場で紅い拳銃が吸い上げ続ける殺戮の記憶が、成層圏で世界を覆っている息子の魂を深く傷つけ、邪悪で大きな『魂の傘』に育てつつあるのを感じながら、種のように蛹のように百年にして一瞬の眠りについた。次の青い拳銃の持ち主によって目覚めさせられた時に始まる、崇高で悦ばしい使命の本番───大量殺戮の連鎖によって世界の構造がバランスを取り戻す美しくも破滅的な瞬間と、最後の紅い拳銃の持ち主となる極東の島国の少年が、息子の役割を引き継ぐことで、その生贄となること夢見ながら。
(続く)
長編小説は完結するまで、詩は100本書けるまで、無料公開しています。途中でサポートをもらえると嬉しくて筆が進みます☆
