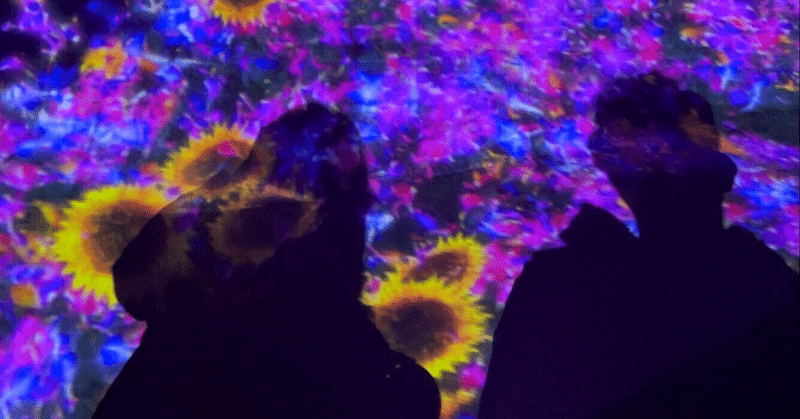
恋で生計は立てられない 第二章「幸せごっこ」1
家に帰る足取りは軽かった。ずっと味わっていなかった心の軽さだった。
自室に引っ込んで、再び名刺を穴が開くほど見つめる。
白。
一昔前の、ペットにつける名前として流行りそうな簡単な印象を受けたが、むしろこのそっけなさがいいのかもしれない。凝った名前じゃなくて好印象だと、自分の都合のいいように脳みそが解釈を始める。
白。どんな男だろう。
素性のわからない相手を想像するうちに、指がひとりでにスマホを掴んでいた。
目覚めると、出社時刻をとうに過ぎていた。
会社に休みの連絡を入れて、久しぶりに何もしない午前中を過ごした。一階に降りて家族と顔を合わせるのが嫌なので、自室でぼうっとする。窓から見える外の景色は、よく晴れた青空と向かいの家の年季が入った屋根瓦。今までと何ら変わりのない風景。けれどいつもと違う心境。私は堕落の道を行く。何かが吹っ切れたような、奇妙な充足感だった。まだ何も始まってないのに。
金で処女を捨てられるのか。
思えば思うほど、愉快だった。
今まで自分の内側でくすぶっていた何かが、放出の時を迎えたかのように、ここから出られるのだと悲鳴のような歓喜の声を上げる。
今、私は、無敵だった。
クローゼットを開け、自分ができる精いっぱいのお洒落を身にまとい、いつもより入念にメイクを施し、家族とあいさつも交わさず、黙って家を出た。
日射しが降り注いで、少し暑さを感じた。そろそろ日焼け止めを買わなければいけない時期だ。焼けたらどうしよう、と二十九年間一度も思わなかった心配を感じた。
一向に増えない貯金と、出ていく一方の生活費。
あの時私は確かにそう感じていた。けど結局は自分の金だ。散財しようが何しようが、私の勝手じゃないか。どうして今まで開き直れなかったのだろう。
昨日の夜に調べておいた、名刺の店までの地図をマップアプリで見る。
東京都からは若干遠くても、ここなら同僚や上司に会う可能性もない。むしろ好都合だ。
早足で、私は駅への道を急いだ。
駅前のカフェでブランチを取り、化粧室でメイクをしつこく整え、入念に歯を磨く。鞄に常備している携帯歯ブラシはいつどんな時でも役立つ。
予約の時間まで、あと三十分はあった。
『極楽浄土』は初心者歓迎のサービスを行っていて、それぞれの部門ごとに分かれたトップキャストの一人と特別接待できるクーポンを配布していたので、私もそれに乗っかる。部門は『ダンディ』『ワイルド』『爽やか』など、多岐にわたっていた。その中の『癒し』部門に私はチェックを入れていた。優しい男が好きだからだ。マッチョみたいなやつも、俺様みたいなやつもいらない。そばにいるだけで心が癒されるような、天使のような性格のいい美形を求めていた。
あるはずもない楽園を、ずっと探し続けているように。
でも、それももう終わり。楽園は見つかった。後悔はない。
予定時間より早めに、私は電車に乗った。
店の外観は小洒落た書店のようだった。明治の文豪の本などが取り揃えてあるような、雰囲気のある店構えだ。とても性行為をサービスする風俗店には見えない。
金をじゅうぶんに持ってきているのを確認し、入り口の扉を開ける。
店内は存外に明るかった。
照明器具が、目に優しい品質を使っているのか、どこかリラックスできそうな光り具合だった。変にまぶしくもなく、暗くもなく。
すぐ向かいに、受付がある。
女性のスタッフが二人いた。
「こんにちは」と感じのいい笑顔を私に向ける。
「初めてのお越しでいらっしゃいますか?」
「はい」
まごつきながらも何とかスマホを取り出して、予約票を見せる。受付スタッフは確認すると私にスマホを返し、「お部屋はどちらになさいますか」と再び感じのいい笑みを見せて、Ipadのタッチパネルを差し出した。
部屋なんて、決めてなかった。一瞬取り乱しそうになりながら、あわてて「いちばん安い部屋でいいです」と早口に告げる。
「承知しました」と通る声で言い、スタッフはIpadを操作すると、鈍色の鍵を取り出した。
見たところ、普通の鍵だった。マンションのセキリュティにありそうな、何の変哲もない、みんなが持ってるのと同じ鍵。
この建物は、マンションなのか。
それを改装して、風俗の商いを始めたのだろうか。
チェーンのついた鍵が、私の手に渡る。
3‐12。
鍵と一緒にチェーンにくくられた部屋番号。
「予定時刻より早めの到着なので、そちらで少々お待ちいただきます」
「あ、はい」
「三階の、十二号室のお部屋へどうぞ」
「はい」
あっさりと、私は処女を捨てる場へ送り出された。
エレベーターを見つけ、ボタンを押して乗りこむ。中は本当にごく普通のエレベーターだった。安っぽい鏡が私の全身を写す。覚悟を決めたはずなのに、そこにいる自分の顔は不安げに揺らいでいた。つくづく情けない顔だ。もとから、誇りを持てたことなどないけれど。
三階に着いた。
自動ドアが開けられ、ふらふらと外へ出た。コンクリートの廊下。それぞれの部屋の場所にオレンジ色の電気が点いている。十二号室は廊下の突き当たりにある角部屋だった。表札には「3‐12」と書かれている。
おそるおそる、鍵を差し込んでみた。
カチャン、と無機質な音が鳴る。
開いた。開いてしまった。
「どうしよう。どうすればいいの」
声に出して、不安な気持ちを吐き出した。ここに来て焦りと恐怖感が這い上がってきたのだ。
逃げようにも逃げられず、仕方なく家の中に入る。
中は、あらかじめ証明が点けられていた。真っ暗ではなくてほっとするとともに、玄関から見えるベッドルームが生々しく感じられてしまう。
だって、そういう行為をするために来たんだし。
そろそろと、まるで空き巣がするような足取りで前に進んだ。トイレ、脱衣所、風呂場、そしてダイニングキッチンとリビングルーム。ざっと見て1LDK以上はあるだろうか。一人暮らしには広く、二人暮らしを演出するような内装だった。寝室には二人分のキングスベッド。柔らかそうな布団は綺麗に整えられている。そばにはちょうど自分と相手が座れそうな、ふかふかのソファー。真向かいにはテレビ。恋愛映画らしきDVDがデッキのそばに飾ってあった。ダイニングには冷蔵庫が設置されており、キッチンはガスコンロではなく、電気で熱するタイプの流行りの設備だ。
見た感じ、恋人との同棲生活を彷彿とさせる、もしくは新婚カップルの二人暮らしのような、幸せに満ちた空間演出だった。
「こんな部屋なんだ……」
誰に聞かせるでもなく、私はつぶやいた。
これから、この部屋で、男の人と。
ぞくりと、快感のような、けれどやはり怖さのような、説明のつかない感情が私の内で暴れ回る。
嬉しくて、でも少し後悔もしていて、けれど引き返す気もなくて、いっそ死んでもいい気持ちであの日画面をタップしたんだ。
だから、何がどうなっても、私が決めたのだから私の責任でしかない。
それが結局、怖かった。
ベッドに座って、何をするでもなく、ただ途方に暮れた。
自分の行動は間違っていたのか? もし今日のことがバレたらどうしよう。親に、世間に、見つかったら? 生まれつきのマイナス思考が輪をかけて私の首を絞め始める。
勇気なんて、出さない方がよかったのか。
涙が出そうだった。
その時、ドアが開く音がした。
心臓が跳ね上がる。
人の足音。
白だ。白が来たんだ。
一体どんな顔をしているのだろう。しぐさや手つきはどんな風なのか。本当に私を傷つけたりしないのだろうか。
膝に置いた両手をぎゅっと握りしめる。
足音が近づいてきた。
ベッドルームのドアが開かれる。
びくびく震えながら、私は決死の思いで振り返った。
目に映ったのは、
「こんにちは」
にっこりと微笑む、天使だった。
○
2へ続く。
