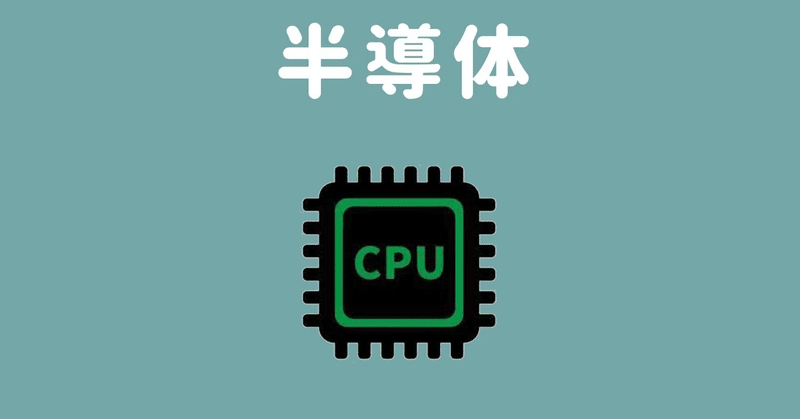
半導体はなぜ特殊?-現代産業のコア-
半導体とは、金属ほどではないが、石やプラスチックよりも電気を流す中間の物質……
なんだか分かりにくいし、ピンと来ない…
半導体の特徴は、半導体の「電気的特性」が他とは全く異なる現象を示すことだ
特徴的な挙動にはこんなものがある。
・太陽光発電
・電流の一方通行
・電界効果トランジスタ
・ゼーベック発電
・制御スイッチ
…
これらは全て半導体によるものだが、
「電気的な特徴」によるものである。
ちなみに幾つか相互に関連のある内容もあるが、それぞれ全く別の現象もある。
金属で言えば、サビが発生する原理と磁石のできる原理のような感じだろうか。
1個1個の原理は大学でやるようなものだし、材料分野の量子力学が必須だ。気になる人は1個ずつ学ぶと良い。
半導体のイメージ
さて半導体と聞いて何を思い浮かべるだろうか?
シリコンという単語を知っている人は結構知識人だと言える。
その原料がいわゆる砂、普通な最もありふれた材料であることを知っている人は博識と言って良い。
半導体の唯一無二の代表格はシリコンだ。
元素記号Si。
材料は酸化ケイ素、いわゆる珪砂である。
と言われてもよく分からないだろう。
もっと分かりやすいものはないかと言われても
答えは「これしか無い」
一応他にも色々ある
・ゲルマニウムGe
・セレンSe
・炭化ケイ素SiC
・窒化ガリウムGaN
・ガリウムヒ素GaAs
・インジウムリンInP
…
ちょっと待て、全部知らない!
となるだろう。
それはそうだ。この世の物質は大体金属か不導体であり半導体の種類はそんなにない。
(物質の組み合わせを研究することで新たな半導体は生まれている)
そもそも半導体が電子部品としてちゃんと使われ出したのはここ80年で大体シリコンやゲルマニウムしかなかった。
要は全部人類の科学が生み出した物質なのだ。
電子部品以外の半導体を知っている人の方が珍しい。
半導体はほとんどがシリコンだ。
それがわかれば一般的に十分だ。
あとはこのシリコンに色々ビミョウな成分を混ぜた種類の半導体、
「n型半導体」「p型半導体」
を作り、あとはその組み合わせでいろんなことが起こる。
詳しいことはもっと調べてみれば良い。
ちなみに「シリコンゴム」は半導体とは一歳関係ないから注意してほしい。
シリコンゴムやシリコーンと呼ばれるものは全て酸化ケイ素の物質だ。半導体になるのはあくまでほぼ純粋なケイ素Siだけだ。
あとがき
筆者は大学を出ているが、そこでは工学の材料分野を学んだ。半導体だけで無く、金属やセラミックについても多く学ぶ。物理と化学の総合分野と言って良い。
つまり金属やセラミック、有機物や無機物、共有結晶やイオン結晶、気体や液体や固体、温度や体積や強度やバネ性など、
あらゆる化学的な知識と物理的な知識を組み合わせている「現代産業の科学」の基本を学ぶわけだ。
半導体はその中の一角を占めており、その原理は高校どころか大学の初等では太刀打ちできないほど「現代的」だと思う。
それこそ本当に教師を必要とする文化だよなあ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
