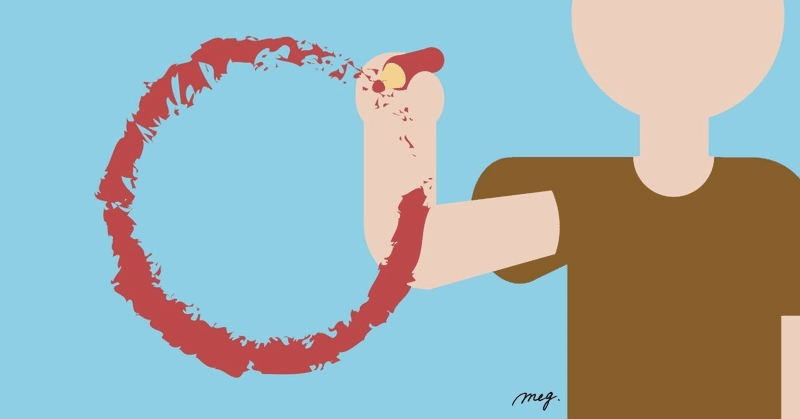
気付かずやっていることに気付くには
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「自分が気付かないでやっていることだから、それに気付くためにはどうしたらいいんですかね?」
そんな話を仲間とのミーティングでしていました。
話題は、仲間が最近参加したとある勉強会の内容についてでした。
そこでテーマになっていたのが「他者の話を聴く」ということについてだったそうです。
勉強会の中身をある程度細かく教えてもらったわけですが、ザックリ言うとこんな内容だったということなんだろうなと以下のように捉えました。
「“対話”において、他者の話を聴くという時には“評価をせずに聴く”ということが大事。でも、人の通常の営みの中で“評価をしないで話を聞く”が行われていることはほとんど無い。自覚無く“評価をしながら話を聞く”をしてしまっていることが多い」
そんな内容だったんじゃないかなと受け取りました。
その話を聞いて真っ先に思い浮かんだのは、「自分が他者の話を聞いている時に、“評価をしているor評価をしていない”と気付くことがそもそも果てしなく難しいんじゃないだろうか?」ということでした。
そもそも、日常会話のやり取りで行われる「それ、わかるわ~」という的な反応や、「え、マジありえなくね?」みたいな批判的な反応などの、ごく普通のやり取りですらも、既に“話を聞いた人の価値判断による評価”が行われているわけです。
「それ、わかる」というのは、「(私の価値判断で)わかるorわからない」という評価が下された結果の反応ですし、「ありえなくね?」も「(私の価値判断で)ありえないorありえる」という評価が下された結果の反応です。
仮に、評価を下さず話を聴くとしたら、「あなたはそう感じた(考えた)んですね」という受け止め方になるでしょうし、更に共感を示すのであれば、自分自身があたかもその他者と同じ状況におかれたらを想像してどう感じるかを伝えるくらいかもしれません。
とは言え、上に挙げた例のように「わかる」などの同感的な反応ばかりなのであれば“評価”が行われたとしても何の問題も起きないかもしれません。
だけど、実際には批判的な“評価”や否定的な“評価”が起きることも多々あって、「私はそうは思わないんだけど」とか「いや違うって、そうじゃないから」とか「いや、今のおかしいだろ」みたいな反応が起きることもあるわけです。
もちろん、否定的な評価を受けた側が、とても冷静でとても賢くて、仮に自分自身が間違っていたという事実に気が付くことができた上で、相手の主張を受け入れて考え方を改める。
そんなことが瞬時にできるのであれば、特に何の問題も起きないのかもしれません。
でも、そんなことができる人には今まで会った事がありませんし、そもそも、僕自身がそんなことができるわけもありません。僕だったら、そんな評価をされたら「何言ってんだコイツ?」って思ってしまうのが関の山です。
そんな僕は、自分の心の狭さを自覚しているので、「せめて僕と話をしている相手が、僕と同じような嫌な思いをする事の無いように」と思い、可能な限り「他者の話の内容は評価しない」とい事を念頭に置いたうえで対話的に話をすることを心掛けるようにしています。
そんな時に気を付けているのは、僕自身の内側に「え?何でそんなこと言ってるの?」と感じたり「自分には理解できない考え方だなぁ」と感じたら、質問をしてその理由を聞いてみることにしています。
そうして、もしも相手がその理由を話してくれれば、質問をする前の段階よりも少しは「この人はそう考えるんだな」と受け止めることができるようになったりします。
とは言え、そもそもの話ですが「僕自身が納得できるかできないかに関わらず、色んな考え方をする人がいる」というのが大前提です。
だから、たくさん話をしていても、と言うかたくさん話をすればするほど“分かり合える部分”も増えますし“分かり合えない部分”も増えていくんじゃないかなと思うんです。
その“分かり合える部分”と“分かり合えない部分”がどこいらへんなのか、その度合いの大小はどれくらいなのか、そんなことが「仲良くなれるかどうか」に関わってくるのかもしれません。
だけど、世間では「“論破”という事に価値を見出したり魅力を感じていたりする」なんて話をよく見聞きします。
そして、そんな“論破”を好んでやりたがる人が、組織の中にいて猛威を奮っていたりすると、その組織では必ず諍いや揉め事が頻発していて、組織としての本来の力(人が集まり協力して一人では成し遂げられない事に向かって進んで行くこと)が発揮されません。
その為、論破をする人は「俺、論破してやったぜ」と思ったその瞬間だけは気持ちが良いのかもしれませんが、組織としては何の成果にも繋がらないどころか、非協力体勢を生み出す要因になったりしてマイナスになっているケースをよく見聞きします。
もちろん、論破された人はダメージを負ったりネガティブな感情が渦巻いていたりするわけで、これも結局、組織としてはマイナスになっています。
本来、“同じ目的”を握り合って仕事に臨んでいるはずの組織の中ですらこうなんですから、日常生活の中で何の目的も握れていない人同士であれば、遺恨は残りまくるでしょうし、負の感情は渦巻くでしょうし、いいことなんて何も無いんじゃないかなと思ったりしています。
仮に色んな話をした挙句、「仲良くなれない」となったとしても、別に諍いを起こしたり揉めたりする事も無いんじゃないかなと思っています。
「ああ、お互いに大事にしているモノが違ったね。それではごきげんよう」
こんな感じでいいんじゃないかなと思っています。
だからというのもあって、僕自身が他者と話をする際には、できる限り“対話的な姿勢”で、相手の話を“評価しない”で話を聞くことを心掛けて臨むようにしています。
でも、この“評価をしないで聴く”というのが、「きちんとできているのかどうなのか?」これを判断するのが、僕にとっては本当に難しいんです。
「本当に評価をせずに聴けていたのか?さっきのは評価じゃなかったのか?」
話を終えた後、そんな疑問が自分の中にずっと渦巻いているなんてことはしょっちゅうあります。もしかしたら、この世界のどこかにいるかもしれない“対話の達人”みたいな人には造作もなくできてしまう事なのかもしれませんが、僕にとってはこれが、と言うか、これ“も”永遠の課題なんだろうなと、随分と前から諦めて取り組んでいるところです。
だけど、自分自身でこれに気付けるように取り組むっていうのも、本当にマインドフルネスや瞑想みたいなもので半端じゃなく難しいなと感じています。
なので、やっぱり仲間に傍からチェックしてもらってフィードバックをもらうっていうやり方が、僕にとっては途轍もなくありがたいなと感じている毎日です。
何事も、一人じゃとても難しいけど、二人ならそこそこいける気がしています。そんな他力本願で今後も研鑽を積んで行こうと思っています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
https://www.protagoworks.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
