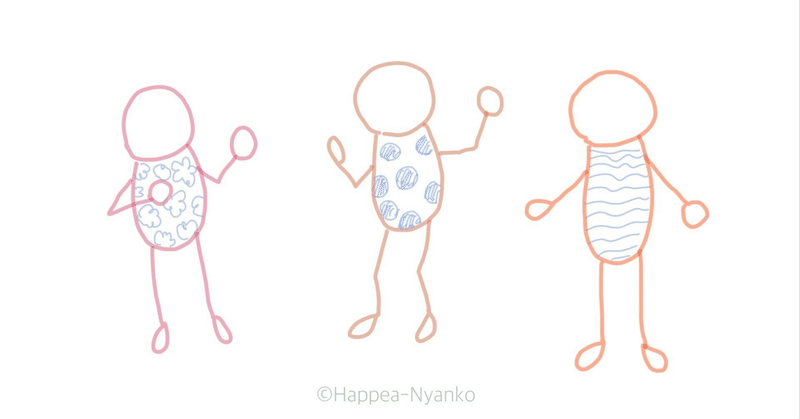
我らサル属ヒト科のヒト目
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「“ヒト・モノ・カネ”の中だと“ヒト”の部分が一番難しいし大変ですよね」
組織開発で他社に関わらせてもらっていると、経営者の方からこんな話をしてもらうことがよくあります。
ウチの事業として“ヒト”の部分だけに特化している仕事柄か、「そうかもしれないなぁ」なんて思いつつも、実際には「モノ・カネ」の部分の難しさや大変さについてはそれほどよく分かっていない部分が多いので、他の“モノ・カネ”と比較して難しいし大変かどうかはよくわかりません。
でも、少なくとも僕達が関わらせてもらってきた中で言えば、“ヒト”の部分での混乱が、その組織に対して大きなダメージを負わせたり、大きなリスクを抱えさせたり、時にはそれらが表面に出て来てしまったりして、“目に見える損失”として出てきてしまっていることもありましたし、そうでなければ“目に見えない損失”として出続けてしまっている状況を抱えているというのが、よくある状況でした。
“目に見える損失”が出ている時は、それはそれで大変ですが、そうは言っても“目に見える”わけなので把握もしやすいし、それをどうやって食い止めるかを考えて行動するのはそれ程難しいことではありません。もちろん、すごく大変ではありますが。
一方で、 ”目に見えない損失”が出ている時は、その大変さに気付いている人はほとんどいない場合が多いかなと思っています。何しろ“目に見えない”わけなので、誰もそこで発生している“損失”に気付かないまま過ごしている状態です。もちろん、気付いている人もいるのかもしれませんし、声も上げているかもしれませんが、その声が拾われたり共鳴したりということが起きないような状態に陥ってしまっているのかもしれません。この場合は、何をどうしたらいいかよくわからないまま、だけど、何だかよくわからないけど何かが上手くいっていないし順調じゃない気がする。だからとっても難しいし、とっても大変に感じてしまいます。
そんな状態にもかかわらず、問題発見があやふやなまま解決策だと思った何らかの手を打ったとしてもそれが徒労に終わってしまったりして、手を打つ以前よりも更に“よくない状態”になってしまい、“目に見えない損失”が拡大していく。なんて状態になっている組織が本当にたくさんあるのを見聞きしています。
組織にとって、こんなおっかない“目に見えない損失”が起きてしまう原因が何かといえば、そのほとんどが“人間関係”と言われる部分に起因しています。
そうです。「仕事を辞める理由」の上位にずっと君臨し続けるあの“職場の人間関係”というやつです。
この“職場の人間関係”が良くないと、それがどうして“見えない損失”に繋がるのか?
例えば、同じ部署のAさんとBさんの関係性が良くなくて、その二人の関係性を知っている他の同部署の人や他部署の人達がなんとなくその二人の関係性に気を使って仕事をしていくうちに、AさんとBさんが直接コミュニケーションを取らなくても仕事が回ってしまうようなコミュニケーション経路が構築されていったりすることがあります(本来、AさんがBさんに伝えるべきことを、AさんがCさんに伝えて、CさんがBさんに伝える、とか)。そんなことが繰り返されていくうちに、A・B間では、業務上必ず必要なコミュニケーションすらも取られなくなる。そして、そこに付随してくるのは「誰がどっちにつくのか」的な“A派・B派”みたいな関係性が構築されてきたり、その二つでは飽き足らず他にも“C派”とか“D派”みたいなモノができあがる。
こんなことが起きていれば、業務が円滑にスムーズに遂行されているはずがありません。何しろ、組織内でのコミュニケーションにムダが多すぎますし、ムダが多いということはそこでミスが起きる確率が上がりますし、実際にそういう組織で“コミュニケーションの齟齬”が発生していなかったことは一度として見聞きしたことがありませんので、間違いなく“コミュニケーションの齟齬”が発生しています。
“コミュニケーションの齟齬”が発生しているということは、当然ですが、その組織のメンバー各自が本来割り振られていてやるべき業務にもその“マイナスの影響”が出ていることは間違いありません。
そして、その“マイナスの影響”は、その組織の“顧客”に対しても、まさに“見えない損失”を与えています。
組織内のメンバーが“マイナスの影響”を受けた状態で仕事をしているのであれば、その“マイナスの影響”は、“顧客”に対して提供する商品・サービスである“モノ”のクオリティにも当然ながら“マイナスの影響”が出ているのは間違いありません。
例えば、製造業で顧客に納める製品が注文通りだとしても、実際にはもっと短納期で納めることができたかもしれませんし、その原因が、製造段階で起きていた加工ミスかもしれません。そんな“目に見えない損失”が起きていたかもしれないわけです(出荷前に気付ければいいですが、もしもそれが納品後に発覚してしまった場合には“目に見える損失”に変わっていくわけです)。
これは単なる一例ですが、そんな感じの“目に見えない損失”が起きているということは、“顧客”にとっては「本来、受けられるはずの高いパフォーマンスが発揮された高いクオリティのサービスが受けられていない」という“マイナスの影響”があるわけです。そして、このことに“顧客”が気付けるということはありません。もちろん、後々に“見えない損失”の原因が解消された暁には、「以前より良くなった」と“顧客”が感じることはあるかもしれませんが。
こんな風に、“人間関係”に起因している“マイナスの影響”というのが“目に見えない損失”を引き起こしているわけですが、そうは言っても「自分のやっている業務の中で、“マイナスの影響”が出ている」なんて客観的に気付くというのは途轍もなく困難なことですし、もし仮に気付けたとしても、それを気付いた本人の取り組みで、根本から是正していくということは途轍もなく難しいんじゃないかなと感じています。
だから僕たちは、組織の中でも“ヒト”の部分についてのサポートをすることで、「今よりももっと働きやすくなる」を実現できると考えて、組織開発を行っています。
そんな仕事をする中で、僕自身も冒頭の話をしてくれた経営者と同じように思っています。
「“ヒト”の部分は難しいし大変です」と。
「もうこれで分かり切ったぜ」なんて思うことはありませんし、毎度毎度「わからないなぁ…」と思うことばかりですし、毎日毎日「どうしたらよいのか?」と考え続けています。本当に難しいし大変です。
でも、仕事が円滑に進むために組織の内側の人達が「役に立つこと」に取り組んでいって、人と人の関係性が少しずつよくなっていっていくのを見ると、こんな風にも思うんです。
「“ヒト”の部分は難しいし大変です。でも、スゲー面白い」って。
冒頭のように思うことがあったとしても、諦めないで一緒に考えて取り組んでいければ、きっといつかこんな風に思える日も来るのかもしれません。
道のりが遠いのか近いのかは、そういう日が来てみないと何とも言えないところではありますが。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
