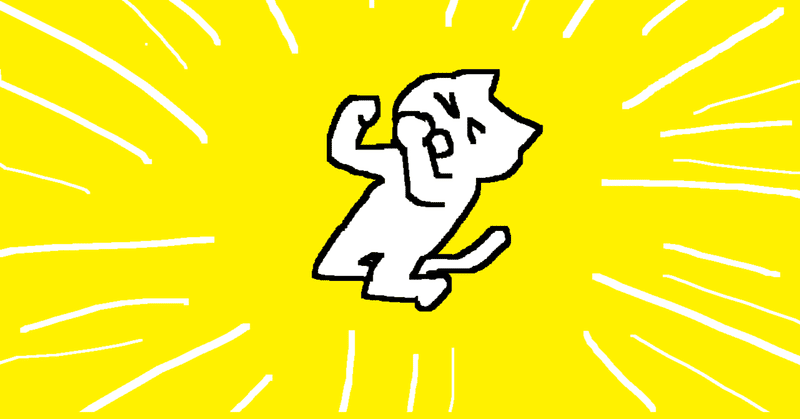
勝ち負けを気にしながらの勝負とは
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「これって、もしかしたら〇〇ってことなのかも…」
そんな思い付きのようなモノが、ふと“降りてくる”ことがよくあります。
特に、事務所が入っているテナントの廊下を歩いている時に“降りてくる”ことが多いので、これがあるたびに「ああ、このテナントはずっと借りていた方がいいのかもしれない」なんて思ったりもするわけですが、とにかくその思い付きのようなモノが、これまでに僕たちの仕事の材料になってきましたし、何度も窮地を救われてきました。
当事者である僕も、この思い付きのようなモノの話を真っ先に聞かされ続けてきた仲間も、この事実については疑いようもなく「確かに、“降りてくる”が無ければ今までの様々な局面を打開することができていなかったかもしれない」と認識しています。
とは言え、この思い付きのようなモノを僕が僕の意志で“降りてこさせる”ことは今のところ出来ていません。
名著と言われている『アイデアのつくり方』(著:ジェームス・W・ヤング)にもあったやり方を、はからずも実践していることになっているからこそ、ふとした時に(しかも、毎回トイレに行くために廊下を歩いている最も無防備な)“降りてくる”が起きているのかもしれないなぁ、なんて思っています。
そうして最近もまた“降りてくる”が起きました。
この思い付きのようなモノが使い物になるのかどうかを色々検証を進めているところですが、どうやらこれもまた新しい仮説として使っていけそうな感じになってきました。
それがどんなモノかと言うと、簡単に言えば「他者とのやり取りを“勝ち負け”で判断する人がいて、その人達の思考パターンと言動について」です。
どうやら、「他者とのやり取りを“勝ち負け”で判断する」ということが本人すらも自覚していないところで起きているらしいことが見えてきました。
少し考えてみれば「特に新しい知見でも無いよなぁ」とも思えてくるんですが、あらためて“そういう人”がいるんだと考えてみることで、これまでに多々あった不可解な発言や行動の謎がすんなり解けたような感じがしています。
例えば、仕事の目的から考えた時には「Aという選択をして行動することが最も役に立つことなのは誰が見ても一目瞭然」という状況の時にでも、自説を主張して別のやり方にこだわり、結果として案の定“望ましくない結果”が起きる。なんてことは、どこの組織でも起きていて、それがいつでも問題になっているわけです。
そして、それをやってしまう当事者も「何が役に立つことなのか?」を考えると、どうやら明確にわかっているということは普段の言動から見えてくるわけです。もちろん、それくらいわかりやすいモノであり、その人以外の誰もが「役に立つことはこれ」とわかっている状況もあったりするわけです。だけど、“役に立つこと”ではなくて、自説や自分のアイデアを実行してしまう、という現実が起きてしまいます。
そこに“勝ち負け”という判断基準を持ってくると、「どうしてこういうことになるんだろう?」という謎が簡単に解けてきます。
「だって、相手の言う事聞いちゃったら自分が“負けた感じ”がしちゃうだろ?そしたら悔しいし、誰かの言う事なんて聞きたくないんだよね」と。
仕事の目的や役割から考えてしまうと、「勝ち負けが判断基準になっている」なんて何だかよくわからない話にも感じますし、ただ単に“感情”の問題な気もしてきます。だけど、当人にとっては“仕事の目的”よりも、「どっちのアイデアが勝ったのか?」とか「自分が勝った」ということの方が大事になってしまうことがあるのかもしれません。
そして、“勝ち負け”を判断基準にしている当事者は、大抵の場合「自分は、“勝ち負け”を判断基準にして他者とやり取りをしている」という自覚を持っていないだろうということも見えてきます。
何しろ、“仕事の目的”を理解できているのに“自分の中の勝ち負けの判断基準”の方を大事にしてしまうんだとしたら、それは「「任せられた仕事の成果に責任を負うことは難しい状態」と言わざるをえません。だからこそ、“勝ち負け”基準の人は、その自覚がないであろうことが見えてきます。
ただ、「他者とのやり取りの中に、“勝ち負け”という判断基準が存在している」と考えてみることで、何かが少しわかったし見えてきたような気もしています。
何が言いたいかというと、「“勝ち負け”が大事なのであれば、自分の仕事を通じて“勝ち”を手に入れてもらえればいいんじゃないか?」ということです。
つまり、勝利条件を変更することができるかどうかを一緒に考えていける可能性について探ってみることができるかもしれない、ということです。
もしも、その人の勝利条件を「仕事の目的にちかづくために、目標を達成すること」に変更できたとすると、特に何の問題も起きなくなるわけです。当たり前の話ですが。
これを「理念の浸透」なんて呼ぶのかもしれませんが、「理念を浸透させるために何が必要なのか?」とか「理念が浸透しないのは何が足りないのか?」なんて考えてみることだけでは“勝ち負け”という判断基準の存在には気付くことができなかったということなのかもしれません。
その人にとって、“勝ち負け”よりも大事なモノはあるのか?
その人にとっては、“勝ち負け”がそれ以外のありとあらゆるモノよりも大事なのか?
その辺りの“感情”に焦点を当ててみることで、停滞していたところに光明が見えてくるような気がしてきています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
