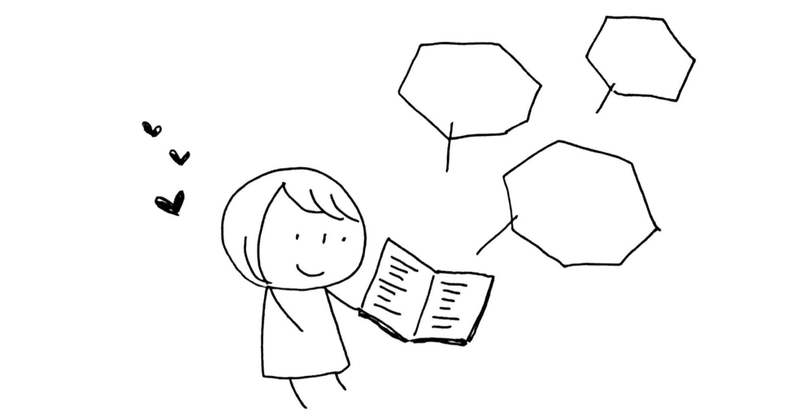
内と外を行ったり来たり
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「頭の中にある漠然としたイメージを言語化してアウトプットする」
巷でよく聞く言葉ですし、僕たちも“これ”は「仕事をする」うえでとっても重要なことだと考えています。
僕たちが「仕事をする」うえで“これ”が重要だと思っているのは、こんな理由があります。
まずは、“仕事”は基本的には「自分一人で完結するモノではない」ということがあります。
どんな仕事であれ、自分の内側から湧いてきたモノを自分の内側でだけ完結して見返りが得られるなんてことはありません。
“その仕事の結果”を受け取った“自分以外の他者”が“見返り(対価や感謝や変容や成長など)を渡してくれる(示してくれる)ことで“仕事”として成立するわけです。つまり、どんな仕事であっても、例外なく“他者”の存在が必要なのが“仕事”です。
そんな風に、必ず“自分以外の他者の存在”があってこそ成立するのが仕事ですから、“自分の内側”にあるイメージを言語化して“自分の外側”に出して、自分と自分以外の他者との間で“同じイメージを共有する”ことで、目的や目標や手法などをできるだけズレることなく握り合って、そこに向かい、それらを使って、協力しあって“コト”を成し遂げる。
これが、冒頭の言葉を重要だと考えている理由です。
なので、もっと正確に言えば、「頭の中のイメージを言語化すること」や「アウトプットすること」というのは、“目的”とか“成し遂げたいこと”ではありません。「言語化する」とか「アウトプットする」というのは単なる“手段”でしかありません。
その先にある「自分以外の他者とイメージを共有する」をして、更にその先にある「同じ目的をズレずに握って、そこに向かって、“コト”を成し遂げる」というのがゴールです。
逆に言えば、「同じ目的をズレずに握って、そこに向かって、“コト”を成し遂げる」ということができないのであれば、どれだけ「言語化する」をしようが、どれだけ「アウトプットする」をしたところで、あんまり意味はありません(ただ、「自分の内側にあるモノを言葉にできてスッキリした」というような独りよがりとか自己満足ができるという“意味”はあるかもしれませんが)。
そうやって考えてみると、冒頭の「頭の中にある漠然としたイメージを言語化してアウトプットする」というのは、実はとっても“言葉足らず”なのかもしれません。
“言語化”するにも“アウトプット”するにも欠かしちゃいけないのが、「同じイメージを必要十分なレベルまで共有できたことが確認できるまで、解像度を上げていく」ということが必要不可欠なんじゃないかと思っています。
これは、自分自身もやりがちなので自戒の意味もあるんですが、自分の中に存在している漠然としたイメージについて語りだすうちに、“自分にとっては”とてもしっくりくる言葉が出てくることがよくあるわけです。そして、その“言葉”に付随している表現についても“自分にとっては”とてもしっくりきてたりするわけです。
だけど、それを聞いてくれている仲間から「すみません。もうちょっと説明してもらっていいですか?」とその直後に言われたことで、“言語化”できたことでスッキリして、なんなら悦に入ってた自分にハッとして、「ヤバイ、今ので伝わってなかったか」と、そこから更に“翻訳”するための言葉を探しながら語っていく。
そんなことがしょっちゅうあるわけです。
そうして、“翻訳”しながら、色んなたとえ話などを使いながら、語ったことについてたくさんの“問い”を投げかけられてそれについて考えてまた語ったりを繰り返しながら、ようやくどこかのタイミングで“イメージの共有”ができたところで、そこからやっと“仕事”として動き始めるようになったりします。
ウチの社内では、こんな感じで対話をしながら進めていきますし、実際に他社の組織開発で関わらせてもらう時にも、“曖昧な言葉”とか“人によってイメージが変わってしまう言葉”については、それを“翻訳”してもらって、みんなで「イメージの共有ができるようになる」ために対話を繰り広げて、たくさんの“問い”を飛び交わせながら進めていきます。
こうやって考えてみると、例えば冒頭の言葉のような巷間で「さもありなん」と思われて飛び交っている“耳馴染みの良い言葉”も、実際には「なんのためにやるのか?」ということが抜け落ちている状態で流通していることがたくさんあるんだなぁ、なんてことに気づかされます。
もしかしたら、「なんのためにやるのか?」が抜け落ちているように感じているのは僕だけであって、僕以外の世間の人たちは「言語化やアウトプットをするのは“他者とイメージを共有するため”なんて前提中の前提だろう」という共通認識があるのかもしれません。
もしもそうだとしても、冒頭の言葉のように“流通している言葉の形”としては、やっぱりどこからどう読んでも「なんのためにやるのか?」が曖昧な状態になってしまっています。
これを“仕事”の場で使うんだとしたら、やっぱり一番大事な「なんのためにやるのか?」という“目的”について、“誰であっても同じモノを握れる状態”になっている方が“役に立つこと”をするのに向いているんだろうなと思います。
そんなことを考えているからなのか、「同じモノをズレずに握りたい」という思いが先行しているからなのか、僕の場合はどうしても伝えたいことが多くなってきてしまい、こんな風にたくさん書いたり話したりしてしまっているので、「もっと簡潔に伝えられるようになりたい」という願望は抱きつつも、でも、「共有したいモノを共有できないかもしれない」なんてことが少しでも頭の中にあると、このnoteのようにたくさん言葉を使って、「何とかして少しでも自分の中にある漠然とした思いを形にして、できるだけズレが無いように受け取ってもらいたい」と、ついつい語りまくってしまうようです。
そんな自分の姿をこうやって客観的に受け止めることができるのも、自分の中の思いを言語化してアウトプットしつづけているからなのかもしれないと思うと、ついつい冒頭の言葉を使ってしまうのかもしれません。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
