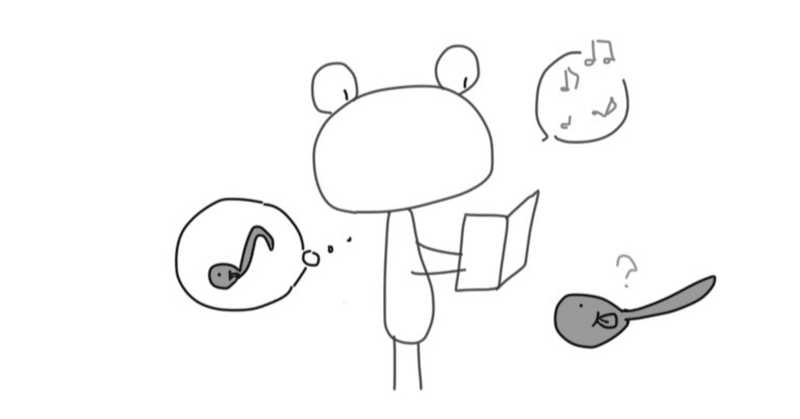
似たようなモノだと思ってたけれど
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
仕事を通じて、様々な組織に外部から関わらせてもらう中でいつも感じていた“違和感”についてなかなか言語化できないでいてもどかしさを感じていたことがありました。
「この“感じ”は何て言ったら伝わるんだろうなぁ」なんて思いながら色んな話を手を変え品を変えしてみたりしてきましたが、伝わることもあれば伝わらないこともあり、なかなか「これだ」と言うような話ができていない感じがずっとありました。
先日、とある本を読んでいた時に、僕がずっとかんじていたその“違和感”について、とってもわかりやすくてとっても短い言葉で説明がされている部分がありました。
それを読んだ時に「これこれ、これだよ!」と、仕事をしている仲間の手を無理やりに止めてもらって、その部分を共有したくて朗読をして聞いてもらいました。
そこには、大体こんな感じのことが書いてありました。
“自主的”と“主体的”は違う。“自主的”とは「自ら率先して行動する姿勢」で、“主体的”は「自分の意志・判断に基づいて行動すること」。“主体性”を発揮するには、“自分以外のモノ”による方向付けが必要。組織で働くうえで必要なのは"主体性”であり、組織による方向付けがあってはじめて発揮される。「“自主性”に任せる」というのはただ単に「あなたの好きにやって」となってしまって「目指すべきもの」が無い状態になってしまう(意訳)。
僕たちが仕事として組織に関わらせてもらう場合には、必ずその組織を経営する経営者の方と契約を交わしています。それはそのまま「経営者が、経営判断として、組織開発を行うと決めた」ということに他なりません。
上の“自主的”と“主体的”の話で言えば、「経営者は“自主的”に行動をしていながら、それはそのまま“組織の方向付け”に沿った“主体的”な行動でもある」ということが言えます。
中小企業の経営者であれば、経営者自身の“自主性”はそのまま“組織の方向付け”に必ず合致した“主体性”の発揮になってしまいます。
そういうベースがあるからなんだろうとは思うんですが、中小企業の経営者の方々の多くが「社員の“自主性”が大事」ということを言葉でも言っている場合が多いですし、指示命令の出し方としても「自ら率先して行動する姿勢」を推奨していることがよくあります。
だけど、当然のことながら社員の方々は“組織の方向付け”を自分ですることはできません。
なので、社員の方が“自主性”を発揮して仕事をすると「自ら率先して行動する姿勢」になるわけで、その時の“基準”だったり“拠り所”になるモノは、その社員の方が内面化している“個人的な価値観”から出てくる“自主性”に他なりません。
そんな“自主性”が、たまたま“組織の方向性=組織の目的”と合致していれば万事OKになるんでしょうが、そうなることはほぼ偶然のようなモノでしかないんじゃないかと思っています。
なぜなら、これまで数多の働く人や求職者の人達と面談をしてきた経験から、“個人の働く目的”と“組織の仕事の目的”が完全に一致している人には、これまでに一度も出会ったことが無いからです。
僕がこれまでに出会った中で言うと、“個人の働く目的”と“組織の仕事の目的”が一致していた人達はみんな組織を経営している人達でした。
だからこそ、経営者以外の“組織で働く人”にとっては“組織の方向付け=組織の目的”という「その人自身の外側に存在している“基準”のようなモノ」が絶対に必要です。
そんな「その人自身の外側に存在している“基準”のようなモノ」が存在しているからこそ、それが存在してそれを拠り所にしてはじめて「自分の意志・判断に基づいて行動すること」という“主体性”が発揮されるわけです。
これまでに関わらせてもらった組織の中で、「“組織の方向付け”なんて一切存在しないから、本当に言葉通りの意味で、あなたの好きにやりたい放題やってもらっていいよ」と言って仕事を任せている組織は見たこともありませんし、そんな経営者の方にも出会ったことはありません。
当たり前ですが、組織が存在している以上はその組織には"組織の方向付け=目的”が必ず存在しています。
であれば、そこで働く人達に発揮してもらいたいのは"自主性”ではなくて"主体性”であるはずです。
そう考えると、まずはその組織の“方向付け=目的”を、そこで働くすべての人が明確に認識できるようになっている必要があるわけです。
だけど、その“方向付け”を経営者と同じレベルで理解して体現できる人は存在しません(もしもいるんだとしたら、すぐにでもその人に経営を代わってもらえばいいんじゃないかと思うんです。そうすれば“経営”という大変なコトからはすぐに解放されるうえに“組織の方向性”は今までと同じようにいくはずですから)。
だけど、「自分の意志・判断に基づいて行動すること」を組織の一人ひとりに体現してもらうことができれば、恐らく経営者のイメージする“組織の在り方”に今よりもグッと近づいていくんじゃないかと思うんです。
だからこそ、一人ひとりが「自分の意志・判断に基づいて行動すること」ができるように“組織の方向性”について深く内面化していくための取り組みが、常に組織の中で継続して展開されることが必要であり重要になってくるわけです。
なんてことを、その本を読んでいて今まで自分の中でなかなか言語化できなかった“違和感”がここまで言語化できるようになったので、いやホントに凄い本だったなぁと思っています。
こういう体験をするたびにいつも思いますが、本ってマジでスゴイツールだなぁと思います。
コスパもそうですが、何よりも“自分に必要なモノ”をいつだって“必要なタイミング”で学ばせてもらうことができるからです。スピリチュアルとは全く縁がありませんが、なぜか「この本が気になるなぁ」と思って読み進めていくと、そういうタイミングでそういうモノに出会えることがしょっちゅうあるんです。
自分の中に“違和感”としてしか存在していなかった何だかモヤモヤとした実体の無い、でも、確実に自分の中に存在している“なにか”が、こうやって本の中の一語や一文によってバチっと繋がってズルズルズルズルっと引きずり出されてくるようなこの感覚が、何度味わっても最高にスリリングだし気持ちがいいし楽しくてしかたがありません。
こういうモヤモヤした“違和感”がハッキリした形を伴ってくると、また色々と捗りそうな予感がしてきています。
さーて、まずはこの話をマシンガントークで仲間に聞いてもらうところからスタートしていこうと思います。こういう時は相手の迷惑は省みないことにしています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
