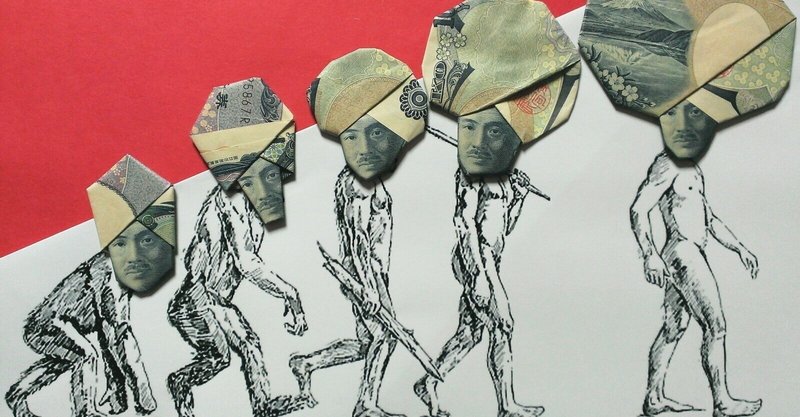
たとえば以前とは全く変わっていたとしても
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
最近、久しぶりな人達に会う機会がたくさんありました。
数ヶ月ぶりに会う人、数年ぶりに会う人、数十年ぶりに会う人、などなど。
だけど不思議なことに、その方々の印象は一様に、「見た目こそ変化していても、話をしてみるとそれほど大きく変わっていない」と感じるんです。
とても久しぶりに会うような場なので、そのほぼ全ての機会が、「何かの機会で顔を合わせただけで、深くじっくり話し込むような時間はとれない」という状況でした。
そんな状況だったから、印象が昔と変わらなかったというのもあるのかもしれません。
現に、僕が久々に会った人達の誰からも「君は変わったね」と言われたことはありませんし、人づてに「そう言っていたよ」と言われたこともありません。
だけど、僕からみた自分自身は、その人達の誰であっても、以前に会ったその日から比べると「まあまあ」なのか「かなり」なのか「全く」なのかはわからないけど、その後には必ず
「変化した」と言えるだけの自覚があるわけです。
自分で感じているその「変化」については、様々な角度から見ても変化しているわけです。例えば、「考え方」や「話す内容」や「話の展開の仕方」というような部分から、大きなところでは「生き方」といったところは、事実大きく変わっていますし、変化した自覚も伴っています。が、久々に再会した人から面と向かって「君は変わったね」とは言われません。
まだまだ「変化の度合い」が小さかった数年前であれば、今と同じような状況だった時に、この「相手が自分の変化を認識していない」という事実だけを切り取って、その事実だけを根拠にして、「相手が自分の変化を認識していない、ということは、自分が感じている変化は自分が感じ取れる程度の変化しかしていないのであって、言うなれば、ごくごく微細な変化であり、客観的にはその変化は存在しないのと一緒である程度の意味や価値しか無いのだ」と結論づけていたような記憶があります。
だけど、今現在の僕と以前の僕を比べた場合に、「変化していない」と言うための理由付けの方が苦しくなるくらいに、現実世界での変化度合いが大きいので、ここには特に異論を差し挟む余地は無いだろうとは思うんです(これが妄想では無いという程度の証言は、接触する機会の多い周囲の人からはたくさん挙がってきているわけなので)。
じゃあ、なぜ、久々に会った人からは「変わったね」という言葉は出ないのか?
そう考えてみると、一番の要因はやっぱり「話をする時間の短さ」だと言うのが見えてきます。話をする時間が短いと、「言葉を強く放つ人」とか「口調の強い人」とか「声の大きい人」とかが、その場の会話の主導権を握ったまま、その人が話したい事や聞きたい事を中心に一方的に会話の場を回してしまいます。特に、一般的な「世間話」とか「思い出話」とかいうようなモノにおいては、その特徴はより強く出てくるんじゃないか、と、これまでの人との話の内容を振り返ってみても間違いないだろうなと思っているんです。そうなってくると、その会話に参加している人達のもっと深いところにある「考え方」とか「価値観」といったものが見えてくる前に、いわゆる、「ノリ」に塗れた会話で終始してしまい、それまでのその人達のキャラに寄ったような話だけで終わってしまい、あまり中身の無いような話で終わっていく。そんな事がよくあります。
そうならないようにするためにも、「対話」が必要なんだろうなと思うんです。
だけど、「対話」は時間がかかります。「話をする人の話をじっくり聴く」のは、とても大事な事だから。それができなければ「対話」は成立しないし、そもそも「人の話をじっくり聴く」には聴く側の意志が必要です。「対話」というものについて、普段から意識をして生きている人はそんなに多くはありませんし、「人の話をじっくり聴く」という事に対して意志を持って臨んでいる人もそんなに多くはありません(これは、これまでの仕事の中で数多の人達の話を聴いてきた僕の実体験からハッキリとわかっている事なので事実であると言えるんじゃないかなと思っています)。
多くの時間と明確な意志を必要とする「対話」を行うには、やっぱり、それが可能な「場」が必要なんだなと、ここ最近の「久しぶりに会う人達との会話」を通じて、あらためて実感したところです。
そして、その「場」は、自然発生的に目の前に出来あがって現れるという事は、よっぽどの偶然に恵まれない限りあり得ません。
だから、「対話」をするには、そのための「場」を作らないと、実践する事はほぼ不可能なわけなんです。
そもそも、「対話」というモノが必要であると認識するという事が必要です。そもそも、「対話」をするには「時間」がかかると認識するという事が必要です。そもそも、「対話」をするには「場」づくりが必要だと認識するという事が必要です。そもそも、「人の話を聴く」ためには「意志」が必要だし、簡単にできるわけではないという事を認識する事が必要です。
こんな風に、「対話」をするためにはこれだけの「必要」が存在しているわけなので、つまり、他者の「変化」に気が付くという状況が発生するためには、それなりの苦労がついてくるというわけなんです。
そんな事に気が付いたここ最近の出来事でした。
なので、「自分が見ている自分自身の像」と「他人が見ている自分の像」とのギャップがある事は、「良くない事」では全く無くて、むしろ、「ギャップがあって当然」だという事がハッキリわかってきたような気がしています。
ところで、今、ふと気が付いたんですが、
45歳の僕が「あの頃とは変わったね」と言われていないという事は、「あの頃と印象は特に変わっていない」という事がその裏にはあるんだろうと思うんです。
だけど、時間が経過して自分が変化すればするほど、昔の自分の印象はどんどん強まっていくわけです。「あの頃の自分はクソだったなあ」という昔の自分の“クソさ加減”が。
てことは、もしかして、
久々に会う人達も、同じように、「あの頃と変わらず・・・クソだね」って思っているという事なのでは?そんな事を考えてしまって、ついついお酒が進んでしまっています。
明日は早起きが必要なはずだけど、果たして起きれるのだろうかと少しだけ心配になってきました。おやすみなさい。
あかね
株式会社プロタゴワークス
#ビジネス #仕事 #群馬 #高崎 #対話 #組織開発 #人材開発 #外部メンター #哲学対話 #主役から主人公へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
