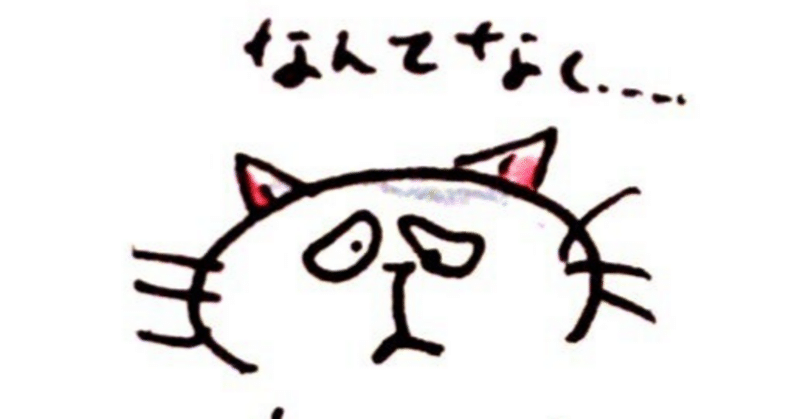
何となく伝わるような気がしないでもないかしら
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「〇〇とはどういうことですか?」
ウチは、外部の第三者として他社をサポートさせてもらっている仕事をしていますが、僕や仲間が目の前の相手に投げかける頻度の多い“問い”といえばこんな形です。
例えば、“採用”や“人材育成”や“制度・仕組みづくり”などのお手伝いをさせてもらうことが多いんですが、それらの取り組みの中で必ず出てくるのが「入ってきて欲しいのは、△△力のある人かなぁ」とか「◇◇力を高めたいんだよねぇ」なんていう言葉がとてもたくさん飛び交います。
そんな様々な「企業側が求めるもの」として象徴的なものと言えば、ここ何年間も「企業が新入社員に求める能力ランキング」というものでずっと1位になっている“コミュニケーション能力”です。
「コミュニケーション能力のある人を採用したいですか?」という質問をすれば、当然ながらどんな企業であっても「イエス」という回答になるんじゃないかと思うんです。「絶対にコミュニケーション能力がある人に来てもらっちゃあ困るんですよ」という回答をする企業もどこかにはあるのかもしれませんが、そういう企業は途轍もない少数でしょう。ほぼ全ての企業では「コミュニケーション能力がある人が欲しい」のは間違いありません。
ただ、これだけどの企業でも一致しているモノなはずの“コミュニケーション能力”ですが、とても興味深いことに“コミュニケーション能力の定義”について企業の経営者に一人ずつに聞いてみるとその定義は一人ずつ異なっていますし、同じ組織で働いている複数の人達に聞いてみてもこれまた一人ずつ定義が異なっているのを、これまで数えきれないくらい見聞きしてきました。
そうしてハッキリしてきたのは、「“コミュニケーション能力”の定義は、組織によっても全然違うし、同じ組織であっても人によって全然違うモノである」ということが明確になってきました。
もっと踏み込んで言えば、
「採用する側が“必要な能力である”と思っている“コミュニケーション能力というモノ”について明確に言語化して考えている人はほとんどおらず、みんなが“なんとなく”でしか捉えていない極めてボンヤリしたイメージでしかない」
ということなんじゃないでしょうか?
そして、これは「企業が新入社員に求める能力ランキング」というものでずっと1位になっている“コミュニケーション能力”というモノだけではなくて、それ以外にもランキングに入って来るような“意欲的”とか“素直”とか“真面目”とか“誠実”とか“明るい性格”とか“前向き”とか“行動力”とか“主体性”とか“忍耐力”とか言われるようなモノについても全く同じようなことが言えるはずです。
“コミュニケーション能力”でも“行動力”でも“主体性”でも、それらを定義しようとした時にスラスラと言語化できるくらい「普段からずっとこういうコトを考えているんだ」という人がいたとしたら、きっとこんな“〇〇力”という言葉を使うことはないだろうと思っています。恐らく、その人の中で定義づけられている言葉を普段から使っているはずです。
そうして、とてもボンヤリとしていて、でもイメージだけは何となく他者と共有できた感じがするような「みんながよく使っている言葉」を誰もが使って、あたかも「誰とでもイメージを共有できた感じがする」という幻想のようなモノを得続けてしまうのかもしれません。
でも、その「何となく共有できている感じがする」のは完全に幻想でしかありません。
そして、その幻想が「組織・チームを作って他者と協働して成果をあげる活動」をする際に、途轍もなく大きな壁となって邪魔をしてきます。
何しろ、「一人ひとりが思い浮かべている“〇〇力”の意味がそれぞれ異なっている」という現実がそこにあるのに、そのことに気が付いていて、それを統一しようとする動きがそこに無ければ、組織としてのパフォーマンスは上がらないからです。
例えば、傍から見て「あの二人は全然コミュニケーション取れてないから仕事の連携ができてないんだよなぁ」と思っていたとしても、当の本人達は各自が思う“コミュニケーション”のイメージで、「自分はコミュニケーションがとれている。だって、友達はたくさんいるし、家族や遊び仲間とはいつも和気あいあいとやれているんだから、自分と合わないアイツがコミュニケーションをとろうとしないのがいけないんだ」というようなことを思っている可能性があるわけです。だけど、「組織が求める円滑なコミュニケーションとはこういうモノだ」ということが示されていなければ、それを知る機会が無ければ、「各自それぞれが考えるコミュニケーションでいいですよ」というメッセージとして受け取られてしまうことになってしまって、みんなが協力して組織としてパフォーマンスを高めるということは途轍もなく難しいわけです。
だからこそ、冒頭のような“問い”を投げかける頻度が多いわけです。
「〇〇とはどういうことですか?」
自分がよく使う言葉は、自分にとってはその意味は極めて明確になっているのかもしれませんが、それはあくまでも「自分にとって」だけの話であって、“それ”と同じモノを他者とも共有できているのかどうかは他者と対話をすることでしか確認することができません。
そうやって対話をする中で、自分が語り、相手が聴いて、問いが生まれて、その問いによって考えが深まり、深まった考えをまた語り、聴いて、問い、考えていく中で極めて曖昧でボンヤリしていたイメージが段々と形になっていく。
そうして、時間と手間暇をかけてようやく形になったモノをもって、はじめて他者と一緒に「これだね」「これだよね」と共有することが可能になるんだと考えています。
だから漠然とした極めて曖昧なイメージでしかない「〇〇力」みたいなものについては、「〇〇力とはどういうことか?」という“問い”についてじっくり考えて、自分なりの、自分たちの組織としての“〇〇力”をハッキリと明確に言語化していくことで、“仕事”をするうえで誰もが「欲しい」とか「必要だ」と考えている「他社(他者)との差別化」というモノを獲得することに繋がるし、それこそが自分たちの“強み”になり得るんじゃないかなと思っています。
漠然とした極めて曖昧なイメージでしかないフンワリボンヤリした使い勝手のよい言葉を使っていると、誰にでも通じるような感じがして、誰とでも共有できたような気がしてしまうけれども実質的には「何も言っていない言葉」はなるべく使用を控えるようにして、それを使いたくなったら“問い”の力で打ち破る。そんな“問い力”が必要なんじゃないかなと思うんです。
ああ、つい、“〇〇力”を使ってしまいました。
本当に使い勝手の良い言葉なんだよな、この〇〇力って。“問い力”という単語だけで、ここに書いたようなことを一切説明しなかったとしたら、それが一体「何の力を表しているのか?」なんてことは誰にも全く通じないんだろうな、ということをこれだけの文字数を使って書いてみたからこそ身に染みて実感させられます。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
