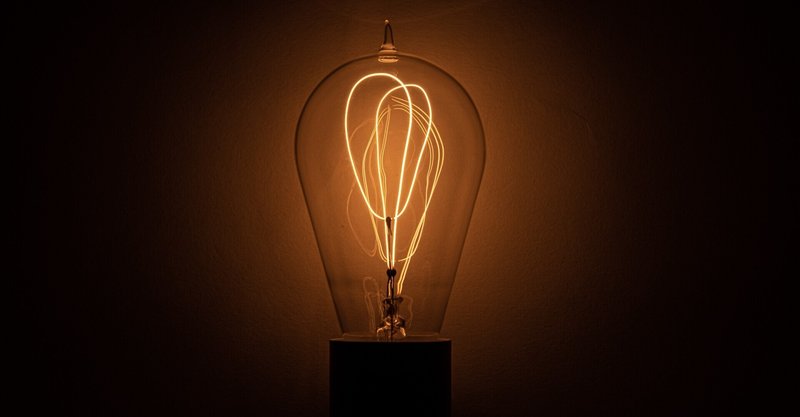
世紀の“再”発明
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「うわあ、自分は何にも考えてなかったなあ…」
本を読んでいると、そう思わされることがたくさんあります。
自分にとって、それなりに考えて、自分なりに“やり方”を確立して、大枠では他者に説明もしたり出来ていて、それなりに「まあまあ出来ている」と思えるような結果が出せるようになっている事柄が、複数あって、それらを、自分の中では“得意”とか“強み”として認定していたりするんです。
ところが、様々な本を読んでいると、そんな“それなりに出来てる感のあった事柄”について書かれているモノに遭遇する事が時々あって驚く事があるんですが、更に読み進めていくと更に驚くような事が起きるケースが多々あります。
そういう本には、大抵、その事柄について、僕自身では考えた事も無いくらいに見事に構造化がされていて、かなり細部まで明確に理論立てられている内容が書かれている事があるんです。
そういう時に冒頭のような事を思うんです。
ちょっと考えてみると、当たり前と言えば当たり前なんだとは思うんです。“そういうモノ”が考えられ、実践していて、書き表す事ができるから本を出版しているわけでしょうし、そこに行きつくまでには“その事柄”について、僕がこれまでに考えて取り組んできた以上の時間や情熱が注がれて、想像も出来ないくらいの精度で実践してきたという事なんだろうなあと、一読者としては思うんです。
そういう本に出会う直前までは、自分自身がしっかりやっていれば「まあまあ出来ている感」とそれなりの結果が得られているように感じていたからこそ、“それ”についてそれ以上深く考える事が無かったという事でもあるんでしょうが、様々な事柄でそんな気付きを得る機会があると、何とも言えない悲しい気分に陥る事もあったりします。冒頭の感想と共に、「自分なりには一生懸命やってきたのになあ」という気分です。
ただ、しばらく時間が経つと、その悲しい気分は払拭されていくのは毎度の事です。
そこからは、傍から見ても明らかにわかるくらいに、僕はその気付きをくれた本を書いている著者のファンになります。
これも毎度の事なので、仲間からは「またか」と思われている視線を感じますが、ファンになってしまったこの気持ちはもう止められません。
そうなると、その著者が過去に出した本を遡って買っていき、手に入ったところから順に読んで行くという行動が始まるのも毎度の事だったりしています。
こういう出来事を繰り返していると、かの有名な「車輪の再発明」という言葉を思い出さずにはいられませんし、その度に、「もっと早くこれを知っていたら」と思わずにはいられません。
“再発明”を行ってしまう理由には、「既存のものの存在を知らない」「既存のものがあることを知っていたはずなのに、つい思い出しそこなった」「既存のものを一応探したが、見つけそこなった」「既存のものの意味を誤解している」などがあるようで、これには自分も思い当たる節が十分にあるなあと感じています。
そんな“やっちまった感”と同時に、全く逆のベクトルの感想も持つことがあります。
それは、「この著者は構造化して説明してくれていて感服するけど、この著者以外がこの理論を書いているのは見た事は無いし聞いた事も無く、もしかしたらその界隈では有名な論なのかもしれないけど、自分達みたいな一般人が知る機会は少なくて広まっていない理論なんじゃないだろうか。だとしたら、それを自分達の経験をベースに発見して実践してる自分達って、これが仮に“車輪の再発明”だったとしても、控えめに言って、まあまあ凄いんじゃないのか?」という自画自賛の感想です。
そんな感想を抱いてしまう僕なので、その後に“ファン化”するのも当然と言えば当然です。何しろ、僕の観点からすると同じ類の理論を(全く比較にならないレベルだし、自分のは理論の態を成していないけれども)唱え著しているその著者に対して、一方的にシンパシーを感じてしまっているんですから。
それと、「その著者が明らかにしてくれた構造と理論を、とても有効に活用させてもらう事が出来るようになるから」というのも“ファン化”する大きな理由です。
自分達からすると、既に実用化していて、それなりに成果らしい成果も出ている経験と実践と“拙い理論”について、著名な方の英知の結晶とも言える“構造と精密な理論”の後押しが加わるようなイメージです。
こうなると、そこから先に手掛ける仕事の内容が、自分達でも明らかにわかるくらいに変わっていくのを実感できる事が多いので、こういう気付きがやってくるのを期待して本を読んでいるような節もあると言えばあるんです。
だけど、これにぶち当たると冒頭のように、それなりのダメージを受けるのも毎度の事なわけです。
自らダメージを受けに行く為の行為“読書”。
これまでの自分の弱さや至らなさが、本の内容に貫かれて“瀕死のダメージ”を正面から受ける。
運よくそこから“回復”する事が出来れば、“何か”を獲得して強さのレベルが上がる可能性がある。あくまでも可能性だ。
こうやって書いていると、これは『ドラゴンゴール』の話に似ているような気がしてきました。
「瀕死の状態から回復すると強くなるサイヤ人」の話です。
新たな段階の強さを得る為に、自ら防御力を極限まで下げて、クリリンに攻撃させて瀕死のダメージを受けたベジータみたいな感じかもしれません(とは言え、そもそもベジータのように強くも無ければ、仙豆も無いし、デンデも居ないような状態ではありますが)。
そんなギリギリを繰り返して何とか生き延びているような感覚の中、ここ最近も、素晴らしい本の内容に見事に打ちのめされ、ダメージに悶絶しながら、どうにかこうにかギリギリで生き延びたように感じています。今回もいつものように、まあまあ危なかったのは間違いありません。いつだって、敗色濃厚です。
それでも、これで獲得したモノを活かす事が出来れば、更に戦闘力が上がっているんじゃないかという期待はありますが、これを活かせるかどうかは、『ドラゴンボール』でいう所の“修行”が必要なのは分かり切っていますので、これはまた別のお話なのかもしれません(『ドラゴンボール』だと“修行”の場面はまあまあ安心して見ていられるのに、自分の場合だと、安心どころか不安しか無いのはなぜなんでしょうか)。
オ、オラァ、ワクワクすっぞ!(ガクガク)
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
