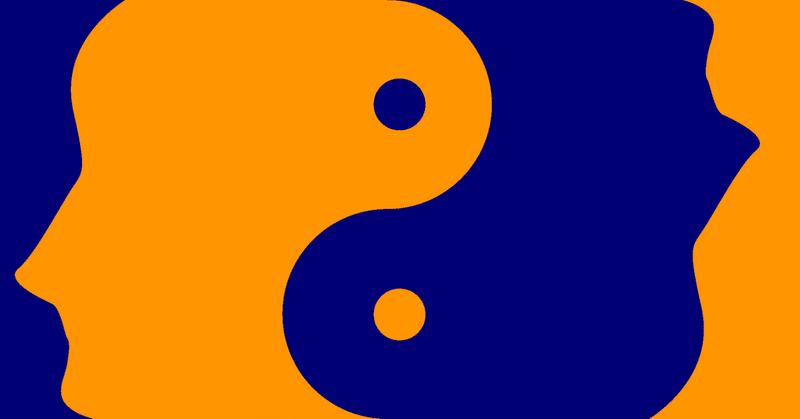
多様で具体な同質の抽象
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「もしかしたら“多様性が内面化されているかどうか?”が違いとして表れているのではないだろうか?」
そんな問いが浮かんできた瞬間がありました。
先日、ある経営者の方Aさんと話しをしている時に、とある資料を見せてくれたんです。
その資料は、その経営者の方が参加している勉強会で配布された資料とのことでした。
内容を見ると、とある企業で社内制度の運用で実際に使っているシートだったんですが、それはどうやらその勉強会に参加していた別の企業の経営者Bさんが「いいものができたので、みんなの参考になれば」と配布してくれたものとのことでした。
そしてどうやらその制度構築には外部のコンサルがばっちりかかわって作ってくれたんだと、件の経営者Bさんは言っていたそうです。
その資料を見せてもらった僕の率直な感想としては、「これを外部のコンサルがお金をもらって作ったなんて俄かには信じがたいぞ…」というモノでした。
そしてどうやら、その経営者Aさんも同じように感じていたという話をそのあとに聞かせてもらいました。
その資料を見る限りでは、社内制度について様々な項目が設定されていたんですが、その項目のどれもがかなり高めの抽象度で記載がされていて、「ここに書いてある項目を基準として社員が行動をとるとすると、かなりの推察力と行動力が必要になるだろう」というのが明確になるくらいのモノでした。例えて言うなら、「なるはやでいい感じに頑張ってね」的な捕えようのない感じの記載の仕方というくらいの抽象度でしょうか。もちろん、正確にそう書いてあるわけではありませんが、抽象度のレベルで言うとそのくらいのレベル感というわけです。それを、もう少しお堅い言葉で表現してあったり、もう少し難しい言い回しで表現してあるような社内制度の運用シートでした。
この例えのように「なるはやでいい感じに頑張って」で、社員が望む通りの行動をとって、なおかつ、求める成果を出してくれるんだとしたら、逆に言えばその会社にはどんな制度もいらないんじゃないかなと思うんです。
何しろ、経営者が「なるはやでいい感じに頑張って」と声かけをするだけで、思うような経営ができるのであればそれは実際には何も指示なんて必要ないのと同じような感じです。
ウチも組織開発の一環として、“他社の社内制度構築のサポート”をやっているわけですが、自分たちが作っているモノとあまりにも異なりすぎていて軽く戦慄を覚えるくらい驚きました。
そして、勉強会でこれを目にしたAさんも僕たちと同じような衝撃を受けたと話してくれました。
そんな話をしながら、これだけ抽象度の高い社内制度を構築した経営者Bさんの「目的とは一体何だったのか?」ということを考えてみました。
すると、この抽象度の高い制度からは“あるメッセージ”が浮かんできたのを感じました。
というのも、これだけの抽象度の高さなのであれば、本来はこの制度にある文言を見た社員の方々は各々が独自の考え方をするはずです。何しろ、いかようにでも解釈が可能な言葉が書かれているわけです。そうであれば、「各々の判断に任せる」という意味になってしまうはずです。でも、これは“新しい社内制度”としてわざわざ外部のコンサルに依頼した代物というわけです。
ということは、「各々の判断に任せる」なんて意味が込められているはずがありません。もしそうだとしたら、外部のコンサルにわざわざ頼むはずがありません(だって、任せるんだとしたらそう言えばいいだけですから制度構築は必要ないはずです)。
だとすれば、この制度構築の大前提になっているのは「この表現であれば、“誰でも”こう考えるはずだ」という“同質性”が根底にあるんじゃないだろうか?
そんなことが見えてきたんです。
そう解釈してみると、ついさっきまではの僕たちの目には「とてつもなく抽象度の高い表現だらけでこれを受け取る側としては“迷い”しか生じないんじゃないか?」と見えていたんですが、「もしかしたら、この表現によって“社員のみんなが同じように動いてくれるだろう”という期待が込められているんじゃないだろうか?」と推測が働き始めました。
“同質性”が根底にあるのならば、確かにこれらの表現で「みんなが同じように動いてくれる」という期待が込められるのもわからないではありません。
なぜ、僕たちがそう思うのかと言えば、“過去の自分たち”がそういう“同質性”を持ったままマネジメントに携わってしまっていた忌まわしき過去を持っているからです(もちろん、今思い出しても当時の自分たちの部下だった人たちには、心から申し訳なかったと感じていますし、マネジメントをしていた当時はその人たちへの謝罪の気持ちを忘れたことはありませんでした。その時の自分たちを反面教師にしてそれ以降のマネジメントをしていたことでせめてもの罪滅ぼしを多少でもしたいと思っていました)。
そんな自分たちの体験を思い返すと、“当時の自分たち”と同じような文言を使って、同じような価値観を持って作られているこの社内制度は、恐らく経営者の方の“同質性”がベースになって作られているだろうことが推測されてくるわけです。
逆に言えば、この資料に目を通したときに、「あれ?なんかこれだとちょっと違和感が…」と感じた経営者Aさんの中には、“同質性”ではなく、“多様性”が内面化されているんじゃないかということが見えてきました。
会社という組織で“多様性”を大事にするということは、すなわち、「弱みも強みもお互いに把握して、弱い部分はカバーしあって強みを発揮しあって、組織として成果を出す」ということに尽力することになるわけです。
そうなった場合の“社内制度構築”は、「できるだけ抽象度を下げて具体的に記述する」ということが必要になってきます。何しろ、“社内制度”というものは、いわゆる“基準”としての機能が必要になるわけですから。
もちろん、「抽象度の高い基準」というモノが存在しないわけではありませんが、どちらかといえば“その役割”は、いわゆる「経営理念」という部分が担うモノであるはずです。
いわゆる「経営理念」というモノは、それを作った人の中にある“想い”が具現化したモノであるわけです。ただ、その“想い”は本来であれば“それを作った人”の中にしか存在していないモノなわけです。その“唯一無二な想い”を、「どうやって他者に伝えるのか?」を試行錯誤して形にしたものが「経営理念」になるわけです。
だけど「経営理念」のままだと“組織の基準”として活用するにはまだまだ抽象度が高いことがよくあるわけです。何しろ、組織自体は“理念を手渡された人たち”がメインで構成するわけですから、そこに書いてあることがどんな想いから生み出されたのかについての“手ざわり”を持っているわけではありません。
なので、傍から見るとまだまだ抽象度の高い「経営理念」を、「行動や判断をする際の“基準”」とするための様々な制度や仕組みを構築していく必要が出てくるわけです。
そして、だからこそ“制度や仕組み”は、「多様な人材たちが活用しようとした時に、誰にとっても“具体的な基準”として機能することが必要不可欠」になってくるわけです。
そんなことを考えた時に、冒頭の問いが浮かんできたんです。
「もしかしたら“多様性が内面化されているかどうか?”が違いとして表れているのではないだろうか?」
“多様性”が内面化されていると「自分の考えている言葉や表現で通じるんだろうか?」と遥か向こうの方までも考えることになるから“どこまでいっても不安に駆られる状態”に陥るのかもしれません。
それとは逆に、“同質性”が内面化されていると「自分の考えている言葉や表現で通じないかもしれない」と想定する範囲がとっても限定されていて、「なるはやでいい感じに」なんて“自分にしかわからないモノ”が伝わるかどうかに疑問を持たないのかもしれません。
経営者Bさんが本当のところ何を考えてこの資料を作ったのかは僕にはわかりませんし知る機会もありません。ただ、「参考のために」と言って配布してくれたその気持ちをしっかり受け取らせていただこうと思っています。
これを参考にして、今後ウチが手掛けることになるどんな会社のどんな制度や仕組みであっても、「そもそもこれは何のために作るのか?」という目的から外れることなく、それを使うことによって「その会社で働く全ての人や、関わる人たちみんなが、“三方よし”になる状態を叶えることができる」そんな状態を実現するために、一切の忖度もすることなく、誰におもねることもなく、ただただ“目的”を叶えるために「役に立つこと」だけを考えて取り組んでいこうと、あらためて固く決意しました。
それが、プロタゴニストとしての矜持を貫くことなんじゃないかと思っています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
