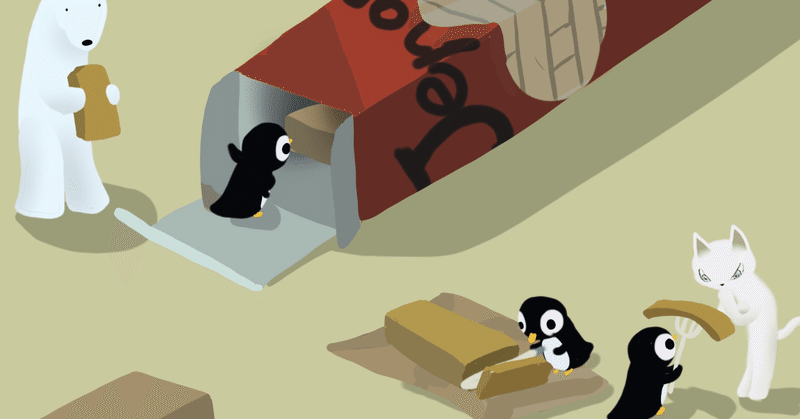
とにかくまずは切り分けて
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「役に立つことをしましょう」
他社の組織開発にかかわらせてもらう中で、僕たちが常に口にしている言葉です。
この「役に立つことをする」という考え方が、僕たちが組織開発をするうえで「実現したい」と考えている“一人ひとりの働きやすさ&業績向上”にとって、とてもしっくりきています。
そんな「役に立つことをする」という考え方ですが、組織で仕事をするうえで「何をするべきか?」を判断する際に“明確な基準”として機能するところが、「とても便利だな」と考えています。
ただ、この「役に立つことをする」という考え方を判断の“基準”として活用する際には、一つだけどうしても越えていかなければならないモノが出てきます。
それは、“自分の感情”です。
例えば、組織内のAさんと自分の関係性が、お互いの視点から見ても、周囲の他者から見ても“対立的”な状態だったとします。
この状態の時には、「Aさんに対する“自分の感情”」は “良い感情”を抱くことは難しくなってしまっているはずです。
そうなると、例えば会議をしていても“Aさんの意見や発案”に対して「“自分の感情”を一切無関係な状態にしてフラットな状態で検討する」というのはどうしてもバイアスがかかってしまうのでかなり難しい状態になってしまっていることが考えられます。
何しろ、「お互いの視点から見ても、周囲の他者から見ても“対立的”な状態」にあるわけですから、この状態で「いや、自分は対立していても意見はフラットに扱えるよ」と自分について考えているとしたら、その状態がもう既に“なんらかのバイアス”によるものであるわけです。
もしも本当に「フラットな状態で相手の意見を検討できる」んだとしたら、少なくとも周囲の人から見た時に“対立的”な状態であるはずは無いでしょうし、Aさんからの視点としても“対立的”な状態では無いのは間違いありません。
なので、客観的に見て“対立的”な状態にあるのにもかかわらず、「自分は相手の意見をフラットに見れる」という自負がある場合には、「対立している相手の意見ですらフラットに検討できる人として見られたい」という“自分の感情”がそこに影響していて、なんなら“周りからそうみられたい”という部分が最優先されてしまっている状態でもあるので、「役に立つこと」を考えるというのは実際にはかなり難しい状態になってしまっているわけです。
組織開発でかかわらせてもらっていると、こんな例のようなことが様々なパターンで起きているところによく遭遇するんです。
そして、当然ながら、そこには当事者たちの“自分の感情”が最優先されてしまっていて、その当事者たちにとっても、組織にとっても、「役に立つこと」がなされないまま仕事が行われていて、“その人自身の働きやすさ”も実現していないし、“組織の業績向上”も実現していない状態になってしまっています。
その状態は、“組織としての目的”が掲げられていたとしても、その“目的”に向かうことよりも当事者たちが“自分の感情”を最優先にしてしまっていて、“目的”から外れた行動をとってしまっていても、そのことに当事者が気付いて修正することがとっても難しくなってしまっているのは言うまでもありません。
でも、僕のように組織の外部から冷静に眺めてみると、そもそもの“対立的”な関係性の原因や、当事者たちが“自分の感情”を優先させてしまっていることの原因や、各自の“働きやすさ”が実現しない原因や、組織の業績向上ができていない原因が、どこにあるのかはある程度ハッキリ見えてくるんです。
そもそも、「“役に立つこと”を基準にした判断がなされておらず、“自分の感情”を最優先にした判断が行われている」のが原因なわけです。
そして、“そんなこと”が起きているのは、“自分の感情”と“事実”を切り分けて考えるということがなされていないから起きてしまっているのは間違いありません。
「あいつはムカつく。だから、あいつの言っていることには耳を貸さない」
そんな“自分の感情”に、もしも気が付くことができたとしたら。
そして、そんな“自分の感情”に気付いたうえで、“仕事の目的”にも気が付くことができていたなら、こんなことを考えることができるんじゃないかと思うんです。
「あいつはムカつく。だけど、あいつの意見は“目的”から考えてみると、確かにこれまでのアイデアの中で一番理に叶っているよな。であれば、この仕事を進める際には“この意見”で進めるのが最もうまくいく可能性が高いから、俺はこの意見に賛同する。あいつはムカつくけど」なんて具合に。
“感情”のコントロールは“悟り”を開いたくらいの人じゃなければ恐らくできないんじゃないかと思うんです。というか、“悟り”なんてほど遠いので、感情のコントロールができる人がいるのかどうか実際には凡人である僕には全くわかりません。
だけど、そんな凡人の僕であっても“感情”と“事実”を切り分けて考えるということは出来る場合がたくさんあります。
まだまだ「どんな状況であっても切り分けることができますよ」と言えるようなレベルではありませんが、“昔の自分”と比べてみれば、仕事の場面であればそれなりに切り分けることができるようになってきた自覚はあります。これは訓練を積めば、以前の自分よりも成長するのは間違いないと実体験から断言できます。
そして、この訓練をしていくと「あ、今ちょっと感情に引っ張られて“役に立つこと”から思考がそれちゃった。修正しないと」なんて具合に、自分で自分の状態に気付くことができるように段々となってきています。
当然ながら、“それ”に気付くことができるようになってくると、「自分は、まだまだ“役に立つこと”だけを考えられるわけではない」という“己の未熟さ”にも気付くことができるようになってきます。
これは、言い換えれば、「自分自身にバイアスがかかっているんだ」という自覚を持っていれば、(即座にではないけれど)自分のバイアスに自分で気付くことができる場合が増える」ということでもあるんじゃないかと思っています。
そうやって、「感情と事実の切り分け」や「役にたつことを基準に判断する」や「自分のバイアスの存在」や「感情やバイアスに飲み込まれたことに気付く経験」なんかを、何度も何度も積み重ねて、それを振り返って事後的に気付いたり、なんてことをしていくと、「目の前の他者が今どの段階でどんなことに直面しているのか」ということが、何となく見えてくるような感じがして、それを仮説として持った状態で対話的に関わらせてもらうことで、“今の自分自身の状態”に気付いてもらって“役に立つこと”に向かってもらうような関わりができる場合が段々と増えてきているように感じます。
もちろん、ここに書いたようなことは僕の中の“主観の話”なので、実際にそうなのかどうかは“バイアス”がかかってもいるでしょうからわからない部分も多いですが、客観的な事実として「こういうようなことが起きた」というのを確認していくことで、この話が本当かどうかが明らかになってくるのかもしれません。
まあでも、今のところはウチの掲げる“目的”から考えてみると、そこに向かっていくために“役に立つこと”を判断できている場合も多いんじゃないかと思える状態になってきているので、ひとまずは「役に立つことをしよう」という考え方で間違ってはいないんでしょうし、それこそがまさに「役に立つこと」なんでしょう。
そう思うと、色んな感情がワーッと湧き上がってくるのを感じますし、日々の中で何度も何度も一喜一憂している毎日ですが、感情と事実を切り分けながら、明日からもまた役に立つことを基準に色々考えていこうと思います。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
