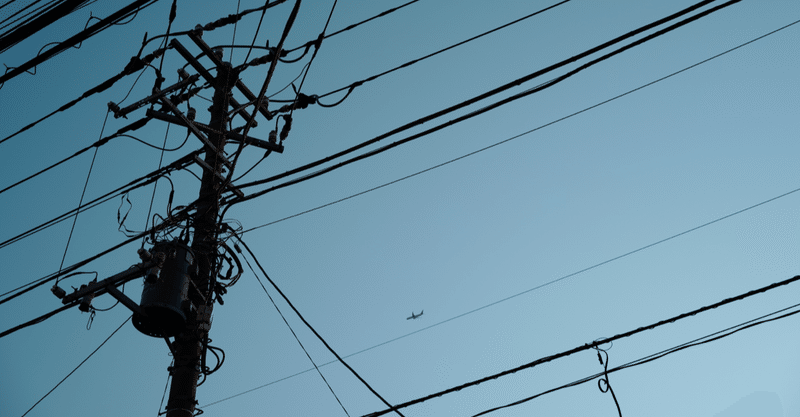
明日のデザインをトゥギャザーしようぜ
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
ウチは、中小企業向けに組織開発を行っている会社です。
色んな中小企業さんに組織開発で関わらせてもらっていると、「組織の中のどのポジションにいるのか」によって、その組織とその組織の事業と自分が担っている仕事について、見えるモノや受け取り方が違ってくるという事がたくさん起きているの見聞きします。
一つの“事象”について、経営者からは○に見えて、管理職からは◇に見えて、現場の社員からは△に見えていて、しかも、どの人もそれぞれ「自分の考えが正しく、他の人がどうしてあんな事を言ったりやったりしているのかわからない」と考えている。
こうやって文字にしてみると、俄かには信じられないような奇妙な出来事が、そこかしこの組織の中で実際に起きているのを見聞きします。
僕も、自分が組織の一員として一般社員や管理職の一員として働いていた時がありますが、自分自身もこれと同じ事を思っていたので、実体験としてもよく知っています。
何でこういう奇妙な出来事が様々な組織の中で起きるのか。
本来は、同じ目的に向かって、円滑なコミュニケーションを行いながらお互いに協力して達成を目指しているはずなのに。
一番大きな要因は“情報格差”なんじゃないかと思っています。
同じ組織内にもかかわらず、それぞれのポジションや、それぞれの担当業務によって持っている“情報”が全然違う。
それによって、“一つの事象”自体を認識したとしても、その事象の周辺にある情報ー例えば“経緯”ーを知らない人と知っている人との間には、同じ“事象”についての見え方や解釈は確実に変わってくるわけです。
そんな、情報格差が色んなところで様々に起きているの現状があるんですが、「自分達の組織の中で情報格差が起きている」ということに気が付くというのは、実はとても難しい事なんじゃないかなと思うんです。
もし、情報格差に気が付いていたら、その格差を埋める情報を取得するための動きをすればいいわけです。そして、その動きをしたとしても埋まらない格差があるんだとすれば、組織のどこかの時点で何らかの情報統制がなされているんでしょうし、情報取得の制限がかかっていると考えるのが自然です。
だとすれば、それをしている要因は色々あるんだとは思いますが、「組織一丸となって仕事をして業績を上げていきたい」という事を考えるのは無理筋です。
特に、多くの中小企業でよく掲げられる「理念の浸透」や「組織一丸となって」という事を実現するためには、“社内の情報格差”は、自分達で掲げたその言葉を阻害してしまう最大の原因の一つです。
なので、組織の中で少しでも情報統制や情報取得の制限をかけてしまえば、各部署の情報だけでなく動きや管理などの様々な部分を細部までキッチリ管理し統制する組織運営方法じゃないと、機能させるのは難しいんじゃないかなと考えています。
だから、「情報統制や情報取得の制限は明確な意図を持ってそれを行わない」というのが、社内の情報格差を無くして、組織が一丸となり理念が浸透して、業務が円滑になり、社内の人間関係が整って、利益率向上のために重要な事柄になってきます。
その取り組みをしたうえで、「それでも情報格差によって、“事象の見え方の違い”が起きていないか?」を注視して、情報格差が起きないために、常に様々な部門の人達との情報共有や情報交換ができる環境を整えておくことが重要です。
例え、“情報の透明性”に気を付けて、誰でも情報にアクセスできるようにしていても、積極的に情報取得が“できる人”と“できない人”が出てきてしまうというのもよくある話です。
そこで、積極的に情報取得ができない人に目を向けずに放置してしまうと、ここまで頑張って来てもまたもやそこで“事象の見え方の違い”が起き、業務の円滑さや感情の縺れからくる人間関係のゴタゴタが発生してしまうことがあるわけです。
せっかくの取り組みが無駄にならないようにするために、“事象の見え方の違い”を起こしてしまう情報格差が生まれないようにするために、僕たちは企業の中での対話を推奨しています。
対話の文化が醸成できている組織の中では、情報格差は減っていきます。
もちろん、情報の共有だけでなく、お互いの“強み弱み”も共有できますし、お互いの“キャラクター”や“価値観”についても共有できますし、それぞれの考えからそれぞれが“学びあう”なんて事も起きますし、当然ながら、“理念”について確かめ合う事も、一丸となって同じ目的に向かおうとする事も可能になります。
だけど、“同質化”や“均質化”をするわけではありません。
あくまでも、お互いの“違い”を認め合ったうえで、同じ目的に向かって協働出来る素地が整ったりするんです。
情報格差も“事象の見え方の違い”も、対話によって解消できる可能性は高いと僕たちは考えています。
これは、僕個人の単なる思い込みではなくて、実際にこれまで自分達が取り組んできた様々な人達や様々な場での“対話的な取り組み”の中で起きている事を基にしている事なので、現場での効果はかなり高いと自負もしています。
とは言え、対話は万能ではありません。
「それだけやっときゃどうにかなる」なんていう魔法のようなモノでもありません。
あくまでも、「その対話に参加する全ての方の協力によって成り立つモノ」であると僕たちは考えていますし、現に、参加者が協力的でない対話の場は「対話で得られるだろうと目されていたはずの効果が得られない」という事が往々にして起こります(これは、僕の個人的な基準で判定しているわけではなく、参加した人たちの感想から得られているある意味信ぴょう性の高い客観的な事実です)。
という事は、「主体的で対話的」であるという在り方が重要であり、その在り方を「日常的にずっと行うのは難しいかもしれないけど、せめて、その対話の場でだけでも実行する」ことで、その場にいる人達にとっての「深い学び」に繋がるし、「この対話というモノは意外と役に立つかもしれない」と体感できる可能性がありますし、現に“対話的な関わり”を他者に対して実行してみて役に立ったという人の話もたくさん聞いています。
それはすなわち、“組織の三要件”である「目的の共有・円滑なコミュニケーション・協力」が実現されていくためにも、とても有用で便利な、“役に立つ”コミュニケーション方法であるという事が、様々な組織の中で体感されているという事でもあるわけです。
いつものように、また長々と色々書きましたが、言いたかったのは、
「組織の中の上手くいかない感じには、対話が結構効きますよ」
というとても単純な話でした。
「組織に効く対話」の効果を体感している「働く人たち」が、徐々に世の中に増えてきているのは間違いありませんし、それが「自分自身にも効く」のを体感して、希望に変わり始めている人達も少しずつ増えてきています。
そして、この事実は、僕たちプロタゴワークスにとっても、大きな大きな希望の光です。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
