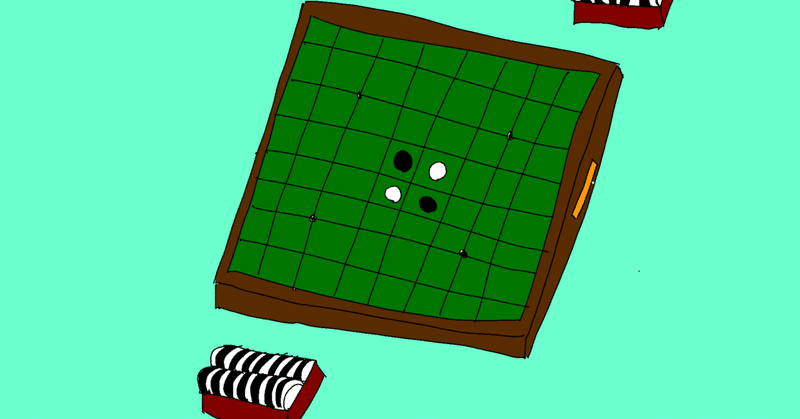
難しいけどだからこそ
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
ウチの仕事柄、他社に関わらせてもらっている中で僕たち外部の第三者から見ると「それって同じモノゴトですよね」としか思えなくても、当事者Aと当事者Bからすると「いや、全く別のモノゴトだ。アイツが間違っている」と言い合っているような状況によく遭遇します(今は便宜上、当事者をAとBに限定して書いていますが実際の現場ではこの当事者の数はもっとたくさんの場合がほとんどです)。
こんな状況になってしまっている原因はその現場やそこに関わる人達によって千差万別多種多様ではありますし、実際に誰もがそう思っているわけですが、でも、その真因は全てのケースで共通しているだろうと考えています。
その真因は、“「自分が正しくて相手は間違っている」という前提が各自の中に存在していること”です。
こんな話は、あと2か月くらいで2024年を迎えようとしている現代で今さら書くようなことではないだろうと思うくらい遥か昔からずっと言われ続けていることですが、それでもやっぱり今もこれからもずっとこの話は巷でされ続けていくんだろうなと思っています。それこそ、「挨拶って大事だからちゃんとしようね」という話と同じくらいに誰もが一度どころか何度も何度も他者から聞かされているようなモノなんじゃないかと思っています。
これまで様々な人から数多の相談を受けてきた身としては、いわゆる“人間関係の問題”というモノのほぼ全てが“これ”に端を発して起きているのは「まず間違いの無い事だ」と言い切れます。
逆に言えば、“人間関係の問題”が生じた瞬間とか生じそうになった瞬間に“これ”に自ら思い至ることができたとしたら、これから起きるかもしれないモノを起きなくさせることが可能なはずです。
もしくは、“もう既に生じた問題”に直面していたとしても、自ら省みることでその問題を解消することに繋げられるかもしれません。
そもそも、“人間関係の問題”というのは文字通り“人間関係”と言っているので“誰か一人”だけの問題であるはずはありません。“誰か”と“誰か”の二名以上の人間がそこに存在して“関係”しているから“人間関係”というわけで、そこに“問題”が発生しているんですから、何をどうしたって「その当事者として存在している人達の関係によって生じている問題である」としか考えることができません。
それを前提にすれば、「自分が正しくて相手が間違っている」という捉え方がどれだけ“おかしなこと”なのかは、問題の当事者以外の人達である第三者から見るとあっさりハッキリと見えてきます。
そもそも、ほとんどのモノゴトは「多面的である」のが大前提だろうと思うんです。
例えば、今僕がこうやってノート型PCのキーボードを打って文字を入力していますが、今この瞬間に見ているのはPCのモニターです。そこに文字が記入されていくのを目で追いながらキーボードを打っているわけですが、この瞬間の僕にはノート型PCのモニターの裏側にあたるカバー部分(というんでしょうか?PCメーカーのロゴが入っている側です)を見ることはできません。
でも、もしも僕の座っている場所の正面に誰かが座っていて、向こう側から見た時には僕のPCのキーボード側は見えずに、カバー部分しか見えないはずです。
物凄く当たり前の話なので「で、それが何か?」と思われるのかもしれませんが、あらゆるモノゴトはそんな感じで「多面的である」ということが言いたかったんです。
これがもしも、“仕事”をしている場面で、僕の向かいに同僚の誰かが座っていて、こんなことを言ったとしたらどうなるんでしょうか?
僕「ねえ、ここにあるロゴってなんか変じゃない?」
相手「(??なんだ急に)変てどういうこと?」
僕「いや、このロゴなんだけどさ」
相手「(ああ、PCのロゴのことかな)いや別に変じゃないでしょ?普通じゃない?」
僕「は?これが普通?これが普通に見えるんだったらお前ヤベーんじゃねーの!?」
相手「いや、そのロゴのどこが変なんだよ?変なのはお前の頭じゃねーのか!?」
この展開はちょっと大げさに書きすぎたのであまり現実味は無いかもしれませんが、様々な組織で起きている“人間関係の問題”ではこれを少し時間軸を長くしてやり取りの回数を増やした感じの展開がそこかしこで実際に起きているのを頻繁に見聞きします。
例えば、上の例ではPCで作業をしている“僕”が自分のPCモニターに映っている「何らかのロゴを見て気になったから」目の前にいる人に唐突に“自分の中の違和感”について話をしはじめました。
それを受けて親切な“相手”は、自分の目に映る“僕”が使っているノート型PCのカバー部分にあるメーカーのロゴについての感想を伝えました。若干の戸惑いとともに。
それに対して、“僕”は“自分の中の価値観”で相手に自分の思ったことを伝えます。「今の状況を客観的に見る」とか俯瞰したり客観的な観察をすることも一切しないで、全て自分自身の主観的視点での一方的な価値基準での話をそのまま。
そうして、何の問題も存在していなかったはずのところに、こんなに短いやり取りの中で短時間でとても効率的に“人間関係の問題”を発生させることに成功するわけです。
この例では“相手”の方は完全に被害者です。「どっちが善いか悪いか」の話をするのであれば、この短い例の中では明らかに“僕”が悪いのは火を見るよりも明らかです。完全に一方的な言いがかりですから。
でも、“人間関係の問題”として捉えるのであれば、もしも「ロゴについて話を振られたけど、そもそも何のロゴのことについて話をされているのかがわからない」という時点で、「何のロゴについて話をしているのか?」という質問をすることができていたら話の展開は変わった可能性はとても高いんじゃないかと思います。もちろん、もっと“そもそも”から考えるのであれば「“僕”が“相手”の意見を求める際の質問の仕方が悪い」というのは間違いありません。
とは言え、「どっちが善いか悪いか」を決めるということをしたところでもう既に起きてしまっている“人間関係の問題”は解消することはありませんし、「あなたは善い、あなたは悪い」ということがあればそれは必ず遺恨を残します。
それよりも、「その問題は、自分にも反省するべき点があった」と当事者である人が“自分自身”について省みることができて、実際にその後からの行動に反省が活かされていれば、その問題の解消にはどんどん近づいていくはずですし、同じような問題が起きることは無くなるはずです。
そんな捉え方や考え方ができると“人間関係の問題”を抱えることはグッと減っていくでしょうし、もう既に起きてしまっている“人間関係の問題”も解消に近づいていくことに繋がります。
でも、「自分が正しくて相手が間違っている」とか「そもそもから考えれば、相手が悪いんだから」とか「相手が非を認めないのであれば絶対に許さない」なんて感じになってしまっていたとすると、恐らくその“人間関係の問題”はその先ずっと解消されることも無く永遠に「自分自身を取り巻く“問題”としてそこに在り続けて、自分と相手が存在する限りその“問題”も存在し続ける」ということになってしまいます。
そうなれば、その“問題”を自分の中から無くすためには、その“人間関係”を解消するしかなくなるので、「自分(もしくは相手)が“その場”を去る」とか「その“関係”が存在しなくなる場に移動する」ということしか選択肢が無くなります。
「誰が善いのか悪いのか」とか「誰に責任があるのか」というような捉え方ではなく、“勝ち負け”とか“誰を責めるのか”というところから見方を変えて、「自分を含めた“人間関係の問題”は自分自身もその問題の中に入っているんだ」という見方をすることで、自分自身の価値観や考え方や在り方や言動を見つめなおすことに繋がるので、それができたらその“問題”を本当の意味で解消することに繋がるはずです。
そんなことを考えていると「他責になるな」というような言葉の本来の意味としては、「実際に“他者に責任がある”という状況であったとしても、その他者にだけ責任の所在を求めてしまうと自分自身が省みて後々の成長に繋げることのできる要素を見落としてしまうことになるから勿体ないよ」というような意味が含まれているのかもしれないなぁ、なんて思えてきました。
そうして、こんなことをここまで書いてきたのは、「それら全てが“自分自身のためになる”から、自分が生きやすくなるんだ」ということが言いたかったんだなというのが見えてきて、あらためて自分自身で納得することができました。
どんなモノゴトであっても自分を含めた関係性の中で“人間関係の問題”が起きたり起きそうになったのであれば、必ず自分自身にも反省すべき点が存在しているんだから、「自分は正しくて相手が間違っている」という考え方からは離れた方が“役に立つこと”に繋がるんだということを忘れずになるべく早いタイミングでそう考えられるように、これからもずっとトレーニングを積んでいくことを続けないといけないんだなぁ。なにしろ、自分も誰でも「モノゴトの表と裏を同時に見ることはできないんだから」。ああ大変だ。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
