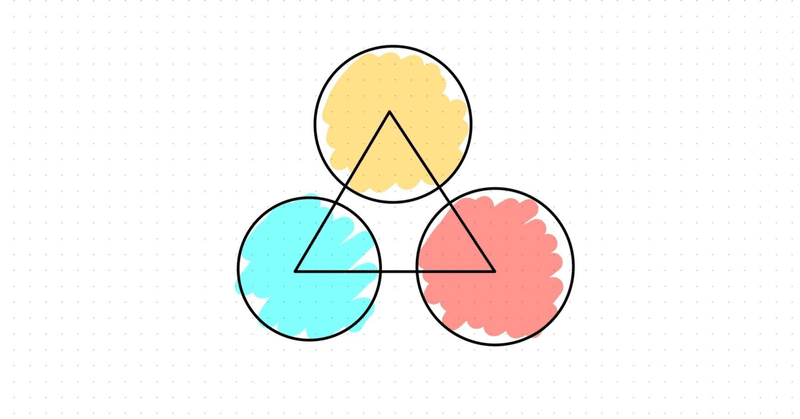
よく見てよく考えて欲張って
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
実際にその人がとった行動、実際に目の前で起きているコト、それをありまのままに見て正しく受け止める。
他社の組織開発に関わらせてもらっている中で、それがとっても大事だと思っていますし、できるだけ多く伝えていくことにしています。
こうやって文字にしてみると「特に、いまさら強調するまでもなく至って当たり前のことだなぁ」と思うんですが、これが「案外となかなか難しい」というのを、“外側”から関わらせてもらっていると常々感じます。
よくあるのが、“その人がとった行動”については特に何の反応も示さないけれども、“その人が話した内容”を「途轍もない重大事項や大問題について言及された」というように反応してしまうとか、他にも、“実際に目の前で起きているコト”については特に何の反応も示さないのに、まだ起きてもいない“今後起きる可能性が低そうなコト”を想像して、その“想像したこと”に対応しなくちゃとアタフタしたり、なんてことが様々な組織でよく起きています。
そんな状況を見ると、「まずは、目の前の“事実”に向きあって、それの対応を正しく行いましょう」ということを伝えます。
以前に、こんな例がありました。
とある企業で、「上司Aさんが、部下Bさんを物凄い剣幕で怒鳴りつけている様子を目撃した」という話を経営者がしてくれました。場所はどうやら休憩室の隅っこの方で、その二人が向かい合って何やら話をしている様子だったのが、突然、上司Aさんが今まで聞いた事もないような剣幕の怒号を発し、部屋中に響き渡ったということでした。
あまりの事態に、慌てて経営者の方が止めに入ったら、その上司Aさんは怒りを露わにしたままどこかにフイといなくなってしまったので、怒鳴られていた部下Bさんに「何があったのか?」を聞いてみたようでした。
それは、こんな話だったようでした。
部下Bさん曰く、「業務を進めるうえで必須のチェック用書類を記入していたら、“そんなのやらなくていいよ”と言われたので、本当にやらなくていいのかについて、先日、(経営者に)確認しに来たんだ。だから、“その書類はちゃんと書かなくちゃだめだ”って部下Bに伝えたんだ。そのチェック大事だから。で、その件について上司Aは怒っていて、“俺はその書類記入をやらなくていい”なんて言ってない。早く終わらせて早めに帰るように”って言っただけだ。何で言ってもいないことを言われたってことにして社長に報告してるんだ!」というような内容だったようでした。
この話の前提としては、部下Bさんは、他の社員さんと比べると仕事の手が遅く、仕事でミスもよく起こす方のようで、上司Aさんや他の社員さんたちも日頃からそれについてストレスを抱えていたようでした。
こんな状況の中で、経営者の方は「上司Aが言ってもいないことを、部下
Bが“こう言われた”なんていうもんだからあんなことになっちゃって。あれじゃあ、上司Aもストレス溜めちゃうと思うんだよね。普段はあんなに温厚なのに、あんなに怒鳴っていて。あんな姿初めて見た」とか「どうやったら部下Bがもっと仕事が速くできるようになったり、ミスが減ったりするんだろう」という悩みを口にしていました。
なので、冒頭の話をしてみました。この件になぞらえながら。
この件の中で重要なポイントは幾つかあると思うんですが、“組織”のパフォーマンスを高めていくためには、そもそも、“上司”というモノの役割を確認する必要があります。
上司とは、“部下の成長を促し見守りサポートをして、自分以外の他者に動いてもらって(率いている)チームとして成果を挙げること”が重要な役割の一つだと考えています。そして、これは経営者の方も同様の意見でした。
であれば、まずは、「自分の伝えたことが、部下には全く別の意味として受け取られていた」ということが分かった時点で取るべき行動は、「怒りを露わにして怒鳴りつける」であっては、“組織”として、“上司”として、とってはいけない行動である。それを上司Aさんにフィードバックする必要があるはずです。
何しろ、何をどう考えても、
「上司として、必要な指示を正しく部下に受け取ってもらえるように伝えることが出来なければ、チームとして成果を挙げることは絶対に不可能である」ということはハッキリしています。
逆に考えてみれば、「上司が何も言わなくても、部下が“上司の考え”を推測したうえで先回りして全てやってくれて、チームとして挙げたい成果が出来上がって来るのであれば、そんな上司は存在する必要は無い」のは言うまでもありません。
だけど、この件について、経営者の方が悩んでいたのはそこではありませんでした。
「上司Aが言ってもいないことを、部下Bが“こう言われた”なんていうもんだからあんなことになっちゃって。あれじゃあ、上司Aもストレス溜めちゃうと思うんだよね。普段はあんなに温厚なのに、あんなに怒鳴っていて。あんな姿初めて見た」とか「どうやったら部下Bがもっと仕事が速くできるようになったり、ミスが減ったりするんだろう」という悩みを口にしていたわけです。
という事は、経営者の方も、上司Aさんと同じように「部下Bが、上司の話の意味を取り違えたことが問題だし、日々の仕事が遅くて、みんなにストレスを与えているのが問題だ」と考えているということが見えてきます。
もちろ、この件について、僕は経営者の方が話してくれた内容と、それまでにこの組織に関わらせてもらってきて見聞きしたモノくらいしか把握できていません。だから、実は、僕の方こそ「実際の行動や実際に起きているコト」が把握できていない可能性もゼロではないとも思ってはいます。でも、それを踏まえたうえで、こう思うんです。
「会社は、そもそも、なんのためにあるのか?」
「組織は、そもそも、なんのためにあるのか?」
「上司と部下という関係性は、なんのためにあるのか?」
「上司の役割とは何か?」
こういう“問い”をベースにしたうえで、現実に起きた“実際の行動・実際に起きたコト”を見ていけば、組織で起きている問題や、組織の中にある課題は、案外ハッキリ見えてくると思っています。
そして、上に書いたような“問い”がベースになっていれば、それらの問題や課題を解決に導く筋道もボンヤリと見えてくるんじゃないかと思っています。
ただ、逆に言えば、これらの“問い”を持っていなければ、自らこの“問い”を立てる必要がありますから、それができていないのであれば、組織の問題も課題もなかなか見えてこないんじゃないかと思いますし、もしもこれらの“問い”が無い状態だったり、しっかりと“考える”が進んでいなければ、「見えた」と思った問題も課題も実は検討違いだったりしてしまうことがあるんじゃないだろうか?
それがつまりは、冒頭に書いたような「実際にその人がとった行動、実際に目の前で起きているコト、それをありまのままに見て正しく受け止める」を邪魔しているのかもしれないなぁ、とも思っています。
起きていることをありのままに見て正しく受け止めることができなければ、その後に、一生懸命に選択して決断してする“行動”が全て徒労に終わってしまう可能性が高まります。
そんなのって、“誰にとっても悲しい結果”に繋がってしまうと思うんです。せっかく、大変なことをやるんですから、どうせだったら“誰にとってもハッピーに繋がるコト”になればいいなと思うんです。
そうやって、“三方よし”になるのがいいよなぁ。
欲張っていきたいんですよね、やっぱり。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
