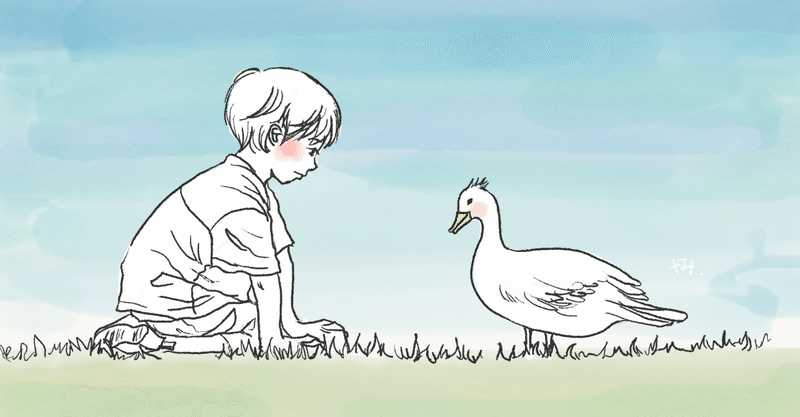
もともと何処吹く他人だから
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
組織開発という仕事をしていると、ふとした時に、『セロリ』が頭の中で流れ出す事がよくあります。
あの、山崎まさよしの歌『セロリ』です。
歌の冒頭の歌詞にはこうあります。
「育ってきた環境が違うから、好き嫌いは否めない」
「組織開発」で様々な組織に関わっていると、この歌詞の通り、「育ってきた環境が違うから」好き嫌いどころか、そもそも同じ言葉であろうはずの概念について話をしているはずなのに、それぞれの「育ってきた環境」の違いに端を発するであろう価値観の違いによって、全然別の話になってしまうという、複雑怪奇な現象が、本当によく起きているのをそこかしこで見聞きします。
組織の中では、日々、その組織が機能するために必要であろう多くの“概念”をそのメンバー間で共有するために、色んな言葉が飛び交います。
「会社」や「組織」や「仕事」なんかはその最たるものですし、「目標」や「成果」や「利益」なんていうのもありますし、「コミュニケーション」や「チームワーク」や「協力」なんかもありますね。
もちろん、まだまだたくさん飛び交っている言葉はありますが、そのどれもがそれを使用する各個人の価値観に委ねられてしまっている現状があるわけです。
例えば、「会社」という言葉を見てみると、Aさんは「会社=経営者達」だと思い、Bさんは「会社=役職者以上の人達」だと思い、Cさんは「会社=会社にいる全ての人達」だと思っている。
例えば、「仕事」という言葉なら、Aさんは「仕事=上司から指示命令を受けた事」だと思い、Bさんは「仕事=決められた事を決められた手順で進める事」だと思い、Cさんは「仕事=会社の目的を果たすために自分がやれる事」だと思っている。
こんな風に、それがどれだけ一般化している言葉だとしても、それらは全て「何らかの“概念”」について語る為の言葉だったりするわけで、それはその言葉を使用する各個人の価値観によって、「同じ言葉を使って、同じ概念を共有しようとしているはずなのに、ことごとく話は噛み合わずに、なぜかいがみあいになったり、口論になったりと、わかり合う事に繋がる道筋が見えない」という状況に陥っている人達や組織を、本当によく見聞きするわけです。
これについては、『セロリ』で歌われているように、「育ってきた環境が違うから」仕方のない部分ではあるわけです。
よく言われる事ですが、身近にいた大人達(恐らく、一緒に暮らしていた時間が最も長いであろう親の影響が一番強い場合が多いのかもしれません)が、「仕事は大変」とか「仕事はツライ」とか「お金を稼ぐには我慢する事が必要だ」みたいな言葉を常に口に出していたり、口に出していなかったとしても、そういう態度や振る舞いで「暗黙のメッセージ」を常に発信し続けていたとしたら、その環境の中で育っってきた人が、いざ仕事をするようになった時には、当然ながら「仕事はツラくて大変で我慢する事で生活が成り立つんだ」と思う事が当たり前の状態で、初めての仕事に就くわけです。そうなると、その人が、「仕事って楽しいものだし、楽しいうえに自分の学びにも繋がって、収入にも繋がる」という風に考え方が変わる為には、相当のきっかけや努力やそれなりの取り組みが必要になってくるわけです(ここでは、かなり話をデフォルメして書いているので、もちろんこんなケースだけじゃないのは当然ですが)。
一方で、身近にいた大人達(親など)が、「仕事とは、この社会に価値を生み出すもの」とか「仕事とは、自分の働きによって他者の幸せを後押しするもの」とか「仕事とは、自分も相手も社会も三方が良くなる為のもの」という事を、常に口に出していたり、口に出していなくても、そういう態度や振る舞いで「暗黙のメッセージ」を常に発信し続けていたとしたら、その環境の中で育ってきた人が、いざ仕事をするようになった時には、当然ながら「仕事は社会に価値を生み出し、他者の幸せに貢献し、三方良しを叶えるものだ」と思う事が当たり前になっているわけです(以下略)。
そうなると、この全く違う背景を持った両者が「仕事」についての話をした時には、全く話が噛み合わない状況が発生するのは容易に想像できますし、現に、こんな状況が生まれているのは本当に至る所で目にする事も耳にする事もあるわけです。
この両者が存在した時に、どちらが正しいのか?という事にはあまり興味がありません(とは言いながら、僕の考え方は後者に近いし、常にそう在りたいとは思うわけですが)。
それよりも、どうしたらこの両者が「同じ目的を共有して、それを成し遂げる為に、協力して円滑なコミュニケーションを取りながら進んでいけるか」という事だけが気にかかるし、僕たちが関わるのであれば、その部分が上手くいくように関わっていきたいなと思うんです。
これを可能にしようと思ったら、ただ異なる価値観を両者がぶつけ合っているだけでは到底無理な話です。
もちろん、とても運が良い人達なのであれば、“たまたま”うまく行く事もあるとは思いますが、それは本当に稀なケースだし、そうそう偶然はやってきません。
じゃあ、どうするのか?
そこで、「対話」です。
ルールのある「対話」を行う事で、うまくコミュニケーションを取る事ができる環境を作り出す事が可能です。
ルールの一部を抜粋するとこんな感じです。
「何を言っても良いけど、お互い否定的な発言や態度はせず、「なぜそうおもうのか?」質問し合う、そして、結論を出そうとしない」
そうやって「対話」を重ねていけば、いずれ、「わかり合える部分」と「わかり合えない部分」が見えてきます。
「わかり合える部分」はわかり合えるので、わかり合った状態で協力していけば何の問題もありません。
「わかり合えない部分」はわかり合えないので、わかり合えないという事をお互いに認識しあった上で、これまた協力していけば何の問題もありません。
決して、お互いに自分の価値観や考え方を押し付け合う事のないようにします。ただただ、お互いの中にあるモノをお互いによくよく観察して、受け止めます。
そのうえで、組織が掲げている「目的」を成し遂げるためには何が必要なのかを一緒に考えましょう。
ただこれだけです。
これだけで、驚くほど、うまくいきます。
(僕たちは、実際にこれをやってきているし、今もやっているからこそ、こんな話ができるわけですし、そのメカニズムもわかるし、なぜそうなるのかもわかっているのでこんな風に断言してしまいます)
話は、とても単純なんです。全く複雑な話ではありません。
だけど、簡単ではありません。
単純だけど、恐らく、とても困難な道のりです。
単純で、とても困難だからこそ、『セロリ』ではこんな事も歌っています。
「がんばってみるよ、やれるだけ。がんばってみてよ、少しだけ」
歌の中に描かれている1対1の関係性でさえ、「頑張ってみる」が必要なくらい困難な道のりです。であれば、組織という自分対複数の他者という関係性なんですから、「少しだけと言わず、やれるだけ頑張る」のはもはや必然なのかもしれません。
ところで、この『セロリ』という歌は、僕からすると「山崎まさよしの歌」なんですが、人によっては「SMAPの歌」という人もいるのかもしれません。
これもきっと、永遠にわかり合えないところだとは思いますが、僕にとっては「山崎まさよしの歌」であり続けるわけですが、もちろん、「SMAPの歌」という価値観を否定するものではありません。
そこはお互いに「『セロリ』が好き」で協力していけるんじゃないかなと思っています。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
