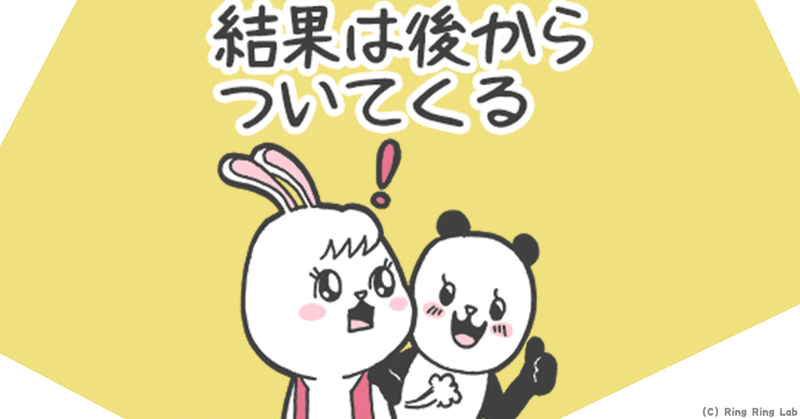
尽くすのは人事だけじゃなくて情理もね
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
その昔、何かの本で読んでから気に入っている言葉に「情理を尽くす」という言葉があります。
読んで字のごとく、「“情”と“理”を尽くす」という意味なんだろうと受け取っているんですが、これが案外と「難しいことだなぁ」と感じます。
“情”は「なさけ」とも読めるので気持ちや真心や誠意などと呼ばれるような様々な感情のことでしょうし、“理”は「ことわり」とも読めるので理屈や合理性や理合いなどろ論理のことなんだろうと考えています。
自分が仕事をするとかコミュニケーションをはかる際には必ずそこに“他者”が存在するわけなので、この「情理を尽くす」という“感情(パトス)”と“論理(ロゴス)”という相反するモノをどちらも“尽くす”行動をしようという心構えのようなモノとして活用しているんですが、この「相反するモノを同時にどちらも最大限出力する」ということがどれくらい難しいのかということは自分の実体験としても感じますし、恐らくずっと昔から人間が抱える課題として言われ続けてきたんじゃないかなとよく思います。
例えば、夏目漱石の『草枕』の一節にもそれが顕著になっているんじゃないかと思っています。
「知に働けば角が立つ。情に掉させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」
最も有名なのは“矛盾”の語源といわれている寓話もありますし、今の世の中だけではなくていつの世も人間が社会を織りなして暮らしている限りはずっとこの「相反するモノを同時にどちらも最大限出力する」ということは無理筋であり矛盾していると捉えられてきたんだろうと感じます。
その一方で現代の社会で“仕事”の中で考えてみると、人間社会でずっと「それが必要だ」と思われつつも「無理筋だし矛盾してる」と思われてきたであろう「相反するモノを同時にどちらも最大限出力する」ということが実はとっても大事であり、実際にやってみると(かなり大変だったりはするけど)案外と「“実現可能”だ」ということが見えてくることがよくあるのを実感します。
例えば、組織の中で“相反する対立した意見”がぶつかり合ったりA派とB派に分かれてしまって物事が進まないという時に、そのどちらか一方に決めるのではなくて“どちらでもない別の案”を創り出してA派もB派も納得することで第三のC案で進めていく、なんていうこともできたりするわけです。
これは例えば“矛盾の寓話”の中で「“最強の矛”と“最強の盾”をぶつけたらどうなるの?」という“問い”ではなくて、「“最強の矛”と“最強の盾”を両方持って使ってみたらどうなるの?」という“問い”に変えるような感じなんじゃないかと思っています。
これを僕と仲間は「矛盾の統合」と呼んでいるんですが、この「“どちらか一方”ではなく“どちらも両方”」というある意味で強欲な考え方を取り入れることで「情理を尽くす」というのは可能になると考えています。
そしてそれを可能にするための手法が“対話”だと考えています。
“対話”はまさに「“AかBかを決するモノ”ではなく、対話の場にいる人達みんなで合意できるような“AでもBでもない新しいナニカ”を創り出す行為」という意味があるモノだと考えています。
もうちょっと正確に言えば「AやBを材料や原料にしたうえで、みんながほんの少しずつだけでも合意できるナニカを創り出す行為」です。
A派は「Aなら100%同意できるがそれ以外はダメ」、B派は「Bなら100%同意できるがそれ以外はダメ」、なんて感じで考えているのかもしれませんし、そう考えているからこそ“自分と同じ考え以外のモノ”には反対するし排除しようとしてしまうのかもしれません。
だけど、それではあまりにも可能性が狭まるんじゃないかと思うんです。何しろ、「自分と同じ考えでなければ許容できない」というのであれば、その組織にはもう持続可能性は無くなってしまいます。
何しろ、現時点で「○○派の考え方じゃなきゃダメだ」と考えているということは、これから環境や状況が途轍もなく大きな変化をした場合(例えば、○○派でNGとされていたモノが世の中でOKとなったりした場合など)には、もはや“それまでの〇〇派”ではいられなくなってしまいます。
ということは、いつでもどんな考え方でも“柔軟性”とか“余白”とか“伸びしろ”みたいなモノを必ずどこかにある程度は持たせておかなければいけないはずです。
そうなると、「絶対に〇〇派じゃないとダメだ」なんてことにはならないんじゃないかと思うんです。
それがなければ「変化に適応できない」ということになってしまうので、いわゆる進化論的な考え方をすれば「生き残っていくことができない」ということになってしまうので当然ながら持続可能性も失ってしまうんだろうと思っています。
その辺りは、(これまた随分と昔から言われている)「三方よし」の考え方こそが“仕事”における「情理を尽くす」や「矛盾の統合」とも言える考え方なんじゃないかと思っています。
「三方よし」とは「売り手よし、買い手よし、世間よし」であり“売る側”と“買う側”という商売を成立させる二者間だけではなく、その二者が存在するために必要不可欠である“二者以外の人達みんな=世間”も含めて「よし」と言える、「よし」と考えることができる商売でなければダメだよねという考え方です。
「一方よし」は“売り手”だけが「よし」と言える商売です。「二方よし」は“売り手”と“買い手”だけが「よし」と言える商売です。
これらについては具体例を挙げるとそれこそ“角が立つ”になりそうなので一般論だけにしておくと、例えばいわゆる“転売ヤー”というような取引なんかは「一方よし」の場合も「二方よし」の場合もあるんだろうなと思っていますし、どうやってどんな理屈をつけようとしたところで「三方よし」になることはありません。「智に働いて角が立ったり、意地を通して窮屈になったり」ということが起きてるんだろうと思います。
だからこそ、真っ当な商売として「三方よし」を実現させて、例え売り手も買い手も世間も“ほんの少しずつ”しか「よし」にならなかったとしても、しっかり「三方がよくなる」ことが必要です。
そのためには、
「智に働いても角が立たず、情に掉さしても流されず、意地を通す必要も無いので、とかくに人の世は住みやすい」
なんて状態を「情理を尽くす」ことで実現できるように、組織全体で“対話的”になっていけるといいんじゃないかなと考えています。
そしたらきっと“矛盾した状態”だと思うような状況に陥ったとしても、組織のみんなのアイデアを材料にすることで「矛盾の統合」ができるような新しい道筋が創り出せるんだろうなと思っています。
もちろん簡単なことではないですし大変で苦しいこともあるかもしれませんが、案外と話は単純明快なんじゃないかなとも思っています。
つまりは、「情理を尽くす」ことで「矛盾の統合」をするっていうのは、自分自身が痛みと喪失感を伴って変化に適応していくという「適応課題」の話だってことなのかもしれません。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
