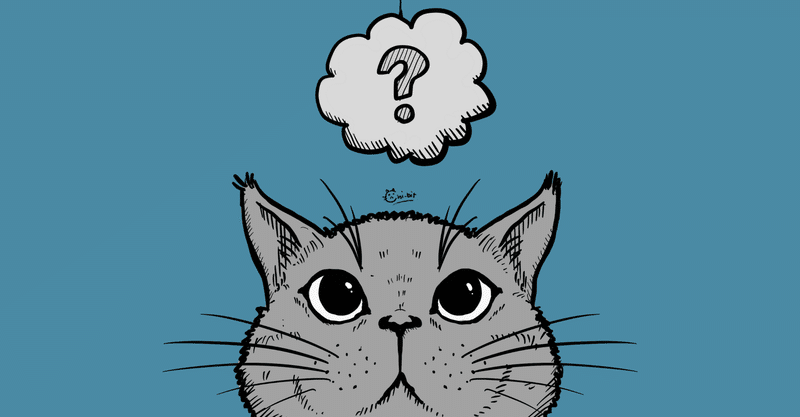
わからないからやるんだよって思ってる
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
「え?そんなの当たり前じゃないの?」
このnoteを読んでくれた人がいたとしたら、そのほとんどの人にそう思われるのを承知ではありますが、今日は敢えてそんな内容について書いてみようと思います。
それは、
「知識があると、モノを考えられる広さとか深さとか高さの範囲が大きくなるよね」
という内容です。
読んだ瞬間に、冒頭の突っ込みをしてくれた方、ありがとうございます。
本当に、当たり前だし、その通りなので今日の話もこれでほぼ終わってしまいます。
だけど、それで終わるのなら、わざわざこんな話題を選ばないよ、とも思っているので、もう少し「解説者」としての役割を果たせるように頑張ってみようと思います。
まずは、大前提としてこんな流れがあると思うんです。
知識があると、「何か」を見たり聞いたりした時に、その「何か」とそれまでの知識が絡み合って、それまでに見えていなかった「別の何か」が見えてきたり思いついたり、といった、それまでに自分の中に無かった「新しいモノ」が生まれる事に繋がる可能性が高い。こういう流れです。
そんな、とても当たり前の流れなんですが、その「何か」とか「別の何か」とか「新しいモノ」というのが、実はとても個人差が出てくるところであり、その個人差が、いわゆる「意味」とか「価値」といったものに繋がっていく為の、扉だったり道筋だったりするのかなと思っているんです。
僕にとって、そんな事を考える時は、主に「本を読んでいる時」なんです。
本を読んでいると、時折、今その時に読んでいる本とは全く別の事柄が頭の中にふと浮かんでくる事があります。
例えば、「これって、○○に書いてあったアレと同じ事じゃん」とか。例えば、「ああ、ここに書いてある事って全然関係ないジャンルだけど△△の□□理論と同じだ」とか。例えば、「これ、あの漫画のあのキャラが言っていた事と同じ内容の事言ってるんだ」とか。
他にも、「この時代のこの人がこんな事を言った(やった)からこそ、後の時代のあの人のあの言動に繋がっていたのかもしれない」などの歴史的な流れが見えてくる事によって、その流れと、現代のそこかしこで起きている事が同じような流れを辿っているのが見えてくる事で、これから先の選択と行動の中の「正解」はわからないまでも「不正解」は見えてくる感覚が手に入ったりするというのが、自分の中でよく起きているのを感じます。
僕が読む本のジャンルとしては、仕事にダイレクトに生きてくるような、経営や組織や人材やマネジメントや仕事術と言うような類いの本の分量は、全体の読書量からすると割合的にはそれほど多くを占めていません。もちろん、必要に応じてそれなりには読みますし、最先端を行っている研究に関するモノはこれまた必要なので目を通します。
でも、それらの類いの本よりも、「これ、おたくの会社の仕事にどう関係するの?」というような題名や内容の本の方が、ウチの会社の本棚スペースの大半を占めているような現状です。ホントに様々なジャンルの多種多様な本がたくさん並んでいる状態です。読んだ本はほぼ全て面白かったし、まだ読んでない本は(たくさんあります)、早く読みたい本ばかり。
だけど、もし、僕にもウチの会社に全く興味が無いし、一緒に仕事もしない人がウチの事務所に来てあの本棚を見たとしたら(完全に在り得ない状況ではありますが)こんな事聞かれるのかもしれないなあと、今思いました。
【一見、組織開発・人材開発や管理職育成といったウチの事業とは、直接的な関係が全く無さそうなこれらの本が、一体全体、プロタゴワークスという会社の仕事にどう関係するのか?】
こんな「問い」が向けられたとしたら、僕は冒頭に書いたような事を答えるとは思います。
でも、きっと答えるのはそれだけじゃないとも思っています。
なぜなら、僕は普段からこんな事を考えているからです。
「それをして何の役に立つのか?」こう問われて、例えばスポーツ競技の選手が競技の技術練習や、その補助として行うウエイトトレーニングの意義や効果について答える。そういう事であれば、大いに正しいんじゃないかと思うんです。なぜなら、「その競技において、何ができる事が必要なのか?」というのが明確になっているからです。
100m走と言う競技であれば、「100mをどれだけ速く走る事ができるか」を競うというのは、どんな人であっても明確に理解できているので、そのために行う練習やトレーニングが「100m走を速く走る事に繋がらない」のであればそれはやる必要の無い事です。
もちろん、「100mを速く走れるかどうか」については「やってみなければわからない」という「未来の不確定さ」はもちろんありますが、実際にはこの「未来の不確定さ」が影響を及ぼす事はそれほど高い可能性として存在しているわけではありません。
その「未来の不確定さ」よりも、それまでの「過去に確定した物事」の方が重要なわけです。いわゆる、これまでの練習で100m走をどれだけの速さで走ることができたのか?という「過去に確定した物事」である記録が速ければ速いほど、いわゆる本番でも速い結果が出る可能性が高い。
だけど、「スポーツ競技というジャンルだけが同じ」という枠組みで考えるならば、格闘技などの「対人競技」については、個人競技よりも「未来の不確定さ」の方が圧倒的に結果に影響するわけです。何しろ、自分にはどうする事もできない部分が「常に50%存在する」わけです。もちろん、今は便宜上「50%」と数字にしましたが、これも前提は「相手と自分の実力が全く等しく拮抗している場合」なので、現実的には「有り得ない状況」なわけです。つまり、頭の中の空論ではなく「現実世界」においては、この「未来の不確定さ」を数値化する事は絶対に不可能なわけです(この場合の“絶対”は人の心の中や頭で考えている事を外から感知する事ができないという認識が前提になっています)。
そうなると、「対人競技」というだけで、もう結果は誰にもわからないわけです。誰がどんな予想をしようが、誰が何を言おうが、あらかじめわかっている結果は存在しないし、そもそもその対人競技の時間の中でどんな事が起きるのかはそれをやっている当事者にもわからないんだから見ているだけの人に何かがわかるはずもなく、結果がわかるのはいつだって常に「終わった後」なんです。当然の話ではありますが。
でも、これが当然の話なのであれば(もちろん、当然の話なんですが)、これはあくまでも「競技」を想定した話なのであって、日常の中で起きる様々な人が絡みあってできあがる「仕事」とか「働く」という状況の中では、もっともっと想定できないような状態になるし、なっているし、そうじゃない状況は存在していませんので、あんな「問い」はそもそも成立しないという事が見えてくるんじゃないかなと思うんです。
【一見、組織開発・人材開発や管理職育成といったウチの事業とは、直接的な関係が全く無さそうなこれらの本が、一体全体、プロタゴワークスという会社の仕事にどう関係するのか?】
上にも書いたこの問いは、僕が、自分自身やウチの会社に向けた問いです。なので、この「問い」自体は、ウチの会社以外の人達には何の意味も無い問いになってしまいます。
それじゃあもったいないという事で、せっかくなのでこの「問い」を一般化してみます。
こんな感じではいかがでしょう?
【それを“やる”事は、○○にとって(○○には適当な対象を入れてください)、どんな意味があるのか?】
もし、その○○が、「過去に確定した物事」が重要な事柄であるのなら、この「問い」にはすぐに答えが出るはずです(そもそも、この「問い」自体が立たない可能性は高い)。
だけど、その○○が、「未来の不確定さ」ばかりの事柄であるのなら(例えば、対人関係が存在するような事柄など)、この「問い」を考える事自体にそもそも意味が無いんじゃないかなと思うんです。何しろ、考えてもわかりようが無いんですから(未来が見えるという人についてはこの限りではないと思いますが、そういう人の存在を僕はまだ知らないので)。
ただ、これで終わりになるなら、せっかくここまで書いてきた意味が何も無くなってしまうので、「敢えて」書いてみようと思います。「未来の不確定さ」ばかりの事柄であっても、「それをやる事にどんな意味があるのか?」という「問い」について。
僕が考えているその「意味」とは、「何が起きるかわからないけど、何が起きても対応できるようになるため」なんじゃないかなと。
未来は不確定なんだから、その不確定な未来にどんな事が起きるかはわからない。でも、「何か」が起きたその時に、「どうしたらいいんだ?」と困っていても、困っているだけで立ち止まっていたら多分すぐに死んじゃうと思うんです。そんな時には、きっと、「選択してはいけない事=選ぶとアウト」な選択肢が山ほどあるんだと思うんです。そして、それはどの選択肢なのかは誰にもわからない。もちろん自分にも事前にわかるはずはない。
だけど、「いざと言う時」には、数少ない、もしかしたら、唯一かもしれない「死なない選択肢」を選べるようになっておく為に。
これが、「問い」に対する回答なんじゃないかなと、僕は思っているんです。
もちろん、そんな場面が来ないにこした事はありません。
この先一生、そんな場面が無い事を祈ります。
でも、僕はこれまでの人生の中で、何度か「そんな場面」に遭遇してきました。
僕以外の人達も、多かれ少なかれ「そんな場面」に遭遇してきたんじゃないかなと思うんです。
今現在、生きているという事は、「そんな場面」だと気づいていたか気づいていないかはわかりませんが、とにもかくにも切り抜けてきたんだとは思います。
今後は、「そんな場面」にいち早く気づいたり、「そんな場面」での選択を誤らないようにしたり、そもそも「そんな場面」を上手に回避したり、なにより「そんな場面」がやって来ないように先回りできたりする。
そんな生き方をしていくためにも、知識を増やして、それを「何か」と繋げて「新しい何か」を生み出していけるように、「何に役立つのかはよくわからない事柄」を積極的に増やしていって、それを何かの折に、ブリコラージュしてうまく役立たせるというのが、これからの時代を生き抜いていくためには必須なんじゃないかなと思うんです。
そんな事を考えると、ブリコラージュをはじめとした文化人類学と組織開発と武道・武術・格闘技の概念と哲学なんかは、めちゃくちゃに相性がいいんじゃないかなと思って色々考えているところです。
だけど、僕の中にある知識と体験の範囲では、これらが全部繋がっている感覚があるんですが、それらを一切知らない人達にうまく伝える事ができるレベルまでにはもう少し色んな知識や体験が必要なのかもしれません。
これをできるようにする為に必要な知識があったら手っ取り早く知りたいなあ(矛盾)。
あかね
株式会社プロタゴワークス
#ビジネス #仕事 #群馬 #高崎 #対話 #組織開発 #人材開発 #外部メンター #哲学対話 #主役から主人公へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
