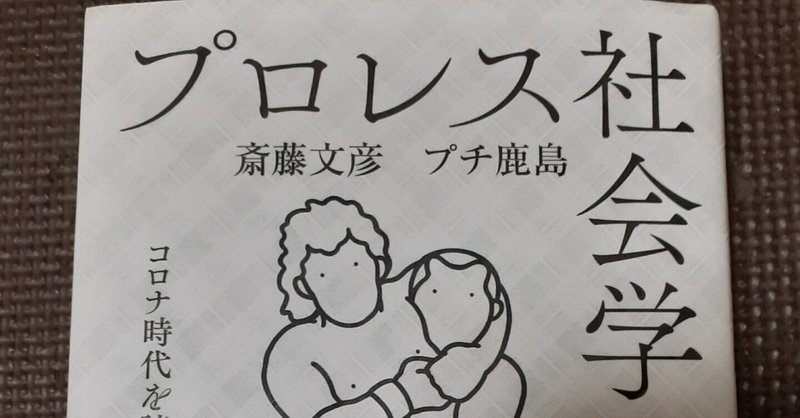
ずっと考えていきたいと思います
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
この休みで、『プロレス社会学のススメ』という本を読んでいました。
内容は、プロレスファンであれば誰もが知っているであろう“フミ・サイトー”こと斎藤文彦と、プチ鹿島の対談を収録した内容です。その対談の進行役は、堀江ガンツが行っている、雑誌『KAMINOGE』の企画から出来た対談本のようでした。
この本を買った経緯としては、他の本と何ら変わり無く、「たまたま本屋に行った時に目に付いて興味を惹かれたから」という何の変哲も無い理由ではありますが、ここ1~2年の間に出版されたプロレス関連の本の中ではかなり異質な題名だったから惹かれたというのがとても大きな理由でした。
ここ最近のプロレス関連本の流れが出版サイドでどう捉えられているのかは分かりませんが、頻繁に本屋に行ってプロレス関連コーナーを覗いている身としては、数年前に出版されて結構売れた『1984年のUWF』や『真説佐山サトル』以降(これらは読みたくて購入しました)、UWFに関する当時の証言的なモノを集めていそうな本や、それ以外の団体の当時の証言を集めていそうな本である“ノンフィクション的な本”がたくさん並んでいるように感じています。ただ、実際にはそれ以降に出た本を手に取って読んだことは無いので「○○を集めていそうな本」という書き方しかできませんが、個人的にはそこまで興味を惹かれるような内容のモノが無かったのも事実です(プロレスラー本人が書いた本では、TAJIRI選手の本はとても面白かったです)。
そんな中で、久々に「これ、面白そう!」だと思って手に取ったのが『プロレス社会学のススメ』でした。
装丁もタイトルもシンプルで、一目見て、“プロレス関連本コーナー”に並んでいるどの本とも全く毛色も主旨も異なっているであろうことも、対談者として名を連ねているのがこの両名ということも、「面白そう!」と思わせてくれる大きな要因でした。
で、読んだら、やっぱり面白い。
何しろ、内容は全て“プロレスのこと”しか話していないんです。
それなのに、プロレスを考察する事を通してこの社会の事をも考察できる内容、すなわち「プロレス社会学」になっているのが、何とも言えずさすがだなと思わされました。
よくあるプロレスファンの間で交わされるような話とか、あまり質の良くないプロレス本のような、「ただただ延々と昔のプロレスの試合やプロレスラーについての知識が羅列されて、その場にいる人達だけで盛り上がって終わっていく話」に終始するわけではなく、しっかりと事実に基づいていて、しかも、フミ・サイトーにしか語る事の出来ないような“プロレスの知識”がベースになりつつ、そこへ“当代随一のプロレス知識人”と言っても過言ではなさそうなプチ鹿島による“プロレスファン”としての目線の話をベースにして“現代の社会情勢を分析する”視点が合わさって、この二人にしか生み出せないような、とても面白い「プロレス社会学」が延々と語られるとても素晴らしく面白い内容でした。
僕は、長年のプロレスファンとはいえども、プロレスを見始めたのは80年代後半の全日本プロレスのジャンボ鶴田vs三沢光晴の時代からでしたので、それより以前のプロレスはあまり見たことがありません。なので、この本に書いてあるプロレスの試合についてはほとんど知らないし、アメリカンプロレスについても『レッスルマニア』を何本か見た程度で、知らない選手や知らない話がほとんどでした。そもそも、特定の団体や選手のファンではなく、言うなれば「プロレスというジャンルのファン」を自認しています。
この本の中に書いてある事実について、ほとんど観たことの無い知らない話ばかりだった僕にとっても、とても面白い本でした。
その面白さの理由はきっと、この本に最初から最後まで感じられる「プロレス愛」なんじゃないだろうかと思っています。
例えプロレスの知識や観戦経験やファン歴が乏しくても、例えそれらがとても豊富だったとしても、そこに「プロレス愛」があるなら、知識や経験や歴の多い少ない長い短い大きい小さいは一切関係がありません。
「知らなきゃ語れない」なら、「観てなきゃ語れない」なら、「ファン歴が長い方が偉い」なら、そんなジャンルはとっくの昔に廃れていますし、そもそもそんなのあまりにも器が小さすぎますし愛がなさ過ぎます。
そんな“小さなこと”は全く関係なく、あらゆるモノを丸ごと抱え込んでその内側に取り込んでしまうその器のデカさを持つのがそもそも“プロレス”というモノなんだと思っていますし、究極の“多様性”と究極の“自由”を備えているのがプロレスの魅力の内の一つなんじゃないかと思っています。
そんなプロレスの魅力をもって、この社会を読み解こうとするこの本は、ここ最近で読んだプロレス関連本の中ではとても秀逸で面白い本だったと感じています。
プロレスに興味が無い人からするとこの本がどう映るのか、読んでみてどう感じるのか、など聞いてみたい気もしますが、そんな感想を聞くことはきっとないんだろうなと思いつつ、「プロレスを通して、この社会情勢というオールジャンルを語る事ができる」というプロレスというモノの持つポテンシャルを、この本を通じて色んな人に感じてもらえるんじゃないかと読み終えた今一人で妄想しています。
『プロレス社会学のススメ』、プロレスファンには当然おすすめですが、プロレスに興味が無い人にもおすすめです。
そしてこの本を読んで永遠に答えが出ないであろう途轍もなく哲学的な問いを一緒に考えませんか?
その問いとはもちろんこれです。
プロレスとは何か?
あかね
株式会社プロタゴワークス
https://www.protagoworks.com/
#ビジネス #仕事 #群馬 #高崎 #対話 #組織開発 #人材開発 #外部メンター #主役から主人公へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
