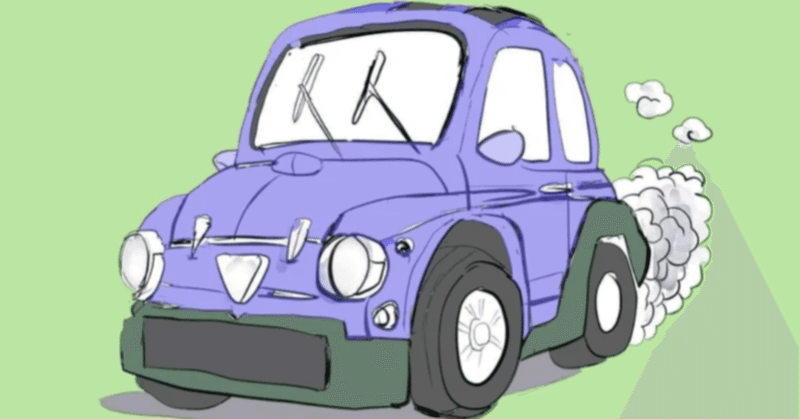
予想もしなかった学びの場
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
先日、某社のカーディーラーに立ち寄ることがありました。
車の運転は日常的にしていますが、カーディーラーにはとんと縁が無く、これまでにも数える程しか入ったことが無い場所なので、僕にとっては店内に入るためにいつもより少し多めの勇気が必要になる場所です。
そんな、アウェイ感満載の場所ですが、これまたいつも行くたびに感じるんですが、そこにいるスタッフの方々がとっても良くしてくれるので、行く前と行った後でのギャップを勝手に感じてる場所でもあります。
そうして元々の用事について一通りの話を終えた後で、ディーラーで取り扱っている認定中古車の話を聞かせてもらうタイミングがありました。
そもそも、僕自身が車には乗っているにもかかわらず、車への興味関心がほとんどないのでディーラーという場所がどういう場所なのかもわかっていませんし、中古車というものがどういう経路を辿ってお店までやってくるのかも全くわかっていませんでした。
ただ、いつもいくガソリンスタンドで以前にタイヤ交換をしてもらった時に、僕の車の走行距離を見て“営業”をかけられた際に、そのガソリンスタンドでは「整備工場を持っていて、中古車の仕入れをして、自社の整備工場で整備して販売もしている」という話をかなりじっくり聞かせてもらいました。その時に、「どうやら中古車はオークションで競り落として販売をするという経路があるらしい」ということを初めて知りました。
そんな半端な知識くらいしか無かったんですが、ディーラーではオークションで競り落とすわけではなく、顧客から下取りした車を整備して販売しているということでした。そして、ディーラーで下取りする車の多くはディーラーでメンテナンスや修理をしている車が多いのでそれらの履歴がわかっている状態であり、そもそも“仕入れ”に中間業者を通さないので安く販売できるというようなお話でした。
そんな話を聞かせてもらって、自分の全く知らない業界であり、これまで全く興味を持ったことのない流通の話だったので、「すげー面白いな、この話」なんて思って色々質問をさせてもらったりしていたら、なんだかとても楽しい時間になりました。
そんな面白い話を聞いた帰り道に、ふとこんなことに思い至りました。
「あれ?てことは、“ディーラー”と“中古車販売店”ではパッと見では「全く同じ商材(=車)」を扱っていて、その顧客も「車」というモノを求めて買いに来るけれども、そもそもターゲットにしている顧客が全く違うし、ビジネスモデルが全然違うってことなのかもしれないぞ?」と。
僕が以前に営業をされたガソリンスタンドのように“オークションで中古車を仕入れて販売する”という形態をとっているお店では、その多くが「色んなメーカーの色んな車種を取り揃えているので選んでください。この中に無ければオークションで競り落としてくきますよ」というサービスをしてくれるようです。
このサービスをしてくれる “中古車販売店”に対して顧客が求めるモノは色々あるとは思うんですが、本質的には「自分の気に入った車をできるだけ安く手に入れたい(だから、それが叶いそうな“お店”で買う)」なんじゃないかと考えられます。お店側も、それがわかっているからこそ、そして、それを提供したいからこそ、店頭や宣伝に「豊富な車種を取り揃えている」とか「安い」ということを全面的に押し出しています。
一方で、“ディーラー”で扱う中古車は、件の店員さんの話によれば「基本的に下取り」だと考えると、ある意味では「“このメーカーの中古車が欲しい”という人だけを対象にしている」とも考えられます。
そもそも、中古車を購入したいと思ってディーラーに来た人の要望に応えられる在庫や仕入れが“その時”あれば、(扱える範囲の)同社ディーラーの在庫から探せるけれども、オークションに出て行って仕入れてくるということはしないわけですから、「今ある物の中から選んでもらう」スタイルになるわけです。
ただ、そういう制約があるとしても“メンテナンス履歴”や“修理履歴”や“走行年数”などの、言うなれば「車の人生(車生?)を全て把握している状態で、車メーカーの威信をかけて整備をしたモノ」を提供しているとも考えられます。
そして、「ディーラーが認定中古車販売をしている」というビジネスモデルをもう少し見ていくと、そこには“動線”が見えてきます。それが、認定中古車の売りにもなっている「“メンテナンス履歴”と“修理履歴”が明らかである」というところから見えてきます。
ディーラーで認定中古車を買った人の多くは、恐らくディーラーでメンテナンスや修理や車検を行うことが予想されます。もちろん“絶対”ではないでしょうが。
ディーラーでメンテナンス等をしないのであれば、ディーラー以外ですることになるわけです。そうなると“何らかの理由”がありディーラー以外の場所で整備をしてもらう(もしくは、自分でする)ことになります。そうなると、そこには“何らかのツテ”も無いとなかなか難しいでしょう。
ただ、“何らかの理由”と“何らかのツテ”がディーラー以外の“車を整備できる場所”にあるんだとしたら、その“ツテ”を辿ることでディーラー以外から中古車を購入することもできるんじゃないかなと思うんです。
なので、そうやってディーラーから認定中古車を買って、ディーラで整備をしてその車に乗っていく人は、購入後もディーラーに定期的に訪れることになる可能性がとても高いと考えられます。そして、「車の部品は消耗品」です。
当然ですが、その車を安全に乗り続けるためには消耗した部品を交換し整備が必要になりますし車検も必要です。そんな、いわゆる“保守・メンテナンス”を定期的に行うことで、ディーラーと顧客との関係性は強くなっていくでしょうし継続していくでしょう。
そして、その関係性が維持されていくことで、次の購入ーそれが新車になるのか、中古車になるのかはわかりませんがーに繋がっていくことは、かなり高い可能性で考えられます。
そんな風に考えると、同じ“車”を扱っていて、少し前の僕には「全く同じ仕事をしているところ」に見えていた、“中古車販売店”と“カーディーラー”の違いが見えてきたような気がします。
中古車販売店は、“「今、安く買いたい」という顧客とのマッチングをはかって、商品(=中古車という有形の物)を提供して利益をあげるビジネスモデル”。
カーディーラーは、“顧客に安心して車に乗ってもらうために、短期的な売り上げではなく長期的な関係性構築を見据えて、その顧客に合ったサービス(=中古車・新車・メンテなどの有形無形のモノ)を提供して、時間をかけて信頼を積み上げていきながら利益をあげるビジネスモデル”
全く同じ商材である“車”を扱っているにもかかわらず、そもそも顧客にしているターゲットが全く異なっていて、さらにビジネスモデルもこれだけ違うということを、たまたま行ったディーラーで、たまたま聞かせてもらった話から気付けたというのは「めちゃくちゃ収穫だったなぁ」と感じています。
ウチが目指しているのも、まさにこの“カーディーラー型”のビジネスモデルです。目指すのは“短期的な売り上げ”ではないですし、提供するのは「どの相手であってもこちら側で用意した決まり切った定型の知識や情報」などではなく、パートナーとなる企業の個別の事情や個別の必要性に応じてオーダーメイドでのサービスであり、その組織・そこで働く人たちに適したモノを適した形で利用してもらえるように取り組んでいます。
今回気付いた“カーディーラー型”のビジネスモデルをあらためて整理してみて、自分たちの仕事に照らし合わせてみることでまた色んなことが見えてきたような気がしています。そして、やっぱりポイントは“時間軸の長さ”にあるんだろうなという気もしています。
(当然ではありますが、ここで書いている”中古車販売店”とは、過去に僕が出会ったことのある“中古車販売店”を想定しており、全ての中古車販売店が「この通りである」と考えているわけではありませんし、実際に「この通りではない」という中古車販売店の取り組みも聞いたことはあります。なので、「ウチはこんな取り組み方じゃないよ」というビジネスモデルの中古車販売店もあるとは思っている前提です。そこまで書くと長くなりすぎちゃうので一般化したような書き方をしています)
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
