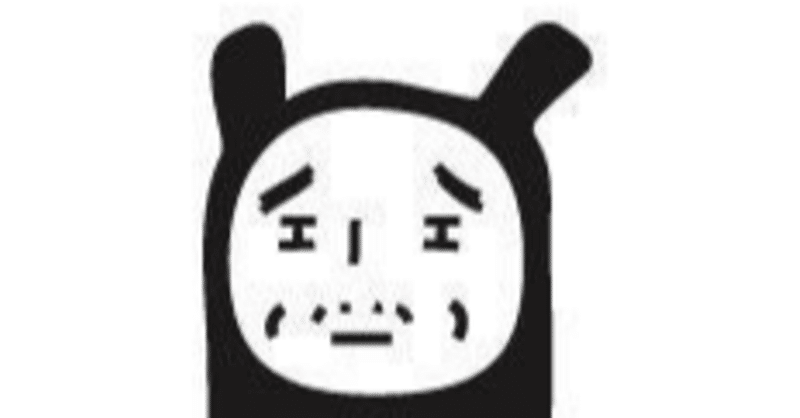
わからないものはわかりません
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
他社の組織開発にかかわらせてもらう中で、経営者や社員の方々の話しを聞かせてもらう機会がたくさんあります。
そうやって“他者の仕事の話”を聞かせてもらっている時にいつも湧いてくるのがこんな疑問です。
「それってつまりどういうことなんだろう?」
なぜなら、僕にはその話をしてくれている人達が日常的にしている仕事についてはよくわかりません。
「仕事についてよくわかりません」とだけ書くと誤解を招きそうなので、もう少し正確に言えば、この社会に存在する様々な“業種”とか“職種”についての体験や知識や情報は、就職支援の仕事を長年してきた経験と、自分自身が様々な業種や職種の経験があるので、いわゆる“仕事についての知識”は豊富に持っていると自負していますし、実際に、話しを聞けば“ある程度”の想像や推測で補うことができるので、これまで「相手の話してくれる仕事をイメージすることができない・わからない」と困ったことは一度もありません。ただ、具体的に「どんな物を使っていて何をどんな風に扱っていてどんな動きをしているのか」などのような“本当に細かい具体的な部分”については、その現場を見ていないので僕には全くわかりません。
そこで、話を聞きながら、上記のような疑問が湧いてくるわけですし、この疑問が湧いてきた時にはできるだけその場に“問い”として投げかけるようにしています。
例えば、“現状の社内での採用で応募者を見る時に重要視しているポイント”として「モラルがあるかどうかは大事だよなぁ」という話しが出た時に、数名の社員さんがその話しに同意をして、その場であたかも合意形成ができたような状態になった時に投げかけてみたり。
「モラルがあるって、どういうことを言うんですか?」と。
すると、「う~ん・・・モラルがあるって言うのは、何て言うか、正しさがわかるとかやっちゃいけないことをやらないとか?」「確かに。やっちゃいけないことをやらないってのは大事ですね」「善悪がわかるってことですかね」「そこって、入ってきてから教えられることじゃないような気がするんですよね」etc。
こんな話が出てきたりするわけです。そうして、こう問いかけます。
「それって、採用の時に、何を見るんですか?どうやってその善悪の判断を見るんですか?」
「いや、面接だとそれはちょっと。入ってからじゃないとわからないよなぁ」
「と言うことは、入社してから教えてあげて身につけてもらうことができるモノですか?」
「いやぁ、入ってから教えてあげられることにも限界があるよなぁ。善悪についてはそれ以前のような気もするし教えたこと無いし」
「ということは、教えてあげることはできないし見極めることもできないけど、大事なモノだから、モラルがあるかないかは運任せってことですか?」
「それだとちょっと・・・」
なんて感じに、「“それ”は絶対に大事なところだ」とみんなが思っているはずなのに、肝心要の“それ”については“みんな”のイメージがとてもボンヤリしていて「具体的で明確な“基準”になっていない」ということがよくあります。だけど、なぜか、“みんな”の中ではこの場合の“モラル”という言葉で「しっかりとイメージが具体的に共有できた」という認識になっている場合があったりするわけです。
もちろん、こうして実際にその“みんな”で「大事だよな」と認識しあってきたはずのモノについて、しっかりと対話をしてみると、かなり早い段階でその“大事なモノ”については「これまで、全くと言っていいほどに具体的な内容について話し合いをしてこなかった」ということをお互いに理解することができるわけです。
そして、このことが“みんな”で理解し合うことができると、そこからはじめて「ああ、ちゃんとみんなで具体的な“それ”について話し合って握り合うってことをしない限りは“大事なモノ”を大事にすることができないから、しっかりと具体的になるまで話しをしないとダメなんだ」ということが合意形成されるわけです。
逆に言えば、「“大事なモノ”について“みんな”で話し合いをしてこなかった」ということに気が付いていない場合には、極めてふんわりした抽象的な概念を投げ掛け合うだけで、その実は「大事なことが共有されていない」“空中戦”のような極めてボンヤリしたコミュニケーションが交わされています。
そんな「大事なことが共有されていないコミュニケーション」が行われている“場”においては、「それってつまりどういうこと?」という“問い”が投げかけられることがありません。
その“場”にいるメンバーみんなが“何らかの空気”を大事にするあまり“何となく”でコミュニケーションをとっている状態になっています。
もちろん、その状態が「必ずしも、どんな状況においても」“悪い”わけではありませんし、そういう“何となく”の状態が大切だったり重要だったりする場合もあるだろうとは思っています。
例えば、“おともだちどうし”の集まりで他愛も無い雑談をしている時にはこの“何となく”は大事でしょうし、それが無ければ“おともだちどうし”の間柄というのは維持形成できないかもしれません。何しろ、“おともだちどうし”の集まりは、多くの場合が“組織”ではないからです。
ここで言う「“組織”ではない」というのは、「①共通の目的の共有 ②円滑なコミュニケーション ③協力」という“組織の三要件”が必要無いから、という意味合いです。つまり、“おともだちどうし”の集まりは“組織”ではなくて“集団”です。
でも、僕たちが“仕事”で関わらせてもらうのは、「仕事をするために集まった人達で形成されている組織」であることが大前提です。ということは、“組織の三要件”は絶対に必要ですし“集団”であっては困るわけです。
“共通の目的の共有”がされていなければ「チームとして仕事を成し遂げる」のは難しいでしょうし、それをするためには“円滑なコミュニケーション”をとらなければ難しいでしょうし、そもそも“協力”をするためにも「目的が共有できていること」と「円滑なコミュニケーション」は必要不可欠になってくるので、この“三要件”というのは、言うなれば「切っても切り離せない一心同体である」と言えるわけです。だからこその、“組織の三要件”であって、この内のどれか一つでも欠けていることが明確であるならば、結局は「三要件のどれもが欠けている」のが実情です。そうであるなら、“その人の集まり”は、どれだけ立派な組織図があったとしても単なる“集団”になってしまいますし、更に「仲の良さ」が無かったりして“いがみあい”なんかが起きていたんだとすれば、“仲良しのおともだちどうし”にも敵わないような“集団”なのかもしれません。
もちろん“そんな集団”であったとすれば、「“組織”として仕事をして成果を上げる」なんていうのはとても難しいでしょうが、そうであったとしても「このメンバーで“仕事”をしていく必要がある」という状況なのであれば、まずは“おともだちどうし”なんかでは無いという状態になっていく必要があるわけです。
だから、まずはコミュニケーションの中で「わかったふり」をしないことから始めてみるのが重要です。
自分にとっても、みんなにとっても、会社にとっても、その先にいる顧客にとっても、社会にとっても絶対に必要不可欠になってくる「わかったふりをしないこと」。
そのためには、「それって、つまりどういうこと?」という“問い”をその“場”に投げかけること。
この単純な“問い”には、「組織になる」という力をその“場”に働きかけるとても強い力が秘められています。
そして、この“問い”を“場”に発するためには、「自分には“それ”がわかっていない」という自覚が必要になります。この自覚こそ、まさにソクラテスの言う“無知の知”なんじゃないかと思っています。
そして、この“無知の知”こそが、「現状のままではいけない。何とかしてこの現状を変えていく必要がある」という時に、必要になる究極の切り札なんじゃないかと思っています。
なぜなら、その「変える必要がある現状」を構成している自分も含めた周囲の人達が、もしもこの“無知の知”を発揮できていたとしたら、もう既に「それって、つまりどういうこと?」とか「なぜ、それをやるのか?(orやらないのか?)」といった“無知の知”から発する“問い”がそこかしこで投げかけられているはずですし、そんな動きがあるのであれば、それは既に“現状に対する問いかけ”なので、「もう既に、何らかの動きが起きている状態」が目の前にあるはずです。
でも、実際には「そうではない」からこそ「変える必要がある現状」が目の前に広がっているわけですし、つまりは、「現時点では未だ、“無知の知”が発揮されてはいない状態である」わけです。
その現状を変えていくために、実現したい未来を創り出すためにも、大昔からソクラテスが唱えていて今この瞬間の現代社会でもそのまま通用する“無知の知”を大いに活用して「自分には“それ”がわかっていない」ということを堂々と発信して「それって、つまりどういうこと?」という“問い”をその場に投げかけることで、現状を変えていくための最初の一歩を踏み出していくことが必要なのかもしれません。
勇気を持って「自分は無知である」という現実を認め、無知だからこそ発することができる無知じゃ無ければ発することができない「とても知的な“問い”」を発していくことができたとしたら、その時には、きっと、“無知の無知”だった頃とは比較にならないような変容が起きるんじゃないかと、これまで数々の変容を間近で見てきた身としては、そんな近い未来像を容易に想像できてなんだか少しワクワクしてきます。
あかね
株式会社プロタゴワークス
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
