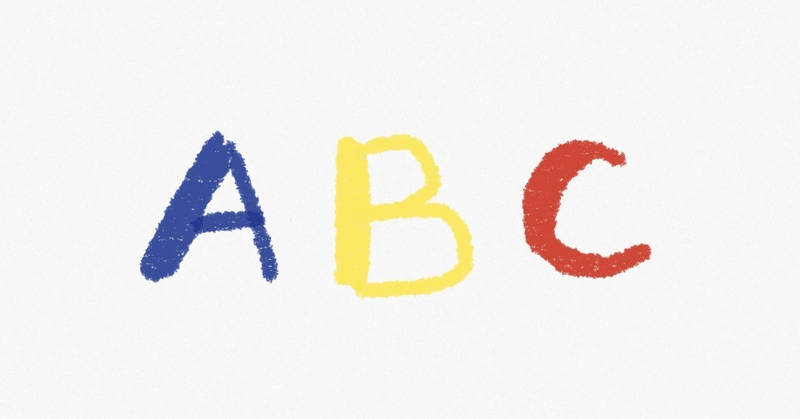
どこから見てもそれはそれ
こんにちは。
株式会社プロタゴワークスあかねです。
本を読んでいる時に、こんな例文が出てきました。
「AはBだ」
この例文を読んで、これまで全然思いだすことの無かった“昔の記憶”がいきなり蘇ってきました。
これからその“昔の記憶”について書く前に、まずは、その大前提になっているモノについて書いておこうと思います。
この“例文”に書いてあるのが、「あくまでも“例”であり、わかりやすく抽象化された例文である」というのは理解しているつもりです。なので、この“例文”があらわしているのは、例えば「僕は人間だ」という文章の“僕”に該当する部分を“A”として、“人間”に該当する部分を“B”ということを示している、ということであるのは理解しています。
これを大前提としておきながら、その昔、僕はこういう例文や記述に出会う度にこんな風に思っていたことを、ふと思いだしました。
「AはBじゃない。AはAで、BはBだ」と。
で、それが頭の中に浮かんでしまうと、そこから先に進むのに苦労するんです。というか、そこから先に進むのがとても大変になってしまっていました。
しかも、こういうことが起きるのは、大抵が“勉強”の中で起きるんです。
それも、“公式”のようなモノは大抵この“例文”のような抽象化がされた記述がメインだったりするわけです。
だけど、この部分で僕が“つまづいている”という事について、その当時の僕自身が理解することが出来ていませんでした。
なにしろ、今ここに書いたことは、あくまでも、冒頭で書いた“昔の記憶”が蘇ってきたことによって、“今現在の自分”によってようやく言語化されたのであって、その当時の僕がこれと同じことを言語化できていたわけではありませんでした。
だから、“勉強”をすることが必要とされた小中高の間で「自分が“こういうこと”に“つまづいている”」と、学校や塾の先生に発信することは出来ていなかったはずですし、そもそも、自分が発する「わからない」について誰かに受け止めてもらったことはありませんでしたし、当然、「わかりやすく解説をしてもらう」という経験もありませんでした。もちろん、自分でも「わからない」を誰かに解説することができないままだったので、「わからない」を解決することが出来ず、「わからない」まま通過していきました。
そんなことを、「AはBである」という例文を偶然目にしたことで、ふと思い出しました。
そして、この話を社内で仲間にしてみたんです。
そしたら、最初は「??この人、何を言っているのかわからないぞ??」という明らかなハテナがたくさん浮かんでいるのが見てとれたんですが、何度か解説をしたところ、「言っている言葉の意味はわかりました」という反応をしてもらうことができました。
そうしたら、仲間のその反応が僕にとってはとても新鮮に感じられたんです。
当初その“新鮮さ”が何なのか全くわかりませんでした。でも、いつもの如く、事務所を出て共用トイレに向かうための片道30Mの廊下を往復していた時に、その“新鮮さ”の正体がわかりました。
それは「嬉しい」という感情でした。
そこでもまた“昔の記憶”が蘇ったことで自分の感情に気付きました。
過去の僕が「AはBではない。AはAで、BはBだから」という“わからない状態”に陥ると、僕に対して教えてくれていた人達は、必ず決まって「これはこういうものだから」とか「これ覚えておいて」的な反応をされて通り過ぎました。時には、何回説明を受けたとしても僕が「わからない」という反応をするもんだから終いには「なんでわからないんだ!?」という“怒り”や“あきれ”といった反応をされていました。で、そうなると「全然わかんねーや」と僕も“怒り”や“あきれ”の感情が出て来て勉強を放棄するなんてことになっていたのを、とてもハッキリと思いだしました。
そんなことを思いだしたら、“今回の自分の体験&過去の自分の記憶”が「“対話”や“オープンダイアローグ”の効果」と結びついたんです。
僕のこの体験は、あくまでも「僕から見えている世界の中で起きている、僕にだけ見えている世界観」がベースになっているわけです。
ということは、当然ながら「僕以外の人の世界では、“こんなこと”は起きてない」わけなので、僕以外の人たちにとっては「AはBである」ということが、瞬時に誰にでも理解できて受け取れる“共通事項”であるわけで、“常識”とも言えるわけです。
でも、“僕にだけ見えている世界観”においては「AはBではない。AはAであり、BはBである」が“常識”なわけです。
そこで、僕以外の人たちが僕に向かって「お前何言ってるんだ?お前が見ているモノは間違っているし、おかしいぞ」と“怒り”や“呆れ”とともに言われてきたのがこれまでの状態でした。それに対して僕も“怒り”や“呆れ”を感じていました。「お前らこそ何言ってんだ?」と。
それが、今現在では「確かに、あなたの見方をすれば、AはBではないですね」と“受け止め”てもらえたことで、僕の中には「嬉しい」という気持ちが湧いてきたんです。「ようやくわかってもらえたんだ!自分の話が通じることがあるんだ」と。当然、“怒り”や“呆れ”を感じる事はありませんし、僕に対して過去向けられてきた“否定”や“攻撃”に対しての“反撃”をしようと思う気持ちも全く生まれてきませんでした。
そんな体験をしたことで、「これこそが、“対話”や“オープンダイアローグ”の中で「最も重要なことだ」と僕が感じている「相手を否定しない」の意味であり、「否定しない」ことによって生まれる効果なんだな」ということが本当の意味で理解できました。
“対話”によって「否定しない」ということが本当に実現されると、必然的に、「あたかも、相手の世界に立って世の中を眺める」ということも同時に実現され、それによって「受容と共感」も実現されるんだというのを、自分の体験を通して味わうことができました。
きっと、僕の言う「AはBではない。AはAで、BはBだから」というのは、僕以外の人からしたら“意味のわからない妄言の類”として受け止められることがほとんどでしょうし、だからこそ、過去に「何言ってるの?」とか「わけわかんねーよ」なんて言葉を向けられることが多かったんだろうなと思うわけです。
でも、僕にとってはそれが普通の世界観であり、僕から見えている普段の世界なわけけですから、それに対して“否定”をされるということは“攻撃”をされているのと同じ意味になるわけです。だから、僕も自然に“反撃”の姿勢を取りますし、売り言葉に買い言葉も出てしまったり、「自分が何かを言っても否定されるから何も言わないようにしよう」となるわけです。つまり、「心理的安全性の存在しない状態」が自然に出来上がっていくのも“否定”によって形成されていくわけです。
そんな、誰にとっても「役に立たない状態」が、「否定をしない」ということだけで、「受容と共感」がうまれ、「相手の世界に立つ」がうまれ、「心理的安全性」がうまれるわけです。
そんなに役に立つことをするために必要なのは、まずこれが必要不可欠なんだなと、仲間の実践によってあらためてわかりました。
それは、「“相手の話をただ聴く”という行為が最初の一歩」だということです。
なんて、ここまで書いたことを振り返ってみると、僕達がやっている他者支援の仕事(カウンセラーとかキャリコンなど)にとっては“途轍もなく当たり前の話”です。
だけど、そんな当たり前のことも“自分が当事者なる体験”をすることで、それまでの自分よりも更に色濃く認識することができるんだというのを、これまた当たり前ですが再認識できるんです。
そんな、“以前の当たり前”と“再認識した当たり前”は、文字や言葉にすると「傾聴大事」なんてもので終わりになってしまうんですが、でもこれは全く同じ意味では無いわけです。
“以前の当たり前”をAとするならば、“再認識した当たり前”はBとなります。
となると「AはBだ」と言われても納得できないと感じます。
やっぱり、「AはBではない。AはAであり、BはBだから」なんて僕は思うんです。
あかね
株式会社プロタゴワークス
https://www.protagoworks.com/
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
