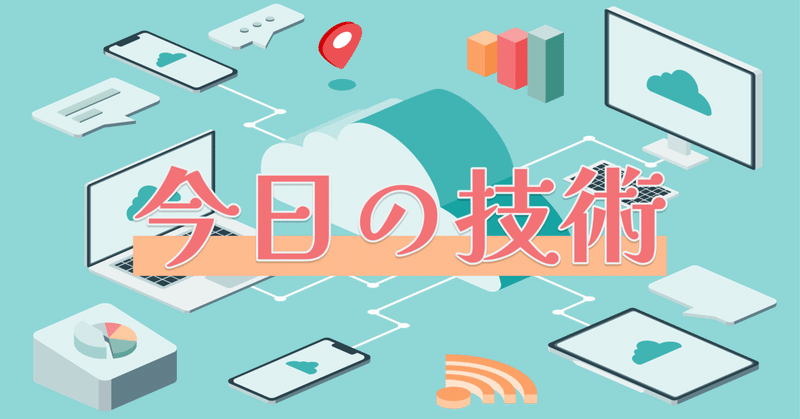
サンプリングってなあに?
サンプリングとは?
音は本来すべての時間で値をとる連続値のアナログ信号だが、コンピュータで処理しようと思うと離散的なディジタル信号として処理しなければならない
これをサンプリングと呼ぶ
またアナログをディジタルに変換するということでA-D変換とも呼ばれる

逆にスピーカーから音を鳴らすときはディジタル信号をアナログ信号に戻さないといけないが、これをD-A変換と呼ぶ
サンプリングは標本化周期と呼ばれる一定の時間間隔でアナログ信号を読み取る標本化と、標本化した値を数値データとして記録する量子化からなる
標本化
標本化周期と呼ばれる一定間隔でアナログ信号を読み取ること
標本化の性能は標本化周期や、その逆数をとって1秒間に何回標本化するかを表す標本化周波数によって決まる
標本化周波数が大きいほど元のアナログ波形を忠実に表せるということ
元の音に含まれるサイン波の周波数を表現できるのは標本化周波数の1/2までという証明がされており、これを標本化定理という
例えばCDの標本化周波数は44100Hzなので、半分の22050Hzまでの音であれば再現できる(逆に言うとそれ以上の高さの音は表現できない)
とはいえ人の可聴域は20~20000Hzなのでこれで十分である
サンプリング時の標本化周波数と再生時の標本化周波数の値を揃えないと音がおかしく聞こえるので注意
量子化
標本化は時間軸方向に離散化する処理だが、量子化は振幅軸方向に離散化する処理
量子化の性能は音の大きさを何段階に切るのかというステップ数や、その2を底として対数をとった量子化精度を用いる
量子化精度の単位はbitである
ちなみにCDの場合16bit=65536段階のステップで量子化されている
コンピュータでは分かりやすさのため、この段階を-1~1の実数値として扱う
このとき振幅が-1~1の範囲を超えているとオーバーフローが発生して波形が大きくゆがむことになる
そうならないよう規定の範囲で打ち切るクリッピングが用いられるがこれはいわゆる「割れた」音になる
そもそも振幅が範囲を超えないように小さく取るのが最善策だが、小さくし過ぎると四捨五入したときにディティールが失われるので注意
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!

