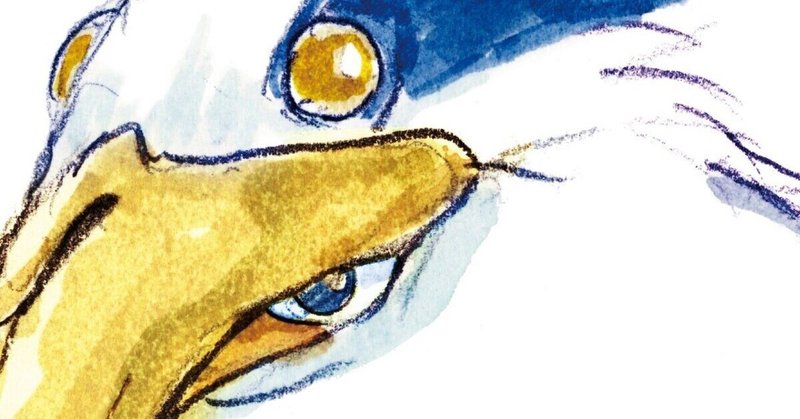
君たちはどう生きるか
観てきました。
といっても直近ではなくて、8/8に見に行ったので、もう2ヶ月ちかく経つ。いっしょに観に行った恋人を除き、観た直後は、ひとの感想を見たり読んだりしたくないなーという気持ちだったので、自分のなかで反芻するための時間がかかってる。いまも消化しきれたとかはぜんぜんない。
とにかく観た。いまからその話をします。がっつりネタバレもします。
これは「君たちはどう生きるか」の感想というより「『君たちはどう生きるか』をとおしてただ語りたいように語るわたしとジブリ」の話です。
どこがよかった、どこがすごかった、とかは観ている最中とくになくて、でも、ラストの塔が崩れ去って、月日が流れ東京に戻る日、家族に呼ばれて「はあい」と返事をして部屋を出ていく眞人、扉を閉められ無人になる部屋、エンディング、の流れにかけて、なんだか泣けてしかたがなかった。
主語のデカい話をすると、いまのアラサー世代ってジブリとともに幼少期から10代を過ごしてきたひとがめちゃくちゃ多いとおもうんですよね。世代ど真ん中だもの。すくなくともわたしはそう。はじめて映画館で観た映画は「もののけ姫」だったし、ちいさいころから何度もくりかえしジブリ作品を観ていた。
10代の半ばごろ、ひさしぶりにジブリ映画を観たときの、感動と衝撃をいまでもおぼえてる。当時の新作映画への感動じゃなくて、「意味がわかる」とおもったことへの感動だった。あきずに何度も観ていた映像に、ちいさいころは意味のわからなかったキャラクターたちの会話に、どれも意味があること、それがわかることがすごくうれしかったのをおぼえてる。
当時2歳かそこらだったわたしが映画館で「もののけ姫」をたのしむには幼すぎたように、「君たちはどう生きるか」も、子どもむけのエンタメではないとおもう。だからって、大人むきだよね、というのともちょっと、微妙にちがって、観終わったときにわたしのあたまに浮かんだのは、「ジブリを見て育ってきた子どもだった、わたしたちのための映画だ」という言葉だった。これこそめちゃくちゃ主語がデカいね。エンディングの米津玄師に当てられたのかもしれない。米津玄師ってそういうところあるから。でもそうおもった。
だって、最後に眞人が部屋から出て行ったとき、さみしくなかった。
だれの手も届かない上空に浮かぶラピュタを観ながら聴く君をのせても、デッキブラシに乗って遠ざかっていくキキも、腐海の底でナウシカの帽子の隣に生えたちいさな芽も、芽吹いた倒木の上で首を振るコダマも、聴くたび、観るたびに、感動や爽快感よりさみしさが勝った。没頭していたはずの物語に置いていかれるような気がした。
わたしは「ゲド戦記」以降のジブリ作品、ぜんぜん好きじゃないです。終わり方もあんまりおぼえてない。だから結局、今作でわたしが泣いたのは、それ以前のジブリ作品への思い入れゆえだ。こじつけかもしれなくても、どうしても、今作をとおして過去のジブリ作品を見てしまう。
でも、決定的にいままでの作品とちがうと、わたしがそう感じたのは、眞人とヒミは「あの世界の当事者」になれなかったこと。
ジブリ作品の少年少女たちは、なにかを終わらせるためになにかを手放す選択をする。その選択を迫られたときの葛藤はほぼなくて、はじめから一本道のような当然の態度で手放すことを選ぶ。
ナウシカが争いを終わらせ王蟲の子を返すために自分の命を手放そうとしたように、パズーとシータが心ない略奪者からラピュタを解放するために滅びの呪文を唱えたように、アシタカとサンがシシガミを止めるために我が身を顧みずに首を返そうとしたように、終わらせるために自ら差し出してきたなかで、眞人とヒミは非現実世界で出会った少年少女でありながら、ロマンスには至りようのない現実世界での実の親子であり、物語の冒頭時点でふたりが死別することはもう決まっていて、さらに「危機的状況にある異世界の創造主とおなじ血を引く選ばれた人間」でありながら、その特別性を活かして異世界を救うことも終わらせることもできなかった。
積み木を崩して世界を終わらせたのは「選ばれた人間」ではなく、勇敢で愚かな第三者の短気だった。
生まれによる特別性、という意味ではインコの王は部外者だけど、あの世界の住人という意味では、眞人よりもよっぽど当事者だった。
いま、当事者、と書きながらおもいついたけど、「自分こそが自分の人生の当事者だと自覚へ至る」ことを描いた話だったのかなあ。
眞人が受け入れようとしなかったもののひとつが、夏子さんだった。夏子さんのことを尋ねられるたびに「父さんの好きなひと」という呼び方をする。
もうひとつ、終盤で、眞人が己の罪だと認めた怪我。あの怪我は、望まない環境=学校から逃避するために、眞人が偽装した外付けの理由と演出だ。自分の口で「行きたくない」と言うのではなく、こんな怪我を負わせられた(実際はそう見せかけた)のだから行かなくても構わない、とおとなのほうから言わせるための手段だった。
眞人はずっと、置かれた環境の居心地が悪くて、納得がいかなくて、それこそ部外者のような心地だったんだろうね。
戦時中にもかかわらず立派な家があり、食べるものに困らず、きれいな服を着て、金まわりのいい親がいる。はたから見れば、そして「火垂るの墓」の兄妹の最期をしっているジブリ作品を観てきた鑑賞者から見ても、恵まれすぎなほど恵まれている。
でも、劇中の眞人視点から見た境遇は、実の母を戦火に焼かれ死に目にも遺体にも会えず、親の都合で住み慣れた土地を離れ、父の再婚相手はすでに子どもを身籠っており、越した先の屋敷は老人ばかりで気の許せる相手も歳のちかい友人もおらず、転校先の学校では手荒く拒絶されている。
そんな環境のなかに望まず放りこまれた眞人は、夏子さんが居ない家に帰るわけにはいかなかった。眞人が夏子さんをどうおもっているかは重要じゃない。それは眞人自身も自覚していた。あくまで夏子さんは眞人の父の好きなひとで、眞人は父の庇護下にある子どもだから、父のいる場所/現実世界へ帰るにには、夏子さんの安否は欠かせない必要条件だった。
現実世界で自分の人生の当事者として生きようとしていない者が、非現実世界では世界の命運を握る当事者になれます、なんて都合が良すぎるもんね。
眞人が夏子さんを「母さん」と呼んだのは、現実世界でいっしょに暮らしていく家族として受け入れたから。
最後の扉のまえで、ヒミがいずれ炎に焼かれて死んでしまうとわかっていながら、ヒミの「素敵じゃないか(このセリフのあとに、君を産めるなんて、とつづいた気がするけどちょっとうろ覚え)」という言葉を聞いて手を離してそれぞれの時間にもどっていったのは、ヒミがヒミの人生を生き、眞人を産んで、産まれた眞人が生きていくため。
ポルコが見た高い空に浮かぶ飛行艇乗りたちの墓場のような、船の幻覚が漂う海の先にあるものは、千尋の迷い込んだ約束ごとを違えたときの破滅と隣り合った世界よりも死の匂い色濃い世界で、そこへ至る森へとつづくトンネルを先導してくれるのはトトロではなく気味の悪い青鷺で、生きて元の世界へ帰るためにひとりで草原を駆け降りていく千尋が振りむけなかった異世界を、眞人は母/夏子さんと並んで振り返り、崩れ落ちていく塔のおわりを見つめる。
眞人は「非現実世界から現実世界に帰る」ことを選んで、やっと自分の世界/人生の当事者になれたんだとおもう。手放すのではなく、受け入れたから、眞人は母/ヒミと別れることができたし、母/夏子さんと戻ってこられた。
正直に言うと、タイトルを見たときに「やかましいな」とおもったよ。自分より数十年ながく生きてるはるか歳上の、しかも一分野における巨匠と呼ばれるひとが、遺作になるかもしれない作品タイトルにこんなん持ってきたら「うるさっ」ってなるでしょ。わたしはなる性根なんだよ。由来になった同名の小説は数年前に大学の授業で読んだけど、あんまり内容をおぼえてない。たぶん、当時も「嫌いじゃないけどぜんぜん好きではないしでもなんか嫌っていうかなんていうかうるせえなっていうか……」とかぐだぐだおもってた。
宮崎駿が言うならゆるせるんだよ、なんてこともべつにない。むしろ宮崎駿が言うから「やかましいな」とおもうまである。これだけだとほぼただのディスりだな。
ちょっとむかつくし、うるさがってしまうところもあるけど、嫌いとはぜったいにちがう。なんて言ったらいいんだろう。なんて言ったらいいんだろう、って映画を観終わってからずっとかんがえてる。
さっきさんざん「当事者」の話をしたけど、わたしのこのかんがえ自体が、タイトルにだいぶ引っ張られてるな。
宮崎駿の遺品になる映画かもしれない。そうおもうと、どうしても今作の映像のひとつひとつにこれまでの宮崎駿の作品を、宮崎駿の人生を、宮崎駿の意思を見出そうとしてしまう。おなじくらい、こういう見方はときにすごくつまらない見方なんだろうな、ともおもってるのに。
宮崎駿のほうこそ「ごちゃごちゃ言ってねえで観ろ!!」とおもってるかもしれんね。いやしらんけどね。
わたしはたくさんの創作物によって心動かされたきたし、生かされてきた。その原点のひとつは、ぜったいにジブリだ。
観るまえは「変に自己啓発的なものになるくらいなら、いっそのこと最後にめちゃくちゃやりたい放題やってジブリを破壊してくれ宮崎駿」とおもってた。良くも悪くもそうなった部分と、ならなかった部分のある映画だった。
この先、宮崎駿がまた引退宣言しながら新作を作ろうと、スタジオジブリとしての後継者がジブリの名の下に新作を作ろうと、たぶん、わたしの大好きなかつてのジブリ作品たちを越えることはない。それは絶望や悲観じゃなくて、強いて言うなら、わたしがおとなになったから、そういうもんなんだとおもう。
眞人が部屋を出ていくときにさみしくなかったのに泣いたのは、わたしのなかで、ジブリという作品のシリーズに対して、ひとつの区切りをつけることができたからだ。これは見限りや失望とはちがう。ぜったいに、まったくちがう。
スタジオジブリとしてジブリはつづいていくだろうし、新しいジブリ作品もきっと観るだろう。
でもわたしにとってはずっと、宮崎駿の作るアニメーション映画こそがジブリだ。これがわたしのつけた区切りの名前と理由。
これからもこれまでとおなじように、わたしは金曜ロードショーでジブリを観て、漫画版のナシカを読んで、やっぱり漫画版ナウシカも庵野あたりががんばってアニメ映画化してくれないかな〜、とおもいながら、やっぱりジブリってすごいよな、おもしろいよな、って言う。
おとなになったわたしにとって、ジブリはずっとそういうものなんだとおもう。
とかそれっぽく締めくくろうとしたけど、これで宮崎駿がまた新作出したらめちゃくちゃ笑っちゃうな。笑いながら観に行って、また好き勝手にごちゃごちゃかんがえながら泣くとおもうよ。
ここまで読んでくださりありがとうございます。 いただいたサポート代は映画代と本の購入代につかわせていただきます。
