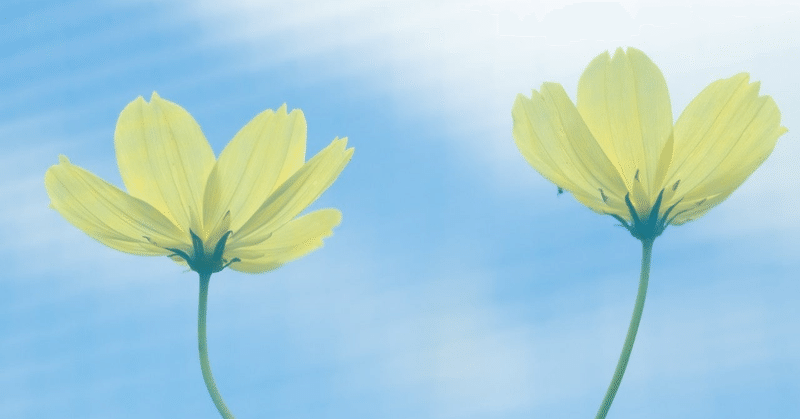
ショートショート『寂しがりふたり』
…これは、人生で最大の失態だ。俺は仰向けに寝転んで真っ白い天井を見上げたまま、深い深いため息をついた。
ここは病院のベッドの上、しかも手首には点滴の管が繋がれ、ついさっき看護師さんにも「しばらく安静」と言い渡されたばかりだ。
…ストレス性の胃腸炎。まさか入院までする羽目になるとは思いもしなかったが、どうやら自分で思っていた以上に、いろんなことがストレスとして積み重なっていたらしい。
言われてみれば、思い当たる節は正直、無いではなかった。恩師との死別、繰り返される目眩や頭痛、悪夢、仕事でのトラブル、職場の上手くいかない人間関係……。就職して二年目、一年目のときよりもはるかに俺の心はいろんなものに揺り動かされ、圧し潰されていたのだろう。
つい最近の仕事のミスも、いつも通りの俺だったなら、もっと上手く挽回できたという自信はあった。一度同僚に「最近元気が無いように見える」というようなことを言われたが、そう指摘されたところで素直に助けを求められる性格ではなかったし、睡眠さえ取っていれば次第に回復するだろうとタカをくくっていた。
…平気だと思っていた。平気じゃないかもと思った時ももちろんあったが、そういうときはいつも、現在同棲している恋人の雫が隣で支えてくれて、あるいは後ろから背中を押してくれて、またあるいは上から腕を引っ張ってくれた。
ところが俺は、自分が思っていた以上に弱かったらしい。家に帰るなり雫に体の怠さを訴えたとき、俺の顔色を見た彼女は何も言わず自分の額で俺の額の温度を測り、有無を言わさぬ迅速さですぐに俺を病院に連れてきてくれた。
それから 1 週間が経過するのだが、俺は病気で具合が悪いとか以前に、雫に会えないのが一番しんどかった。何しろ今は感染症のせいで面会が禁止されていて、彼女とコンタクトが取れるのは電話のみ。雫は俺からの着信には必ず出てくれるが、まさか話をしたいというだけの電話で仕事の妨害をするわけにはいかない。ベッドで横になりながら、俺は大袈裟なんかじゃなく本当に、ほとんど雫のことばかり考えていた。一目会いたかった。会ってその目で見つめてほしかった。電話越しじゃない、生の雫の声が聞きたかった。触れなくてもいい、せめて姿だけでも見たい。自分が雫の相棒として傍にいられない今、彼女は誰と何をしているのか、どんな話をしているのか、全てを知りたかった。
やがて、盗聴器でも付けていれば…などと考え始め、俺は自嘲の笑いを洩らした。相手が好きすぎるあまりストーカーと化してしまう人たちの気持ちが理解できる気がした。その人が好きで、ものすごく好きで、その全てを知りたいと思う。見たいと思う。同じように相手にも自分を想ってほしいと願ってしまう。
俺にとって雫は、今やそれほど大きな存在だった。会えなくなって苦しいほどに実感したのだ。
俺には雫が必要だ。そして、彼女にとっても、俺は必要な存在であってほしかった。
【おはよう、今日の 10 時に退院できるよ!】
朝 8 時に、雫に送った LINEメッセージ。ちょうど彼女は夜勤明けで、普段なら睡眠時間に当てている時間のはずだった。
雫にはちゃんと寝てほしいし、迎えに来て欲しくて送ったメッセージではない。恋人として、お知らせまでに報告しただけ。寝て起きてからメッセージを見て、会いに来てくれればそれでいい。だから電話は掛けなかった。
ところが、病院から出た途端、小走りでこちらに向かってくる人影が見え、それが誰だかすぐに分かった俺は思わず立ち止まった。雫だった。もうそれだけで俺は泣きそうになり、無理矢理明るい笑顔を作った。
「…あれ? 雫、何してんの? さっきまで仕事だったんだろ、寝てる時間じゃん」
「……大丈夫なの?」
「え?」
「大丈夫なの、もう? 少しでも無理してたら怒るよ」
俺の問いかけには答えず、雫は真剣な顔でそんなふうに言った。心配してくれているのが分かって嬉しかったが、ちゃんと問い掛けに応えてほしかった俺はワガママを通した。
「…雫、何してんの? こんな時間にこんなとこで」
「……」
意地悪をして、彼女と同じことをやり返した。
問いかけに答えずに質問する。
焦っているときや、もっと気になることに気を取られているときに雫がやりがちなこの振舞いを、別に気に入らないわけではなかったが、今回はいつも通りにとはいかなかった。すると彼女は察してくれたようで、少しの間黙ったあと、きちんと答え直してくれた。
「…晶を迎えに来たの」
「……何時まで仕事してたの?」
「…9 時」
「寝てて良かったのに」
「………」
雫は「意地悪を言わないで」、という顔をした。確かに、自分でも意地悪だと思った。そしてずるいとも思った。…本当は、こうやって彼女が迎えに来てくれるのを期待してLINEを送ったのだ。
「……俺に会えない間…寂しかった?」
「…………」
雫は少しだけ上がった息を整えるように、しばらくは何も言わず俺の顔を見つめていた。
「……晶は?」
「…ほら、また聞き返す。聞いてんの俺なんだけど?」
笑いながら応じると、雫は下を向き、短いため息を吐いた。そしてばっと顔を上げたかと思うと急に俺との距離を詰め、胸の辺りに頭を寄りかからせてきた。
「……寂しかったに決まってるでしょ、…バカ」
俺は何も言葉を返せず、黙って雫を見下ろした。これ以上、意地悪をする必要も、ワガママを言う理由も無かった。俺は一瞬、彼女を抱きしめようと両手を上げかけ、考え直して片手を握るだけに留めた。雫の行動はきっと、公衆の面前でできる彼女の精いっぱいなのだ。
「…俺も。」
雫が手をぎゅっと握り返してきた。ほとんど痛いくらいだった。俺は歓喜の波を少しでも抑えようと唇を噛んだ。…別に、無理に雫に返事をしてもらう必要は無かったのだ。夜勤明けに寝ずに迎えに来てくれた。自分のことより俺のことを心配してくれた。もうそれだけで、彼女の気持ちが俺と同じだということは分かりきっていたのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
