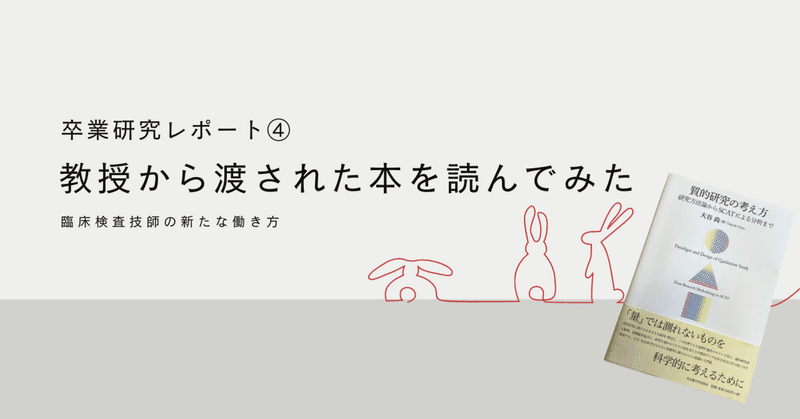
教授から渡された本を読んでみた
インタビュー調査に向けて
今回の研究では、いくつかの調査方法の中でインタビュー調査を行います。
これまで出会った先生方や、臨床検査技師の方々に直接インタビューという形でお話を聞いて、それを文字に起こして分析する予定です。
(ちなみに、早速明日インタビューをします、わくわく)
ただお話を聞いて「わ〜聞けてよかったな〜」で終わるわけにはいかないので、データ分析をしなきゃいけないですよね
そこで、今回の分析のために、教授に「インタビューの前に読んどくといいよ/読んどいて」と渡された本がこちら。
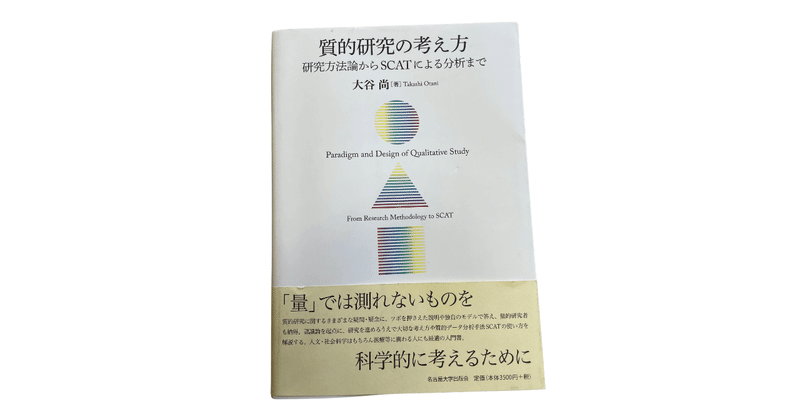
若干擦れてますね…😅
(持ってっただけ、ということも多々あった笑)
既に退官されたそうですが、名古屋大学の先生で、私の知り合いの名大生も授業を受けたことがあるとのこと。とりあえず開いてみました。
読みきるまでの時間、いつもの3倍
本を読むのはすごく好きではあるものの、それは小説に限った話で😅
いわゆる説明文?みたいなのはそこまで得意ではないのです。

特に推理小説が大好きで読み漁っていました。
〇〇的、〇〇性とか出てくるとうっ…てなるし、
タイトルから早速"質的"が登場してるんですよね笑
カタカナが出てくるのも苦手です。イデオロギーが…とか、モラトリアムを…とか言われると、おおおお願いだから分かりやすい日本語で頼む…!!って気持ちになります(わかってくれる人がきっといると信じたい笑)
言葉の意味がすんなり理解できずにつっかえながら読む感じがどうも苦手です。
物語文だと、ある程度物語の流れが捉えられたらいいし、ざざーっと流し読みできるんですけど、今回は特にそういうわけにはいかないのです。
内容を理解しながら、実際自分が分析するときのことも考えながら読まないといけないので、いつも以上に時間がかかりました。
読んでみて感じたこと
感想としては、「SCAT分析楽しそう。」です。
やってみたらきっと大変なんだとは思いますが、ちょっとまだ楽観視させていてください。笑
著者の大谷先生が本の中で、普段から"言語化をすること"が大切だとおっしゃっていたことが印象に残りました。
これは2022年から、私が頻繁にやっていたことでした。
考えたこと、感じたことを言葉にする
どこかに記録しておいたり、誰かに伝えたり。
自分がメンターとして中高生たちと一緒にやっていたことであり、自分自身も色んな人に言語化したものを伝える機会が有難いことにたくさんありました。そしてそれが"好きだな"とも感じていました。
言語化し、伝えること。
ちょっと研究の話から遠ざかってますが、記録のために書いてみます。個人的な記録なので、なんでもありです笑
2022年、色んな人に会って、色んな経験をする中で「自分の思いや考えを伝える」重要性を身をもって実感しました。

一回一回貴重だなと思うようになりました!
話すつもりはなかったけど、流れで話をする中で自分の思いや考えを伝えたことで、相手がその思いに共感してくれて思いもよらなかった一歩を踏み出すことができたり、素敵な方と繋げていただいたり、
もしかしたらもうこれが最後に伝える機会になるかもしれない大事な人に思いを伝えて、思い残すことなく「またね」と言えたり
そういう貴重な経験を積み重ねる中で、言語化するって大事だな、いいな好きだなって思うようになりました。このnote投稿もそうです。
拙い文章ではあるけれど、自分の思いや考えたことを残しておくことで、自分にとっても振り返るための材料になるし、反応をくれる方と新たなコミュニケーションが生まれて何かが始まることもあります。

めちゃくちゃ恥ずかしいけどちょっと嬉しかったりします笑
当たり前のように感じて考えることを大事にしたいし、言語化して伝えたいな、と思います。
あー、なんか本当に全然違う話になっちゃった笑
話を戻して
インタビューの内容を文字に起こして、いい感じに区切って、重要なワードを抜き出して言い換えて…みたいな結構重めな作業にはなりそうですが、たくさんの方の色んな思いが聞けると思うとすごくワクワクします。
ただの卒業研究ではなく、自分の進路に直接関わってくるから余計に前のめりでできるし、地域の病院にも訪問できるので、楽しい数ヶ月になりそうです。なるといいなあ笑笑
バスの中でパソコンうっているからそろそろ酔いそう
また、書きます!
読んでくださってありがとうございました✨
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
