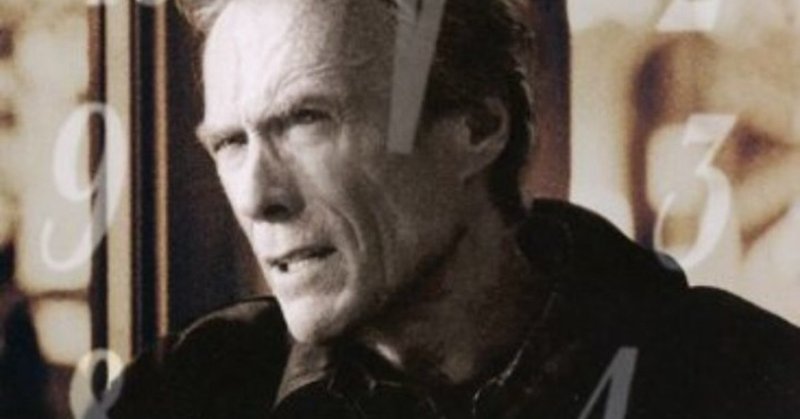記事一覧
「芳華-Youth-」
青春を諦めない映画だ。
戦争という祝祭、青春は大合唱の後の静けさをもって幕を閉じる。
青春を引き延ばそうとすればするほど、彼らは傷ついていく。
腕を失う、心は壊れる。
それなのに、私たちは青春を諦めない。
あの一瞬の輝きを永遠にと思うから、私たちは映画をつくるのだ。
青春という純粋無垢な時間に突如異物として入り込む、血や泥や焼けただれた肌、食い込む銃弾。
青春にドロドロの赤黒い血色はいらない
「勝手にしやがれ 強奪計画」
純粋な映画というのは、純粋な行為と同義でそれなら純粋な行為とはなんだという話になるのだろうが、純粋な行為とは自身が何故それをするのか知らない運動であり、第三者から見てもその人が何故それをするのかわからない運動である。
映画は純粋な行為が、そのままアクションとして提示されてさえすれば良いのだ。
物語の辻褄や、登場人物の心理などはどうでもいい。
この映画で「何故それをするのか知らない」ということが画面
「セーラー服と機関銃」
長回しは鑑賞者を発狂させる。
その圧倒的な情報量によって。
同時多発的に何かがそこかしこで起こり、スクリーン内では何もかも平等で、悲しみや喜びも、生や死も平等で、血などただの赤い絵の具に過ぎない。
機関銃が火を噴く時のスローモーション、「カイカン」という音と薬師丸ひろ子の開ききった瞳孔がスクリーン前景にせり上がってきてゾッとする。
紛れも無い暴力だと思った。
長回しのゆったりした時間の流れを遮って
「トゥルークライム」
物語という意味を映画に付与されることを、極端なまでに嫌がるのがクリントイーストウッドなのだと思う。
一見、黒人差別を取り上げた社会派映画のように見えるが、そのようにこの映画に意味を付与した瞬間にこの映画は映画ではなくなってしまう。
主人公は物語という意味から逃れるように、自分の「鼻」だけを頼りに行動していく。
彼の「鼻」が突き止めた「ホントウ」のことは一切の物語を拒否している。
差別される哀れな黒