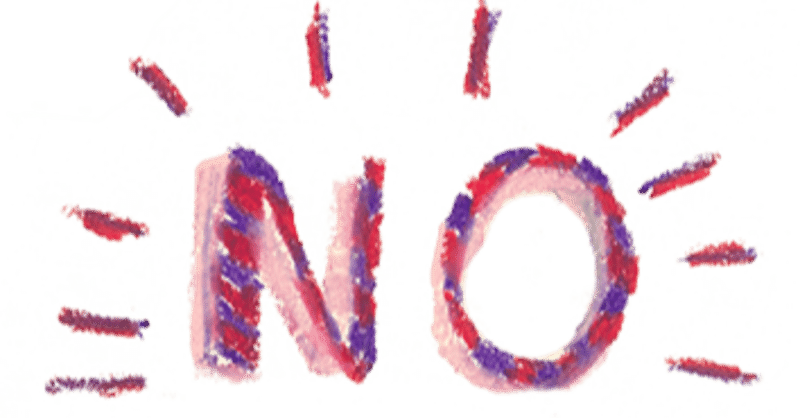
承認は必要か
以前仕事で経費精算などの稟議・決済・承認プロセスの見直しを行なっていたのですが、そのときあるマネージャが「そもそも承認なんてないほうがいいよね」と発言しました。確かに承認がなければ意思決定がスムーズに進んでよさそうだが本当にそんなことは可能か…不正が多発するのではないか、責任は誰が取るのか…。一見非現実的にも見えますが、同時にその世界に魅力を感じました。そこで、承認を排除した企業・組織について書かれている2つの本を参考に承認を排除することについて調べたので、シェアします。
承認を必要としない企業
参考にした書籍は、ネットフリックスの社内カルチャーについて書かれたNO RULESと、現代のいくつかの企業に見られるこれまでとは違う組織の在り方について書かれたティール組織です。これらに登場する企業・組織は程度の差こそあれ、承認を必要とせず、意思決定を行うことができるようです。
信頼か統制か
これらの組織に共通しているのは、統制は従業員への不信を伝えるサインであり、創造性やモチベーションを奪うものとして考えられているということです。そして、従業員たちの良識を信じて自由を与えることで、従業員たちはよりその自由を維持するように、自分たちが十分信頼に足るということを証明するような責任ある行動をすると考えています。
信頼と統制の問題はXY理論とも呼ばれているようです。こちらにわかりやすい定義がありました。
X理論とは「人間は生来怠け者で、強制されたり命令されなければ仕事をしない」とする、性悪説にもとづいた理論です。
Y理論とは「人間は生まれながらに嫌いということはなく、条件次第で責任を受け入れ、自ら進んで責任を取ろうとする」とした、性善説にもとづいた理論です。
一般的な企業・組織においてはX理論に、ネットフリックスやティール組織ではY理論に基づいていることがわかります。
とはいって管理がないと破綻するんじゃない?
とはいえ、X理論は実際にうまくいくのでしょうか。実は上述の企業は手放しで性善説を信じているわけではありません。従業員の良識を信じつつも、ルールではなく、コンテキストやプロセスを導入することで回避しています。
ネットフリックスでは、ルールの代わりにコンテキスト(条件)というものを設定しているようです。例えば経費の承認を無くした際には、初めは必要以上に経費を使うものが現れたそうですが、試行錯誤の結果「ネットフリックスの利益を最優先にする」というコンテキスト(条件)を与えることで、個々の従業員が自らの判断で適正に経費を使うようになったといいます。
また、多くのティール組織では、意思決定の際に承認を取る必要はないが、関係者に助言を求めなければならないという「助言プロセス」が存在しているといいます。場合によってはCEOに助言を求めることもあるそうです。ただし、これは承認やコンセンサスを取ることとは違い、助言を全て聞き入れる必要はありません、最終的には個人の判断に委ねられます。
これらに共通しているのは、コンテキスとやプロセスといった枠組みのみを規定し、個別の事象についてはその枠組みの中での従業員の判断に委ねるという点です。そして、それれらが結果的に統制よりもより正しい判断になると信じられています。
もう一点知っておくべき点は、自由を与えると同時に、相応の責任を負わせているということです。ネットフリックスでは内部監査チームが経費精算の一部をチェックし、万が一不正があれば不正をした者は即解雇されることになっているそうです。また、ティール組織に登場するFAVIという会社では、トイレットペーパーであっても盗んだ場合は解雇されることになっているそうです。
優秀な人だけが集まっていないと無理なんじゃない?
ここで一つ疑問が浮かびます。信頼>統制が成り立つためには、優秀な人だけが集まっているとか、特別な条件があるのではないか?ということです。これに対しては、ネットフリックスとティール組織は異なる回答になるでしょう。
まず、ネットフリックスであればYESと答えるでしょう。ネットフリックスでは、平凡な人材2人よりもスーパースターを1人雇うことを優先しているそうです。このようにして優秀な人材だけを集めることで、従業員が責任のある行動をとってくれると期待できる、とあります。
一方で、ティール組織では、全社共通の雇用方針については特に言及されておらず、特別優秀な人間だけを集めているということはないようです。むしろ、人事などが集中的に採用を行うのではなく、各チームが自らの判断で求人を出し、採用することを許している企業もあるといいます。ティール組織においては、この点はあまり重視されていないようです。また、ティール組織では医療、製造業など様々な業界、また従業員規模が数千をを超える大規模な組織でもこの仕組みが成り立つことを確かめています。
ここからは私の推察ですが、X理論の文化がうまく働くためには、優秀な人材が集まっているかどうかやその企業・組織の規模に関わらず、自由と引き換えに責任を負うことを望む人だけで構成されていることが重要ではないかと思います。そうでない人にとっては自由と信頼のカルチャーはストレスがたまり居心地の悪いものであるため、自然と辞めていくでしょう。実際にティール組織の中にも、従来型の統制の組織から自由と信頼の組織に変わったことで、適応できず辞めいった人の話が書かれています。
夢から覚めて
承認を排除した実在の企業の例を見て、自由と責任のカルチャーを醸成することで、承認を無くすことは十分に可能だろうと思いました。しかし、私のプロジェクトでは仮に承認を排除する場合、下記のような現実的な課題がありました。
・自由と責任のカルチャーのない組織で承認だけを無くしてもうまくいかず、全社的なカルチャーを変える必要がある
・外部監査(ISMS、PCIDSS、JSOX)などの基準を満たすためには承認が必要
結果として、下記の方針に従い可能な限り無駄な承認を減らしていこうということになりました。
・承認観点を明確にし、システムによるバリデーションや下位承認者によってその観点が確認できる場合は権限を委譲することで、上位承認者による承認を最小限に減らす
夢から覚める結果となってしまいましたが、「承認」というものについて考え直すいい機会となりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
