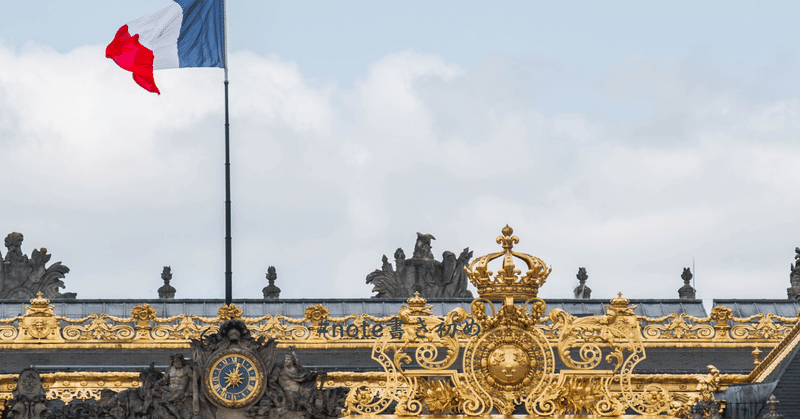
(不完全稿)ヒトのいらない世界~経済と社会の「資本化」~
この記事は不完全ではありますが、とりあえず公開します。できる範囲で見るべき資料の提示などをいただきながら完成に近づけていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
1.R>G
すべてはこの不等式から始まった。
何かというと、R(資本収益率)は常にG(経済成長率)を上回っているという現象が200年程度続いているということを、トマ・ピケティなる経済学者が過去の税務調査データから読み解いたという研究結果である。
ピケティのこの結果からは、Rの定義を「資本収益」、すなわち、株式や不動産などの収益としている。しかしながら、この「資本」なるものの定義を「既存の社会システム」や「過去に積み上げられたノウハウの独占権」などに広げた場合、労働収益の一部すらも「資本収益」すなわち、素寒貧の人間の「労働」以外の収益となるということになる。
これはどういうことなのか、本当にそうなのか、あるいは、そういう現象が人と社会との関係に何をもたらすのかについて、筆者なりに雑に考察する。
2.広い意味での「資本」なるもの
まずはここで格差を考えるうえで必要な「資本」を定義してみる。
資本をまずめいっぱい広くとると、「存在するだけで利用価値(便益)があるもののうち、戦争でもない限り消耗が少ないモノ」と考えられる。
株式の配当は原理的に消耗が少ない。まあたこ足のごとく資本金を吐き出していたら消耗するが、普通はあまりそういうことはしないものとする。
不動産も一辺には消耗しない。
まあ建物は年単位の時間がたったりすれば消耗するが、
組織に積みあがったノウハウやブランドも、きちんとメンテナンス(技術継承など)をすればそんなに消耗しないし、(技術革新で価値が消えてなくなることはあり得るが、とりあえずそういう技術革新も多くの場合は「既存技術を持っているところが比較検証して使えるものになる」ことが多いので、ここでは置いておく)、行政(「税金を取る」という仕組みなど」)も戦争でもなければそんなに消耗しないものである。
と、ここまで書けばこれでいいような気もするが、しかし本稿では「格差」について考えた場合、「格差を全く生み出さない資本」を除いて考えたほうがより分かりやすくなる。
具体的には「入場制限をしていない公園」や「道路」など、「非排除性を伴う公共財」は除く必要がある。
これを含めてもいいのだが、含めないほうが分かりやすいと考え、いったんこれを除くこととする。
よって、この「資本」の定義を「存在するだけで利用価値(便益)があるもののうち、戦争でもない限り消耗が少ないモノのうち、「非排除性を伴う公共財以外のモノ」」としてみる(仮なのでかなり定義は甘い)。
3.労働
次に、本稿における「労働」を定義してみる。
労働といえば、基本的には何かを「労力を使って加工」することである。
機械と材料を使って何か消費財を生み出しているとすれば、機械や材料そのものは「資本」といえるが、材料を運んでくることや機械に投入すること、機械を操作し、誤作動がないかを確認することは「労働」である。
農業にしても土地や過去に改良された土壌、取れた種子、農具などそのものは(全勝の意味より広義な)資本であり、いまその土壌を改良する行為や種子を植え、面倒を見るという行為は労働である。噺家であれば人が足を止める会場やオンラインであればネットワーク・ソフトウェア・SNS、あるいは噺家個人の名誉や集客シ ステムも資本であり、今現在話している話こそ労働である。
つきつめると、労働は「その瞬間に生み出している価値」であり、資本は「すでに形成された価値」と言い換えることもできる。
本稿では「労働」を「資本を利用して価値を生み出す「その瞬間」の生産のための人間活動」と定義する。
4.なんらかの生産物の「価値」と「資本」と「労働」
生産物を生むということは、「資本」あるいはその資本からとれた「材料」を「労働」によって何らかの加工を加えることによって成り立つ。
となると、最終的に消費される何らかの価値には、資本に付随する部分と労働に付随する部分が存在するというのはごく一般的に当たり前である。
しかしながら、実経済を観測する上で、具体的にこの部分が「資本に付随する価値」であり、もう一方が「労働に付随する価値」であると分けようとした場合、その判断自体に必ず何らかの「価値判断」が出てくる。これはたとえ原価計算の部分を数理的に出そうとしたとしても賃金そのものに実賃金を当てるのか、市場の賃金を当てるのか、あるいはそれ以外の何らかの手段があるのかなど、何らかの「価値判断」を含んでおり、おそらくはどちらがより「希少で価値が多いと思うか」という意識の集合に過ぎない。つまり、生産物の価値に対する資本と労働の価値は、実態よりも「希少と感じているか」によって変わる。
5.RとLの性質の違いからくる必然
資本生産性と労働生産性には必然的な違いがある。
それは、資本生産性が「金額や知識(特にマックス・ウェーバーの「官僚制」による蓄積)などによりいくらでも蓄積可能」なのに対し、一人当たりの労働生産性は身体的限界などにより上限が存在することである。その格差を補うのは「労働者の数」であるが、市場の競争において、必然的に「資本の優位性」が増してくることになる。(この問題を解決しようとして「共産主義」が提案されたが、その試みは政治的指導層の腐敗と国民の意欲管理ができなかったこと、国民の知識の発展を阻害したことなどによって失敗した。しかしながら、「資本主義の問題」そのものが消滅したのではない。)
6.「就活」とは何か
ここまで書いたところで、わが国特有のイベントである「就活」とは何かについて考えていきたい。
基本的に自分の労働力による生産物で自分が食うに足る価値のあるものを何らかの手段で生産しようということであれば、わざわざ「就活」というものをする必要はない。
しかしながら、これは現実的ではない。なぜなら、現代人が現代における「最低限度の生活以上の生活」をするための生産活動をしようとすれば、相当な「資本」による力を借りなければ追いつかないためである。(技術・知識・ノウハウ・ネットワークなどを含む)
そのためには、何らかの形で「資本」にアクセスする必要があるが、そのための手段としては「金融機関にカネを借りたり誰かに資本を出してもらうことで金銭を得てそれを資本アクセスとする」か「資本を管理している組織にアクセスして従業員となる」という方法が有力である。
そして、後者のための手段が「就活」ということになる。そこでは、「組織の従業員」は「同じ資本を利用して生活する新しい仲間」として、「どの就活生を迎えるか」を決めることとなる。
7.「労働」と「雇用」の悲劇
前段で述べた通り、「新しい就活生を従業員として迎える」際に、当然もともとの組織の従業員はどのような基準で新たな就活生を選別するのであろうか。
当然ながら、「既存の従業員にとって良い人材」を選ぶことになる。そのためには基準は二つあると思われる。
基準の一つは、「資本の蓄積と生産性向上に資する人材」である。例えばよく働く人材や、発明、イノベーションのタネを作れる人材などである。
もう一つの基準は「既存の従業員にとって快適な人材」である。例えば、コミュニケーション能力に秀でた人材や、性的魅力に富んだ人材ということになる。
そして、「現状の生活を改善するためにより自分たちが稼がなければならない。そして、その見込みもあり、そのために必要な人材が決まっている。」と思っているときには前者が選ばれる。そして、現状の生活に満足しており、自分たちは今以上に無理をして稼ぐ必要はない。そして、だれが新しく来ても問題ない」と思っている場合、後者が選ばれる。この「前者」よりも「後者」が選ばれる組織が増え、社会全体が「コミュニケーション能力」を要求する社会は「労働の生産性」を無視しても成り立つ経済という認識をもっている社会となる。これを「社会経済の資本化」と定義する。
すなわち、「人の手による」成長をする気がない企業の場合、コミュニケーション能力が強調され、現状の従業員にとって「快適」な人材が選好され、優遇されることになる。その結果、「コミュニケーション弱者」は、ほかにどんなに技能があったとしても「不快である」という理由で排除されることになる。また、仮に必要な技能を持っていたとしても、不快であるがゆえに隔離され、冷遇されることとなる。
そういった選考の結果、企業の従業員の多様性は失われ、「生産に貢献できる人材」は減少する。また、「コミュニケーション弱者」はどこにも受け入れられずに衰弱することとなり、その能力を発揮する手段を失う。そして、それらが積み重なった国家では、経済成長の機会を失うこととなる。
8.成長の必要性は何によって決まるか
では、社会全体において「人の手による成長」をする必要がないと「感じる」ような社会とはどんな時だろうか。
企業においても社会においても表向きは「経済成長が必要だ」というようなことは必ず言う。リソースはあるに越したことはないからだ。しかしながら、実際には失業がそれなりに発生したり、働きに見合った賃金が払われていなかったりなど、「言っていることとやっていることが違うじゃないか!」という事態は当然に起こりうる。
この点については、低成長だった社会や時代がどんなタイミングだったかを考えてみるのがよい可能性が高い。
低成長時代といえば、世界史的にはローマ帝国末期である。当時のテクノロジーでは市民生活はこれ以上ないほどに快適になり、パンとサーカスが供与され、これ以上の生活はそう簡単には望みえないほどになっていた。その結果、人口の伸びも経済成長も低下し、100年単位の時間をかけて衰退していった。
もう一つの時代はわが国だと江戸時代。特に江戸そのものであろう。
江戸時代も都市部に関して言えば極めて快適な生活ができていた。それこそ当時の感覚ではそれ以上望みえないほどにである。その前の時代が戦国時代という「戦争と高成長」という時代であったからなおさらである。農村からしても、戦国時代に比べればおおむね年貢の率は下がっており、(四公六民は戦国時代としては斬新だったが、江戸時代には守っていない大名はいっぱいいるとはいえ「標準税率」となっている。)その結果、「これ以上豊かな生活」が想像できなくなってしまった。
つまり、「これ以上豊かな生活」が想像できなくなってしまったとき、様々な意味で経済成長の意思がなくなると推測しうる。
9.それでも「成長」は必要である。
さて、現状の日本という国を振り返ると、長年かけて蓄積させてきた様々な「資本」を利用し、それを効率的に運用することで牛丼福祉論に表されるような安価で快適な食生活や無料で提供されるインターネットの娯楽など「パンとサーカス」があふれることで、これ以上の豊かな生活が「それこそセレブの生活」意外に想像できなくなってしまった。
しかしながら、そのような社会でヘイトスピーチをなくせと言っている団体から「キモイおじさん」などヘイトスピーチが飛び出すほど、「快適性」が人に対する評価の基準になり、その結果、リソースが低下したうえにリソースへの関心が失われた結果、「滅びが約束される」という事態を本気で心配されなければならなくなった。
人類はいまだ経済成長と人口維持なしで「快適な生活」を持続する手段を知らない。であるとすれば、その可能性を「持続」するためには人間の評価を「快適性」一辺倒ではなく「きもくても使える人材」を活用する努力をするという「不快な」営みが必須となる。
きれいごとではなく、真に持続可能な社会を営むためには、「快適」を追及するだけでは追いつかず、「きもくても使える人材」を社会に包摂し、参加してもらう必要がある。
