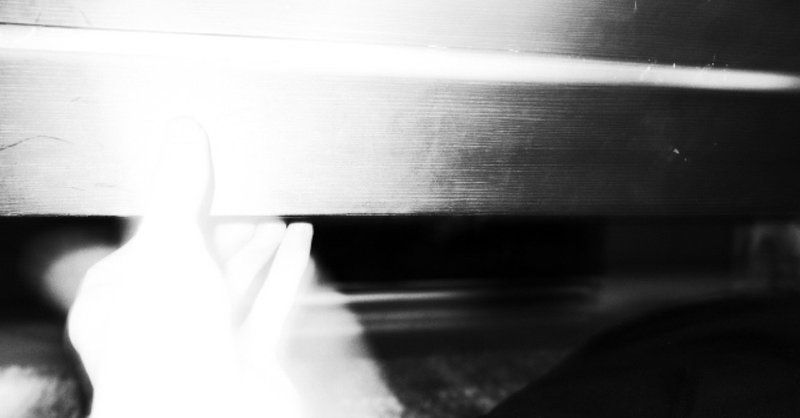
nero 3
雲の裏で人の目にさらされていないときでも、太陽はちゃんと動いている。ネロがもたもたしている間に、世界はすでに薄暗い。雪は地球の影をかぶって、灰色にくすんでしまった。そしてそのまま、雪は降り積もった灰になってしまった。まるで化学反応みたいに。言い忘れていたけれど、この小説は厳密なリアリズムなんだ。苦しみも悲しみも、―その比率に偏りはあるかもしれない―偽装なしできっちり含まれている。
ネロはどんなに力を込めても、身動き一つとることができなくなってしまった。少し動くだけで灰が舞い上がって、ネロの気管をひっかきまわすからだった。風の音は聞こえなかったけれど、ほんとうは強い風が吹いているのだという事を、灰がその振る舞いをもって示していた。
雪上歩行用の器具(ペンギン・シューズ)は灰に巻かれて消えた。むせて咳をするたびに、灰は喜々として舞い上がって、ネロの真っ赤に充血した目から大きな球の涙が、ころころところがり落ちた。涙は外に出ると、あっという間に空気中の灰の粒子を溶かして黒く濁った。涙の流れた跡には、待ち受けていたかのように細かな灰がわいわいと集合してきてこびりついた。
苦痛に耐えるしかないネロは、顔をくしゃくしゃにして、まるで悲しんでいるかのようだった。
しばらくなすすべなく、石像のように固まっていると、涙で歪んだ視界の隅に、紫色が揺らめいた。ネロはしつこくあふれる涙を繰り返しぬぐいながら、しかしいくら拭っても涙は湧いてくるので、涙の歪んだレンズを通して紫色の方向を見つめた。
それは雪の下から、風に揺れるビニールのように頼りなく、わずかにちょろちょろと姿を見せていた。
答えから先に言ってしまうと、それは子どもたちが操るガスバーナーの炎の色だったんだ。子どもたちは含ませる空気の量を変えたり、化学物質を混ぜたりして、炎の色を遊ばせていた。
オレンジだけじゃない。グリーンやオレンジ、ピンクもあった。彼らは、さっき空き家の二階から降りてきた子どもたちとは雰囲気がちがっていて、きびきび動いていた。働きものたちだ。
ガスバーナーは灰を雪に戻すだけでなく、それを溶かすこともできた。彼らは雪を溶かすことで、むき出しになる地面の上を歩いていた。ペンギン・シューズなんて必要なかった。彼らは庭に打ち捨てられた補助輪付自転車のように途方に暮れた様子のネロに気付くと、人好きのする笑みを浮かべながら近づいてきた。
「きちんとお金を払ってくれるなら、行きたいところに連れて行きます」と、先頭で提灯と貯金箱を持つ子どもが言った。ネロは丁寧な口調で話す子どもに、奇妙な印象を受けた。
「いくら?」
子どもはためらいなくそれなりの金額を要求した。ネロは了承して、お金を払った。財布が軽い。お金は、子どもが持つラクダの形をした貯金箱の、二つの瘤に詰め込まれた。
列の最後尾に、ネロは合流した。雪の壁に挟まれ、圧迫されながら、ぬかるんだ地面を進んだ。先頭で、ドリルのようにバーナーを扱い雪を掘り進めていく子供たちは、7人で効率的に動いた。素晴らしい手際なんだ。
提灯の子どもは、全体を見ながら、進む方向を決めたり、バーナーを持った子供たちが見えていないところを注意する。バーナーを持った子どもたちは二人一組だった。一人が雪を溶かし、もう一人が替えのガスボンサルや、炎の色を変化させる化学物質を用意しておく。どうして炎の色を変えるのかは分からない。合理的な理由は分からないけど、見ている分には鮮やかで楽しいんだ。
溶けた雪はさまよう水になって、一行の背後に小規模な池となってたまったり、斜面をせかせかと流れ下りていったりした。
山には手つかずの雪がたっぷり積もっていたから、一行を挟む壁はどんどん高くそびえた。顔の高さにまで迫ってくることもあった。だけど、子どもたちはプロフェッショナルだった。彼らは危なげなく、雪の中に道を作っていった。
ネロは、手のひらで肘を包むようにして腕を組み、背を丸めて歩いた。
みんなの行進は、地面のぬかるみのおかげでべちゃべちゃと音を立てている。また、バーナーの炎の熱から遠い最後尾は、ひどく冷えこんだ。ネロが振り返ると、東の地平線から夜が這い出して来るのが見えた。
ネロの他に子どもたちの後をついて歩いていた人たちは、山に入る前にみな列を抜けて、遠ざかり見えなくなっていった。そのうちの一人の乗客、あるいは後続人に
「どこまで行くんですか?」
と訊かれて、ネロは正直に
「訓練施設です」
とこたえた。
「それは良いことですね。私たちのためにもぜひ頑張ってください」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
