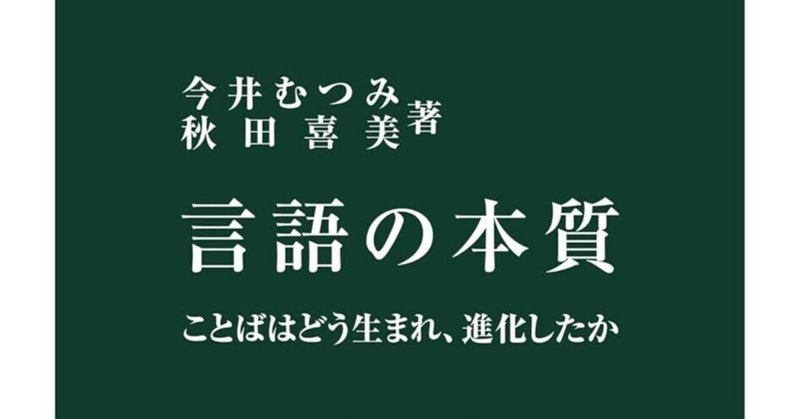
人間特有の「学ぶ力」を考える〜『言語の本質』
◆今井むつみ、秋田喜美著『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』
出版社:中央公論新社
発売時期:2023年5月
言葉なんかおぼえるんじゃなかった。かつてそのように歌った詩人がいました。もちろん人は言葉をおぼえようと決意しておぼえ始めるわけではなく、無自覚なままに言葉をおぼえ、気がついた時には言葉を操る人生を送っているのですが。
言葉なんかおぼえるんじゃなかった、という思いでさえ、言葉抜きに表現することは難しいでしょう。
人間と言語の不可思議な関係は昔から多くの人の思索や研究を誘ってきました。
言語と身体。言語の起源と進化。子どもの言語の習得について。本書ではそのような問題を考え抜いた末に「言語の本質」を浮かびあがらせます。一見大仰でダイレクトな書名が本を手に取るのを躊躇させなくもないのですが、いったん読み始めれば、その面白さに引きずり込まれること請け合いです。
その鍵となるのはオノマトペ。げらげら。もぐもぐ。ふわふわ。……日本語話者なら誰もが当たり前に使っている擬音語・擬声語・擬態語です。
従来、オノマトペは幼稚なものと考えられ、言語学の研究においては軽視されてきました。言語は膨大な抽象的記号の集まり。オノマトペを分析しても言語の本質にはたどりつけないと考えられてきたのです。
本書はそうした言語学の主流に挑む試みです。抽象的な概念を自由自在に操作できることが人間の知性の象徴と考えられてきましたが、抽象語の森に分け入るには、その前に何らかのきっかけが必要なはず。「サラサラ」「ザラザラ」のように、物事の特徴の一部を写し取るオノマトペは、身体感覚に近いので理解しやすいものです。ならば言語理解はオノマトペを足がかりにして成立しているのではないか。このような記号接地問題を基点に、オノマトペの考察に向かうのです。
オノマトペのアイコン性は様々な語形に見出されますが、一例をあげると、重複形をみればわかりやすい。「ドキドキ」は鼓動が繰り返し打つから「ドキ」を繰り返します。反対に繰り返さないことで繰り返さない出来事を表すのも語形のアイコン性です。「ドキッ」「ドキン」「ドキリ」はいずれも一回の鼓動を表します。
もちろん話はそこで終わりません。実世界と言語を接地させるのが「オノマトペ」であれば、私たちをその先の抽象的な語彙へと導いてくれるものが必要です。それは何でしょうか。本書の回答は「アブダクション推論(仮説形成推論)」というものです。演繹でも帰納でもないアブダクション推論の進化的な起源をみていくと、過剰一般化なる推論を見出すことができます。
対象→記号の対応づけを学習したら、記号→対象の対応づけも同時に学習する。人間が言語を学ぶときに当然だと思われるこの想定は、論理的には正しくない過剰一般化なのである。(p228)
ヒトの子どもがことばを覚えるという事実は、その時点でそのような推論を行っていることを示しているのです。それにしても、論理学的には誤謬とされる推論が言語習得の鍵を握っているという仮説はまことに興味深い。このような非論理的な推論が持つ利点として、本書は「既存の限られた情報から新しい知識を生み出すことができる」ことを挙げています。しかも、より少ない法則や手順で多くの問題を解くという節約の原理にもかなっているのです。
……言語習得とは、推論によって知識を増やしながら、同時に「学習の仕方」自体も学習し、洗練させていく、自律的に成長し続けるプロセスなのである。(p204)
オノマトペから私たちの思考のあり方そのものへ。言語の進化をとおして人間の思考の壮大な旅路を追体験できる一冊といえるでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
