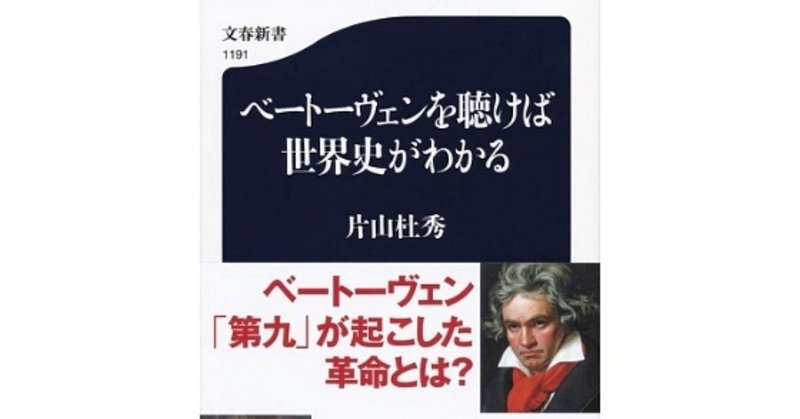
受容者層の変遷に着目した音楽史〜『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』
◆片山杜秀著『ベートーヴェンを聴けば世界史がわかる』
出版社:文藝春秋
発売時期:2018年11月
音楽の歴史には人類の歴史そのものが刻まれている。とりわけ音楽の受け取り手である教会、宮廷、市民層の変遷は、まさに政治、経済、社会の歴史にほかならない。本書はそのような認識に基づき、音楽批評にも健筆を振るっている思想史研究者の片山杜秀がクラシック音楽の歴史を語りおろしたものです。
ヨーロッパの音楽史で、中身がある程度はっきりしたかたちで今に連続していると考えられるのは、中世に成立したといわれるグレゴリオ聖歌です。伴奏がなく人間の声のみで歌われるのが基本形。メロディは今日の感覚からすればとても単調です。それは人間にとって楽しいかどうかが問題ではなく、神の秩序すなわち「ハルモニア・ムンディ」を反映した音楽だから。
宮廷音楽は壊滅することがありますが、宗教音楽はその宗教ある限り残ります。キリスト教はもちろんヨーロッパの歴史を貫いて信仰されてきました。クラシック音楽の権威性のルーツはグレゴリオ聖歌に端を発する教会音楽にあります。それはキリスト教の権威を示し、神の秩序をあらわす最高の道具としても機能してきました。この宗教音楽としての特性は、その後、クラシック音楽が世俗化しても脈々と引き継がれていきます。
グレゴリオ聖歌のモノフォニー(単旋律)の世界の後に、ポリフォニー(多声音楽)と楽器の多様化現象があらわれます。そのきっかけとなったのはオルガヌムという唱法です。それは単旋律に同じ旋律をダブらせるところから始まったとされています。その背景には十字軍遠征による東方からの影響などが考えられるでしょう。
グレゴリオ聖歌を歌うのは修道士や神父たちで、聴衆は聖職者たち自身であり、ミサなどに参加する信者でした。
その状況を大きく変えたのは16世紀に始まる宗教改革です。
宗教改革の口火を切ったマルティン・ルターは音楽にも通じていたことはよく知られています。教会で歌う歌もラテン語の聖歌ではなく、ドイツ語の讃美歌に代えていきました。重要なのは、グレゴリオ聖歌からポリフォニーの教会音楽までは修道士や神父が歌い、信者は聴く立場だったのが、宗教改革以後、プロテスタントでは信者たちが自ら歌いかつ祈る、いわば参加型のスタイルに変わっていったことです。
さらに宗教改革の音楽の特徴として、独唱・独奏が重視されるようになったことも挙げられています。
……宗教改革は、民衆が主体的に信仰と音楽に参加していくコラールの「参加の原理」と、私に与えられた天職をまっとうし、ひとりで歌い、一対一で神とつながろうとする独唱の「個人の原理」という二つの方向性をもっていたといえるでしょう。(p72)
……そこでは、神の秩序を表象するパノラマのような音楽から、個人を主体とした参加と、魂の叫びとしての音楽への大転換が起きていました。近代の自由主義や民主主義を用意する音楽が登場したのです。(p73)
この時期、ローマ教会の絶対性が揺らぐ過程で、もうひとつ、神の秩序を目指す音楽から離れ、人間の感情をストレートに表現する音楽ジャンルが誕生します。オペラです。
ルネサンス期には、個の感情の爆発、官能性の表現、ギリシア神話などに姿を借りて現実の人間世界がテーマとなり、世俗の舞台で堂々と演じられるようになりました。オペラの誕生は、こうした音楽の世俗革命だったといえます。
教会とともに音楽のパトロンとなったのは現世の権力を握った王侯貴族たちです。彼らは専属の音楽家を雇って自分たちのために作品をつくらせ、自分たちの屋敷・別荘などで演奏させました。その時代に登場したのが、ヨハン・セバスティアン・バッハ、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルらです。またゲオルク・フィリップ・テレマンの活躍も無視できません。彼は公共の世俗的催事のための音楽、教会音楽、オペラなどの娯楽作品などを次々とつくります。まさに市民の時代の幕開けを象徴するような作曲家でした。
バッハは当時、テレマンほどの人気はなかったといいます。かつてのポリフォニーの音楽の時代にこだわる古いタイプの音楽をつくっていたからです。フーガやカノンなどの対位法的な手法を徹底的に使って音楽を緻密に数学的に織り上げていくことにこそ、音楽の本分があると信じていました。しかしそれは時代錯誤なことだったのです。
18世紀になると、商業経済の活発化に伴い、大都市圏では市民層が主役になっていきます。ドイツやオーストリアなどではまだ領主たちの力が強かったのですが、宮廷音楽家を養っていくことは次第に困難になっていきました。その就職難の波をまともに受けたのがモーツァルトです。彼の生涯の大半は、ヨーロッパ中の宮廷をまわる就職活動に費やされたといっても過言ではないらしい。「ハイドンやモーツァルトが変わったのではない。作曲家の商売相手が変わった」のです。
19世紀になるとようやく作曲家は自立できるようになります。その頃には市民層の拡大により、音楽教師の需要も高まります。ベートーヴェンはそんな時代に生まれた偉大なる音楽家でした。
片山は、ベートーヴェンの音楽を三点に要約しています。
「わかりやすくしようとする」「うるさくしようとする」「新しがる」──かなり大胆なまとめ方ではありますが、解説を読めばなるほどと思います。ベートーヴェンの時代に音が大きくなった社会背景として片山は都市化と革命と戦争を挙げています。そうしたコンセプトのうえに成立した「第九」は、当時の「市民の音楽」の最終形態であり極限形態だというのが片山の見立てです。
その後、ロマン主義の時代が到来します。ポスト・ベートーヴェン時代の市民は生まれながらの近代ブルジョワで「芸術の権威、音楽の高尚に、市民社会における神の等価物」を求めるようになります。クラシック音楽の権威化が起こるのです。音楽学校というシステムが成立し、音楽理論も煩雑化していきます。
ロマン派の本質は「旅」にあります。ここではない何処かに憧れて彷徨うこと。それがロマン派の精神。この頃に台頭した「教養市民」が高尚な芸術に憧れる姿はまさにロマン派そのものだと片山はみなします。
そして手の届かないものへの渇望に強烈なナショナリズムを強力に結びつけたのがリヒャルト・ワーグナーです。
ワーグナーの音楽は、近代と土着のナショナリズムによる統合でした。それがドイツという非常に強力な国家の形成に貢献したのでした。
そのような19世紀を経た後、クラシック音楽は「洗練」と「超人志向」の二つの流れを生み出します。市民社会のひとつの完成や行き詰まりとしての「洗練」と、その壁を踏み越えさらなる進化を目指す「超人志向」。
演奏家はクライスラーのように、趣味の良い典雅さの中に微妙なニュアンスを込めるスタンスが高く評価されるようになります。「超人志向」の音楽としては、ワーグナーにつづいてグスタフ・マーラーやリヒャルト・シュトラウスなどが現れました。
第一次世界大戦は音楽の世界をも当然ながら大きく変えました。もはや進化も超人も決定的にリアリティを失います。音楽は刹那的で享楽的なものになる。ジャズはその代名詞でしょう。クラシック音楽の世界では、新古典派音楽が登場し、さらに前衛音楽が生み出されます……。
シェーンベルク、ストラヴィンスキー、ラヴェルがそれぞれ表現しているのは、壊れた世界で、周囲も見えぬまま、我を忘れて熱狂し、時間も空間もすっかり分からなくなって、バタンと倒れて、それでおしまい、という世界です。これぞ二十世紀のクラシック音楽が第二次世界大戦の前の段階で到達した姿です。その世界の、まさにサーカスの綱渡りのような延長線上に、われわれは今日も生きているのです。(p234)
音楽家の音楽観や精神性などにスポットを当てた音楽史はこれまで数限りなく書かれてきました。本書のように音楽の受容層の変遷に着目したものは類書にはないユニークな特長といえるでしょう。なるほどいかに優れた才能といえども社会から隔絶されたところから芽を吹き出すことはありません。とりわけクラシック音楽というジャンルは、演奏され人に聴かれるためには、多くの労力と金銭を必要とします。聴衆のニーズをくみ取ること。音楽家がそのことを無視できなかったのは明らかです。片山の音楽史観はこうして一冊の本にまとめられると、至極説得的なものだと思われます。
中公新書から出ている岡田暁生の凡庸な『西洋音楽史』に比べると段違いの面白さといっておきましょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
