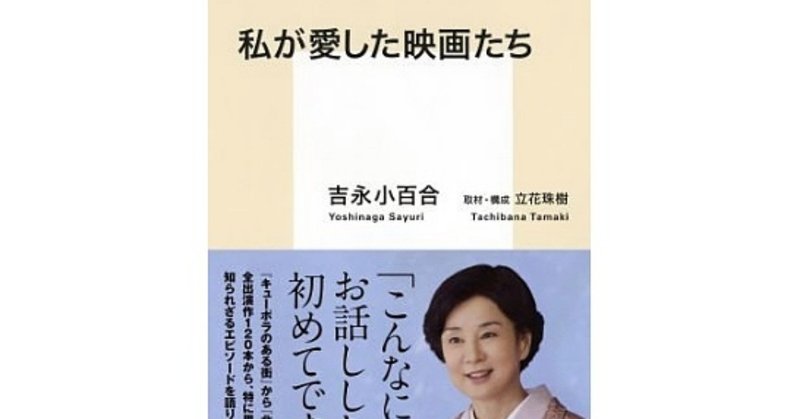
戦後民主主義を生きてきた女優〜『私が愛した映画たち』
◆吉永小百合著『私が愛した映画たち』
出版社:集英社
発売時期:2018年2月
吉永小百合は日本が敗戦した1945年に生まれました。文字どおり日本の戦後民主主義の歩みとともに生きてきた映画女優といえるでしょう。《朝を呼ぶ口笛》でデビューして以来、最新作の《北の桜守》まで出演した作品は、120本。本書ではその中からとくに吉永にとって印象深い作品を選び、それに即した思い出話やエピソードを問わず語りで振り返ります。インタビュアーは共同通信者編集委員の立花珠樹。
《キューポラのある街》は吉永が日活入社三年目の作品で、私も名画座で観て大変印象に残っています。フランソワ・トリュフォーは「主役を演じた女優がたいへん見事でした」と評したらしい。父親役の東野英治郎は酒を飲まなかったけれど酔っぱらいの芝居は上手だった。「東野さんを見ていて、役者っていうのは経験ではないんだな、観察力なんだなと実感しました」。
《愛と死をみつめて》は原作を読んだ吉永が「どうしてもやりたい」と会社に願い出て実現したもの。日活史上、興業成績ナンバーワンを記録した作品です。《愛と死の記録》は広島で被爆した青年とその婚約者の悲劇を描いています。被爆者の顔のケロイドの場面などを日活首脳部がカットするように命じたのは愚挙だったと私も思いますが、「切られる前の “完全版” を、皆さんに観てもらいたかった」と今も憤りを隠しません。
1970年代に入り、スケジュールが過密だったこともあってか吉永は突然声が出なくなるというアクシデントに見舞われました。そんな時に出会ったのが松竹のドル箱シリーズ《男はつらいよ》。録音のレベルを上げてもらってなんとか乗り切ったらしい。「役者なんて、さだめのないもの。だから何年も先の仕事を決めるもんじゃない。ふらっと出会った作品の中で自己実現していくもんなんだ」という渥美清の言葉を今も大事にしているといいます。
《動乱》では高倉健と初めて共演します。吉永にとって「再び映画への情熱を蘇らせてくれる作品にめぐり逢うことができた」という貴重な作品です。厳冬期の北海道ロケで、高倉が雪原で独りぽつんと立ったまま昼食のカレーライスを食べていた姿を回想する語りは高倉の映画に対する姿勢を象徴的に伝えてくれます。「役になりきっている状態で、集中力を切らさないために、暖かいバスの中に入らないようにされていたんです」。
《夢千代日記》では被爆したヒロインを演じ、NHKの人気シリーズになりました。シリーズの幕引きとして映画化作品に出演したときの挿話は本書のなかでもとりわけスリリング。監督は《キューポラのある街》の浦山桐郎でしたが、一つのセリフをめぐって監督と対立したのです。吉永は最後まで譲らなかった。「たった一つの台詞を譲らなかったのを見て、私は小百合さんのことを認めました」と共演した樹木希林は後に述懐しています。
《細雪》は巨匠・市川崑との初仕事。「それほど積極的にやりたいという気持ちではなかった」ようですが、「でき上がった映画の中に今までの私と違う、新しい私を見つけました」。その後、吉永・市川コンビで《おはん》《映画女優》《つる 鶴》の三作が作られましたから、相性は悪くなかったと思われます。
深作欣二監督作品《華の乱》ではで与謝野晶子役を演じました。「夜の撮影は12時までに終えてほしい」と要望していたのですが、初日に反故にされたらしい。ハリウッドなら吉永クラスの女優なら契約書に盛り込んで法的に厳守させるところでしょうが、日本ではそうもいかないようです。
《外科医》《夢の女》は歌舞伎俳優・坂東玉三郎とのコラボレーションとして話題を集めました。「女性らしいしぐさについて学ぶことができました」という発言がおもしろい。吉永は女優としての基礎訓練を受けてこなかったので、歌舞伎の様式美からは吸収すべきことが多々あったのでしょう。
《北の零年》《北のカナリアたち》《北の桜守》の北の三部作は吉永が企画段階から参画しました。《北のカナリアたち》で共演した子供たちは今でも吉永の役名である「はる先生」宛で手紙やメールを送ってくるといいます。
《母と暮せば》での母親役は「これまでで一番難しい役」だったとか。せりふが多く、一人芝居的な要素が強かったからと。私は山田洋次作品の台詞の多さ、説明過多な作風はまったく好きになれないのですが、吉永は役者の側からそうした演出の意味を汲み取ろうと努めたことが真摯に語られています。
立花の筆致は全体をとおして吉永に対してきわめて好意的であり、その点は本書の雰囲気を、よく言えば和やか、厳しくいえば微温的なものにしているように感じました。また、本書における吉永の印象的な発言は既刊書のなかで紹介されているものも多く、本書がどこまで吉永の意外な側面を引き出しているのか評価は微妙なところです。
何はともあれ「サユリスト」にとっては安心して楽しめる一冊には違いありません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
