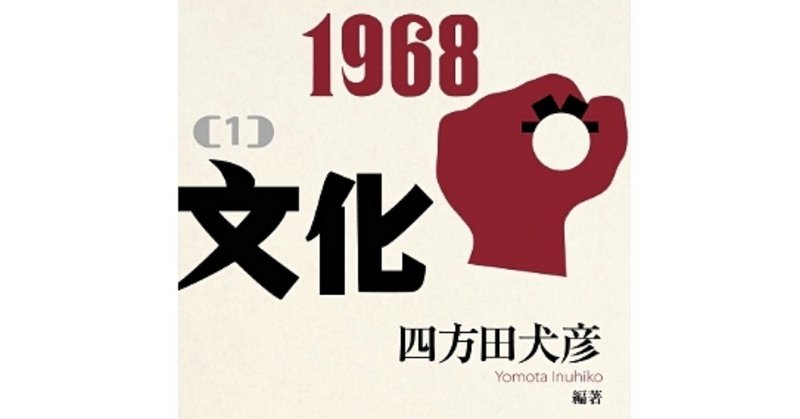
時代が生み出した多彩な才能〜『1968[1]文化』
◆四方田犬彦編著『1968[1]文化』
出版社:筑摩書房
発売時期:2018年1月
1968年。それは世界の現代史にあっては特筆されるべき年でした。
米軍がハノイ爆撃を本格的に開始しベトナム戦争が激化する。ドゴール政権打倒を叫ぶ学生たちによりパリで次々と大学が閉鎖され「五月革命」が始まる。西ベルリンで学生がゼネストを行なう。
日本ではエンタープライズの佐世保入港をめぐり全学連と機動隊が激しく衝突する。東京大学医学部自治会では無期限ストに突入する。年末には入試中止が決定される。成田空港反対集会で反対同盟と全学連が警官隊と初めて激突する。日本大学で全共闘の大集会が行なわれ、初めてヘルメットが出現する……。
こうした若者たちの政治的反乱と連動するかのように、文化の領域においても様々なムーブメントが発生しました。「1968〜72年は、世界の文化が同時性のもとに成立した歴史上はじめての瞬間であった」のです。
今年2018年は、1968年から50年目のメモリアルイヤーにあたります。本シリーズはもちろんそれを意識したもので、全三冊ともに四方田犬彦が編集を担当。第一弾〈文化〉編の本書では、美術、演劇、舞踏、図像、映画、音楽、ファッション、写真など文化領域における当時の前衛的な活動を掘り起こし現代人の前に差し出します。
四方田の巻頭言がいい。
ある時代の記憶に接近するために最初になすべきこととは何だろうか。
まず先入観を捨てることだ。次に、そこに複数の地層が重なり合っていることを、冷静に認めることである。とりわけそれが変革と破壊、実験と試行錯誤に満ちた時代であった場合、生起していた事象の一つひとつを前に、スコップと軍手を用いて、丁寧に発掘の作業を試みなければならない。真実は埋められているか、封印されているかのどちらかであるからだ。その時代に一世を風靡していたものだけを追いかけてみても、時代の本質である真実に到達することはできない。(p23)
椹木野衣は、1970年の大阪万博を基軸にして、万博に協力した前衛美術家たちとそれに反旗を翻した一群(ダダカン、ゼロ次元など)の対照を浮き彫りにしています。そして「祭りのあと」に台頭した「もの派」に言及しているのは当然としても、さらに、そのような大きな流れとは別の個別的な動き──美共闘、タイガー立石、菊畑茂久馬──に注目しているのも本書の趣旨に適っているといえましょう。この時代における美術の動きは多様性に富み、その混沌がそのまま現代にまで通じていると椹木は指摘します。
四方田自身が執筆している「グラフィックス」の章もなかなかおもしろい。ベ平連発行の『週刊アンポ』がビジュアル的にも実験的な試みを行なっていたことは不勉強ながら知りませんでした。粟津潔、横尾忠則、赤瀬川原平、佐々木マキなど錚々たるメンバーが入れ替わり立ち替わりに表紙を担当していたのです。イラストはもはや文章の添え物であることを止め、自立した表現ジャンルとして存在を主張するようになったのがこの時代からといいます。
「演劇」を担当している西堂行人の論考は、唐十郎、鈴木忠志、寺山修司らの活動を当時の政治動向と関連づけながら活写しています。まさに「アングラ革命の時代」でした。時代が母体となって次々と才能を輩出する。そんな時節がそう遠くない過去の日本にあったのです。
大島洋の「写真」論もいささかカタログ的ながら当時の熱気をおおいに伝えてくれるものです。1968年は写真にとっても画期的な時代だったといいます。特筆すべきは何といっても写真同人誌『PROVOKE──思想のための挑発的資料』。多木浩二、中平卓馬、森山大道らによる「ブレ・ボケ」の作品は既存の写真の価値観を大いに揺すぶったのでした。
「舞踏」に関しては、國吉和子がもっぱら暗黒舞踏の土方巽にスポットライトを当てています。「個人史と日本の近代が渾然と混ざりながら形成されてきた自分の肉体を、徹底的に対象化し、それによって自らをもつき放そうとする」土方の強烈な批判精神が言語化されています。
社会学者・稲増達夫による「音楽」論は、ビートルズやGS(グループサウンド)への若者の熱狂と大人からの批判について「世代断絶」とみなして興味深い。GSにこだわるのは「当時はビートルズよりもファンが多く影響力もあった」のに「商業主義」「欧米のコピー」「無思想」といったステレオタイプで貶められることが多いからといいます。ロックと歌謡曲が化学反応を起こした日本独自の「民族音楽」なのではという問いかけもあながち大げさとはいえないでしょう。
「ファッション」について語る中野翠はみずからの実体験に即した書きぶりで、多くの資料と格闘したと思しき他の男性論客とは一味違う、いかにも中野らしい随想を寄せていて愉しい。
「映画」はもちろん編者の四方田犬彦による一文。まずは本書のテーマとなっている1968年から数年間の動向について端的な言明を下しているのが注目されます。
1968年から72年にかけての5年間とは、それまで独自の発展を見せてきた日本映画が、〈世界映画〉の最前線において受容されるという文脈が、ほぼ成立した時期である。(p306)
大手映画会社によるプログラム・ピクチャーと個人の〈作家〉の映画という二つの軸に沿った論考では、とりわけ後者に対して高く評価しているのが目を引きます。
ATGや若松プロ、小川プロに代表される小さな制作会社はこの時期、もっとも豊かな結実を残しているといいます。実験映画で今まさに生成しつつある映像の現前を作品に仕立てた松本俊夫。『エロス+虐殺』『煉獄エロイカ』を世に問うた吉田喜重。青春映画というジャンルの解体へと進めた羽仁進。
さらにこの時代にもっとも過激に活動し、機会あるたびにスキャンダルを引き起こした映画人として大島渚と若松孝二に紙幅を割いているのはこれまでの四方田の批評活動からすれば当然の流れでしょう。
「雑誌」についても一章が割り当られていて、上野昂志が寄稿しています。1960年代後半はいろいろな雑誌が創刊された時代でした。66年『話の特集』『デザイン批評』。68年『血と薔薇』『季刊フィルム』『シネマ69』『PROVOKE』『月刊ビッグコミック』。69年『季刊写真映像』『週刊アンポ』。……こうして振り返ると、写真・映画・デザインなど表現に関わる分野における批評を主なテーマにした雑誌が多い。この時代は政治運動の時代でしたが、表現活動に対する批評が「妍を競った時代」でもあったのです。
本書は、写真作品だけでなく映画のポスターや書籍の表紙などなど図版資料がふんだんに使われた編集で、目で見ても楽しめる作りになっています。1968年という時代の表現や知のあり方、そして何よりも熱気が伝わってくるような本といえます。その試みはけっして過ぎ去った時代への懐古にはとどまらない、私たちの現在的な力動へとつながる何事かを示すものであると思われます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
