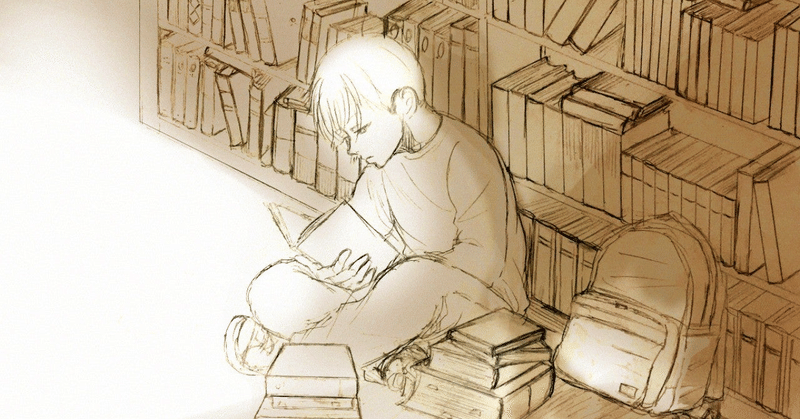
地元エッセイ(10)小中高も失敗続きなエブリデイ
京都エッセイでは、大学デビュー失敗の話を書いた。そんな人間がそれまで失敗がないかと言われると答えはNO。大アリである。
保育園の頃はよく覚えていない。だが、ヤンチャだったと親や地域の人から言われている。小学校の記憶はあって、ヤンチャだったのは覚えているので、間違いないだろう。
小さい頃は本を読むような子どもではなかった。仮面ライダーや戦隊モノを観て、外で帰り道に見つけた棒を振り回して、野山を駆け回っているような元気いっぱいな子どもで、悩みとは無縁だった。当時はそれなりに悩んでいたのかもしれないが、中高大今に比べれば大したことではない。
僕が本と出会ったのは、小学校六年生の頃である。その出会いの少し前から、僕は少し心がおかしくなっていた。きっかけは夏、忘れもしない。僕の人生を狂わせた、あの日の思い出。
プールの授業が早めに終わり、皆が水球などで楽しみはじめたところ、僕は一足先に教室に戻っていた。そこで他の男子一人とふざけて遊んでいた。その最中で机を倒してしまった。中に入っていたものが床に落ちた。
その中の一つに開けちゃダメ、と書かれた紙があった。僕と友人は悪ガキらしく、中を見た。
中に書かれている文字を追っていくうちに僕の心は壊れ、音が遠くなっていくのを感じた。
中に書かれていたのは僕に対しての悪口の数々。誰かが書いた悪口に誰かが「それな、あと〇〇だよねー」「わかるー」といった具合にチャットするように書かれていた。最後の方には好きな男子ランキングと嫌いな男子ランキングなるものがあって、好きの中に僕はおらず、嫌いの中に僕は1位で入っていた。文字の筆跡からするに6人。僕の小学校は僕を入れても8人しかいなかった。
「俺は知らねぇからな」と友人は言っていたので、そいつ以外の全員が俺の悪口を書いた手紙を回していたことになる。
男子は4人しかいないので、僕は好きランキング最下位、嫌いランキング1位ということになるわけである。
プールから戻ってくる同級生たちの足音に僕はようやくハッとなって、ガラッと扉を開けた人の胸ぐらをつかんだが、すぐに取り押さえられた。
話し合いの場が持たれたが、それは書かれていることが真実であることをただただ確定化させていく時間だった。
絶望という言葉を実感したのはあれが初めてだろう。
今となっては言われて当たり前だなと思うし、直せばよかったなと思うくらいの出来事だが、それでも当時の僕には十分なトラウマになった。
それから僕は人間不信になり、みんなぼくのことが嫌いなんだと思い込むようになった。誰かと遊んでいても、話していても、ただ近くにいるだけでも、本当はぼくのことなんか大嫌いで、一緒にいたくないんだろうな、という思いが何度も頭の中をかけめぐる。家族や店員にさえ疑心暗鬼になっていた。
それから僕は人の顔色をうかがうようになった。それまで見ないふりをしていたが、僕と接する人間は困った顔をするような人が多いことに気がついた。
近くにいたら何をするかわからない、気が気でないといった表情だとはわからず、この人は僕のことが嫌いなんだと思ってしまい、癇癪を起こすこともあった。
それから今もずっと、誰かが嫌な表情をしていると、全て自分のせいだ、解決しなければ! と冷や汗がでる。
沈黙が怖い。早く離れろよと、相手が言っているような気がするのだ。
それではダメだと、小学生の自分なりに努力をした。人が嫌がる作業を率先して行うようになった。
トイレ掃除やいきものがかり、洗い物や犬の散歩などなど。
でも同時にそれは褒めて欲しい、認めてほしい、必要として欲しいという心を満たすためのものでしかなく、それがもらえない、どころか例えば女子トイレを掃除していたら変態やキモいと言われたことなど、欲しく無い反応を貰われたらまた癇癪を起こした。
だから結局僕への評価は変わらなかった。
中学生になったら、異性の反応により傷つくようになった。明らかに僕から離れるように弧を描いて通り過ぎていく女子、席をくっつけるときに少しだけ開けられる隙間、班行動や席が隣などになったときのえーっという表情や、実際に陰でそう言っていたこと、善意で拾ってあげたのに、嫌な顔をして泣きながらタワシでゴシゴシ下敷きを擦って洗われたのはさすがにこたえた。
そんな僕はさらに愚行を重ねることになる。男子からは面白がられていて、少しばかりいじってもらえたのだが、それがうれしくて距離がとても近くなってしまった。
あるときネットに詳しいクラスメイトに「お前ホモなん?」と聞かれた。ホモ、を褒められるのほめ、と勘違いした僕は「うん。僕ホモ」と言った。
それから僕に捕まったらヤバい(笑)という空気が出来上がり、普通に近くに行っただけなのに、「逃げろー!」と誰しもが距離を置くようになった。しかしみんな笑顔だったし、なんだか楽しそうだったので、僕はホモという意味をよく知らないままにホモのふりをして気持ち悪がられ、いじられることによって中学時代を過ごした。
たまにいじられてプライドが傷つくと癇癪を起こしたりもして、「急にキレるから怖い」と女子には思われていたらしい。そんなふうだから、少し前に書いた初恋の話で登場した、先輩の女子との時間は本当に貴重で救われていたのだ。
高校生になり、新しくできた友達に見放されたくなくて彼が選んだ同じカヌー部に入った。練習は楽しかったけど、顧問の先生のいじりがきつかった。
昔から知り合いの別のコーチは、とても良くしてくれたけど、二人の衝突でコーチがいなくなってしまってから、僕は嫌になってカヌー部を辞めた。カヌー部では一応一年生で全国にまで行ったのだけど、それ以外に語ることがない。
やることがなくなった僕はアルバイトを始めた。
同時期に通学のための原付の免許をとったこともあり、地元の散策、隣町へ遊びにいくお金が欲しかったのだ。そこでは僕の心の問題なんて関係なく、業務を的確にこなされることを求められ、自分の不甲斐なさに何度も泣いた。
そうして、僕は心を病み、永遠に満たされることのない承認欲求を抱えたまま、大学に行くことになる。
そんな人間が大学デビューに成功するはずは、今思えばなかったのだが、それはまた別の話。
いや、こちらから読めます。是非。(全4話)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
