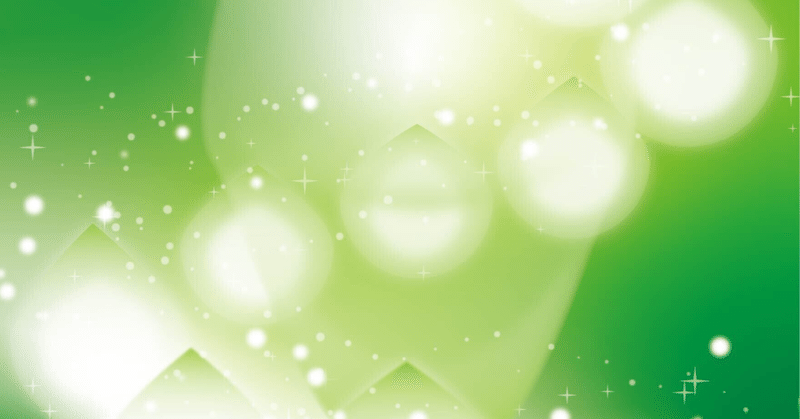
SF『マルチバース調整庁SM管理局』(7) 完結回
(第6話から続く。末尾にマガジンリンク)
裕子は自分が一時的な記憶喪失に陥ったのだと思った。
ダブリンからヒースロー経由でアルゼンチン行きのフライトに乗ったことは覚えていたが、何故ブエノス・アイレスに来たのか、まったく見当がつかなかった。隣席の乗客と会話した記憶が微かにあったが、隣には誰もいなかったという。
とりあえずイミグレを通って入国する。
携帯を見ると、4日後の帰国のフライトが予約してあり、ブエノス市内の住所のホテルの予約も3泊入っていた。オテル・ルルデスとある。予定表には、ある住所がひとつ書いてあるだけ。むしろ旅行予定以外の、ショーンの宿題提出締め切りとか、水泳クラスとかがそこにはいっており、それらはすべて見覚えがあった。
ブエノス・アイレスはちょうど15年前に別れた夫ジョンと旅行で来たことがあった。肉料理とワインが美味しかった記憶だけが残っていた。もしかしたら、予約してあるオテル・ルルデスはその時に滞在したホテルなのかもしれなかった。
まだ早朝だったがほかにすることもないので、空港のタクシーに乗ると、携帯にあった住所の行先を告げる。
長髪の運転手がルームミラー越しに裕子をじろじろみて、片言の英語で聞いてくる。「どこからきたの?」「日本人?」
裕子は昔一人旅をしていたころに旅先でうざい男が声をかけてくると使っていた常套手段の嘘を使って黙らせる。
「日本人じゃないの、ピョンヤンからよ。北朝鮮の政府の軍関係の仕事なの」
*
「結局、いろいろ手を回したが、二人は会うことになるのかね」
スクリーンを見ながら初老のオーバーロードの局長が聞く。
「はい、局長。ChotGPTのシナリオの性癖を梃子にした邂逅回避策があと少しで達成していたところをM管理官がアボートしたので、緊急措置として体験記憶を隣のバースの裕子へ飛ばしたんですが、記憶の断片が若干残ってしまいました」係長が答える。
「まあ、新人担当官のあの直球すぎる人生についての禅問答みたいな問いは、その答えが無いだけに、なんとも究極の放置プレイで性癖を刺激して案外おもしろいとおもったんだがな。しかし、ChotGPTはちょっと紋切すぎる。あれじゃSM小説としてもチープすぎる展開だよ。やっぱり今後はシナリオはAIにまかせず我々が考えていこう」
「新人Mくん、謹慎処分にしましたけど、たしかに反転のMの性癖の裕子にはああいうストレートな問いがSMの鞭みたいに効くかもしれないですね。地球人には人生の意義を問うというのが、究極の凌辱プレイなのかもしれないです」
*
タクシーは裕子を行先の手前で下ろし、前のほうを指さす。
それは古いつくりの地下鉄のレティーロ駅へと下る静かな通りで、画廊やヨーロッパ風のカフェが点在していた。
裕子は、そこで、地球の裏側まで来た違和感がまったくない理由に気が付いた。駅舎の建築が英国風だった。そういえば前夫のジョンが、アルゼンチンには20世紀に入ってイタリア移民とイギリス資本がどっと流れ込んだ、スペイン系南米ではちょっと変わった国なんだといっていたのを思い出す。
住所の場所には、小さな骨とう品屋らしき店があった。まだ朝の8時で閉まっている。
「カサ・デ・アラーニャス」と店名が書かれた真鍮板には、蜘蛛の絵が描かれていた。
グーグル翻訳をかざすと、「蜘蛛の家」と訳がでてくる。
ガラスを通じて少し見える中には、東洋風の家具が並べてあるのがみえる。記憶を探るが、なにも反応しない。手掛かりがない。何故、この店に来たのか、まったくわからない。
しかたないので、店が開くまで待とうと周りをみると、向かい側にカフェがあって開いている。中にはいる。
それなりに広いが、がらがらだったが、身なりのきちんとした初老のウェイターが席へと案内してくれる。
渡されたメニューをみると、昔飲んだことのあるアルゼンチン名物の「マテ茶」もある。
「果報はお茶してマテ、のマテ茶なのかしらね」とひとりつぶやくが、その面白くもない自分の駄洒落に「はぁ」とため息をついて、やはりカフェ・オ・レにしようと思う。
裕子が「カフェ・オ・レ、ポルファボール」というと、初老のウェイターはニコリとして英語で聞く。
「コーヒーは普通のフィルターのとエスプレッソとどちらがお好みですか?」
「濃いエスプレッソが好きですけれど」
「では、コルタードですね。こちらでは普通のコーヒーのがカフェ・コン・レチェ、つまりカフェ・オ・レなんですが、ポルテーニョつまりブエノスっ子は、エスプレッソベースの『コルタード』を好むんですよ」
たしかに運ばれてきたミルク入りの小さなエスプレッソ・カップのコーヒーは、とても香りよく、美味しかった。
裕子が美味しそうにコーヒーを飲むのをみて、ウェイターが聞く。
「ブエノスには、旅行ですか?それともお仕事?」
裕子は微笑み、答える。また嘘をつく。
「仕事関係です。アパレルの。早朝便でついちゃって時間つぶしですけど。歩いていたら、この向かいの骨董品屋がちょっと気になってそれでここに入ったんです」
「ああ、カサ・デ・アラーニャスですね。あそこのオーナーも日本人ですね。あなたもそうでしょう?」
「はい。わかりましたか? オーナーご存じですか?」
「もちろん。ヨーコは週に何回か、朝、うちに寄られます。娘さんを学校に連れていく途中、クロワッサンとコルタードの朝食とられますよ。グアパ(美人)の常連さんです」
そう言うと、ちょうどカフェに入ってきた客の応対で入口へと歩いて行った。
裕子はコーヒーを飲みながら、ゆっくり、途切れた記憶を思い出そうとする。自分の人生でも稀なこのおかしな展開、息子を預けてまで地球の裏まで旅行してきたのになんのためかわからないという事態についてじっと考えるが、頭の中はまだ真っ白、理由や目的はみんな消えてしまっている。
なにか、とてもエロティックな夢を見ていたような気もした。
でも、なぜそんな夢をみたのかよくわからない。
ふと、前の席に誰かが置き忘れたアルゼンチンのタブロイド雑誌があるのが目に入る。
カバーに大きく見出しのついたブロンドの女性の写真がでている。その笑窪で笑った顔はどこかで見たことがある気がしたが、まったくなにも思い出せない。
翻訳をかざすと「アルゼンチン出身の新鋭女優、ハリウッド進出」とでている。
*
1時間ほどすると、カフェの入り口に、小学校高学年くらいの娘を連れた、東洋系の母親らしき人が入ってくるのが見えた。
ウェイターと親しげにハグをすると、入り口近くの席に座る。長身で背筋のぴっと張った姿勢の良い美しい人だった。オリーブグリーンの落ち着いた色のコートを脱ぐと、空いた椅子にかける。
イタリア系アルゼンチン人とのハーフなのだろうか、伏し目がちな可愛い女の子は、ちょっと英国風の学校の制服を着ていた。
裕子は、ダブリンにおいてきた、息子のショーンのことを思い出した。そして今すぐにとても会いたいと思った。
その時、どこからか、とてもいい香りがしてくる。
カフェにはないすがすがしい、森林のような香り。
もしかすると実際にはそこに存在しない妄想の香りなのかもしれない。
でも、たしかにそれを感じることができた。
よく知っている香りだった。
いつかどこかで、もしかしたら前世で、嗅いだことのある香り。
。。。フランキンセンス、乳香の香りだった。
遠い昔の香り。
目をつぶって、それを嗅ぐ。
こころが落ち着いていく。
すると唐突に、なぜか脳裏に短歌が整ってくる。
ポケットにあった紙に書きとる。
そして、それを後でNotesにポストしてみよう、と思う。
その短歌は実はそもそもの混乱のきっかけとしてNotes上にポストされていたものだったがSM管理局によって削除されていたものであった。裕子は、再び、そして記憶を消された今の彼女にとっては新たに、それをポストする。
それがこれである。
ポストすると、まず数万回、そして突如バズって全世界で数億回のスキをあつめることとなる短歌がこれであった。
サムサラの
契りの記憶か
吹く風の
香り懐かし
しばし佇む
その匂いを嗅いだ時、裕子は悟る。
すっと、すべてが腑に落ちてくる。
自分は、
イタリアの14歳の少女でもあり、
江戸のかんざし差した16歳の小娘でもあり、
メキシコのアラサーのハーフのギタリストでもあり、
東京のボリビアからの大学生の留学生でもあり、
更にもっともっといろいろな国の様々な境遇の女性たち、
若さと美しさの絶頂期に自らの行動でその命を絶たってしまう悲劇のヒロイン達、
その繰り返しのメビウスの輪のようなループの中に自分は生きてきているということを
。。。
「でも今世は違う」
口にだして、裕子は言う。
一刻も早くダブリンに帰って、「おかあさん、苦しいよ」と言われるくらい、息子のショーンを強く抱きしめたい。
テーブルをドンと叩いて、立ち上がる。
そして空のほうに向かって言う。
「あんたらね、もうやめてよね。
私は、もう管理されたくないのよ」
(連載完結)
(タイトル画は、Noteギャラリーで「輪廻」で検索してでてきたなかから、センスよいのを拝借)
*この意味深い短歌は吉隠ゆきさん作のを承諾いただいた上で拝借(以下リンク)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
