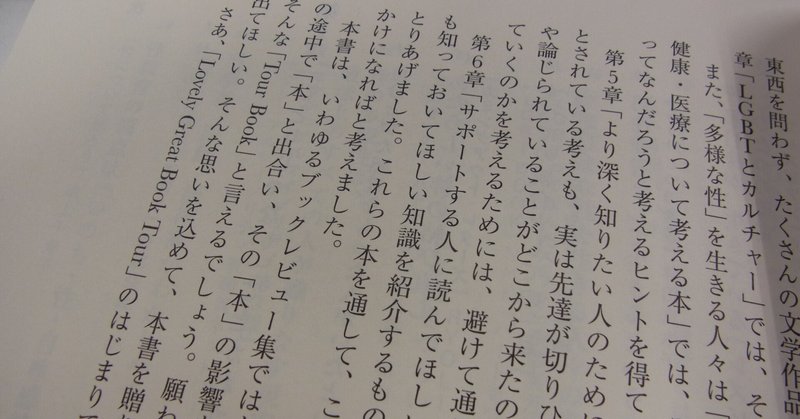
私が制作に【関わらなかった】本
「私たちはゲイの本が読みたいのではない。良い本が読みたいのだ」
そう言った作家は誰だっけ。デイヴィッド・レーヴィット? たぶん。
その言葉がずっと頭にあって、本を作るのであれば「単に性的少数者の本であればいい」のではなくて、それ以前に本として優れていなければならない、という戒めが私にある。書けば当たり前のようだが、それが難しい。
「にじ色の本棚 LGBTブックガイド」(三一書房)
三一書房に「にじ色の本棚 LGBTブックガイド」という本がある。
実は私が企画段階で関わっていて、途中で【暴力的に】身を退いた本だ。
編者は原ミナ汰氏、土肥いつき氏。私も「三人目の編者として」そこにいたのかもしれなかったということ。だが私は編纂中にひどい暴言を吐いて、投げ出した。「後足で砂をかける」というが、その通りのことをやった。

本に私の名前は一切、出ていない。私がクレジットを拒んだせいだ。そうした本について、今さら名乗りをあげて語ることは褒められた真似じゃないと思う。身を退いたいきさつを思えば道義的な意味でもそうだし、すこぶるカッコ悪いし、何より制作側にいたと明かすことで、ここに書くことが一種当事者性を帯び、それゆえ人々に「ここに書かれていることが正しい」と思わせてしまう――「関わっていたのは企画時のみと短期間であり、内情など知らないに等しくても」、私がこの本について「参加していた」と認めた上で書くなら、それが何であれ、決して単なる一読者としての感想や意見として読まれることはない。そうだろう? 分かりきったことだ。
ではなぜ単に一読者として書かないのかと、このニ週間あれこれと考えていた。書くなら読者として書いてよいのだし、書かないこともできるのだ。だがこの本について書く行為が「贖罪」になるのなら――私は書きたい。この記事が一読者としての感想や意見になろうはずがないし、実際そうではない。これは「編者になり損ねた」私による、感傷たっぷりの懺悔である。
なぜ私が身を退くことになったのか。単に、私の傲慢からだ。
何か作ろうとする時、私は隅々までイメージをもって臨む。この本で言えば、「LGBT本」という読み手の先入観をはるかに越えてくる本が並び、「ブックリスト」という体裁を忘れさせる極上の読み物であることを考えた。単にゲイを扱った本というだけで売り物になる時代はとうに終わっている。もう清潔で痛ましい当事者が「私たちも人間です」と健気に書いみせて感心される時代じゃない。「感心などされて満足してるな、感動させるんだよ!」と書き手に示し、出版界も驚かせなければならない。そんな気負いがあった――それは完全に正しい考え方だったと今でも思っている。他の面々と心震えるほど感動した本をリストアップしながら(それは何と楽しい時間だったことか)、私はタイトルを考えた――【 LOVELY GREAT BOOK TOUR 】。ただのLGBT本だと思うなよ、ようこそ、愛しくも偉大な本の旅へ。――編集者からの「本を探し検索する人のことを考えると弱点になる」という意見でタイトル採用にこそならなかったものの、「自らLGBTという括りを捨て、固着したイメージを越えていく」という、そんな思いが共有されていたのだ。

先に「私の傲慢さゆえに身を退くことになった」と書いた。
「LOVELY GREAT BOOK TOUR」というコンセプト自体は良かった。イメージを共有して新しいものを作る仕事の喜びは他に代え難い。私が我慢できなかったのは、「リストの本を読み解説を書く」作業が編者でなく他の執筆者に任されることだった。私はそれを選書作業の途中で知らされたのである。私は「なぜおれに書かせないんだ!」と反発した。それこそが自分の仕事だと思っていたのである。その部分で自分が生かせると思っていたし、見たことがないような本にしてやると待ち構えていたのだ。しかし編者は選んだ本について書けないって?――膨れ上がった不満が、ある日ちょっとした言い合いで爆発した。私は未練気もなく身を退いて、二度と顧みることはなかった。献本があったのに、それさえ開封もせず8年間、放置していた。
それを先々週、何となく読んでみたのだ、何かの気まぐれのように。
おお「カミングアウト・レターズ」で始まるのか。私が選んだ本があるな。カニンガム入れてくれたんだ、よかった。ナーヴァは入らなかったか。レーヴィットもないか。遠藤まめた氏はやっぱり確かな書き手だな。ミナ汰さんこんな気持ちだったんだ。「夫夫円満」の書評はこの人で正解だな。やっぱり伏見さんの「さびしさの授業」は最高だろ。あれほど愛情に満ちた本もそうそうないんだよ。だからぜひ「欲望問題」も入れたかった。「パレード」は書評ですらないな、愛がないのに書いちゃダメだって。あ、こっちの本は評を書くの難しいんだよな、分かるよ。あああ「体の贈り物」で終わるなんてマジかよ、なんて、なんて嬉しいんだ!

私は編集者に言ったのだ、「LGBTの本をただLGBTの執筆者たちが紹介したリストにどんな価値を読者は認めればいいのか」という内容を、もっとずっと口汚く激しい言葉で叩きつけた。もちろんその時点で「どういう人々が執筆するのか」選定されていなかったのだから、これは実際に執筆に協力した人たちの不名誉ではない。そもそも私が書評を書いたところで私自身が無名であり何ら状況は変わらないのだけれど、企画をまとめ選書した編者たちではなく編集者が選ぶ執筆者が書評を書く方法では、全体の質を一定に保つことが困難になる。――だが、つまるところ、私の思いは「これはおれにしかできない仕事だ」という慢心であることに尽きたのだろう。あの時も、これを書いている今も、私にはハッキリと自分の思いが分かっている。ただ、本を読んだ今では「そんなことはなかったのに」と思うというだけだ。
本に対する愛は、多くの人々の中にちゃんとあった。
本を開いてみれば、優れた書き手も入り高名な執筆者もLGBTじゃない人もいて、編集者が執筆者集めに東奔西走したのだということがよく分かる。たぶんこれで正解だった――私なしで完成したその本は、隅々まで本への愛に満ち、温かかった。私は何を怒っていたのだろう。もっと話し合えばよかった、分かり合えばよかったのだ。苦さとすまなさがこみ上げる。
「LOVELY GREAT BOOK TOUR」に込めた私の思いは、完成したこの本にはそれでも/それゆえに少し相応しくないように、いきさつを知る私には感じられる。「爆弾が必要」と言った私に対して、この本は「爆弾なんて必要ない」と証明してみせたじゃないか。バクロニムで分解された「L/G/B/T」は、それで何が悪いのかと私の焦燥を笑いながら単なる「LGBT」に還り、輝いた。「LOVELY~」を使ってくれたのは、完成を待たず去った私に、それでも手向けてくれたスタッフの思いやりにすぎない。
私たちは単にLGBTの本を読みたいのではなく、良い本が読みたいのだ――しかし、もしそれが「良い本であり且つ、LGBTを扱った本なら」、どれほど感激することか。この「にじ色の本棚」もそういう役割を果たすだろう――人々に愛されたタイトルが並び、そこから力を得てきた多くの人が本に対する愛を語る、その光景の愛しさ、温かさ、頼もしさ。とても良い本だった。
最後まで関わればよかった。――これは、そんな私の懺悔である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
