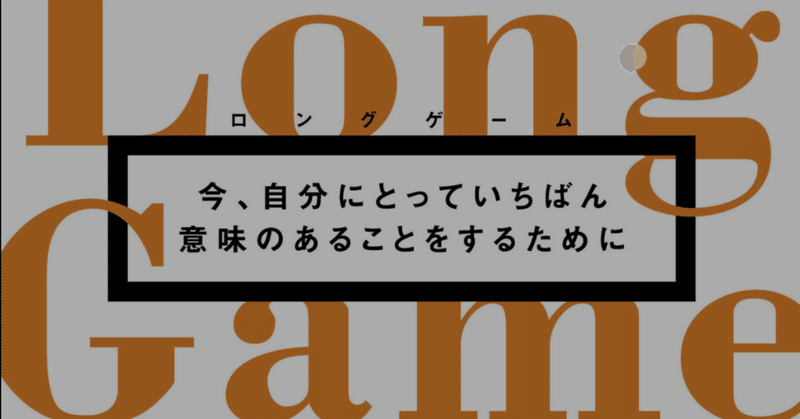
『ロングゲーム』要約
メンタリストDaiGoさんが『ロングゲーム』を紹介されていたので、気になって読んでみました。
最近、仕事で「ノー」と言えずに、難しい案件を引き受けてしまって、本当に必要な推進のための時間が作れなかった苦い経験がありました。
そこで「断る」ことも大事なんだと身に沁みました。
この本にも同じようなことが書いてあったので、全身の毛穴をむき出しにしながら読み進めてしまいました。
めちゃくちゃ今の自分に刺さる内容だったので、共有したいと思います‼️
『ロングゲーム』の前提
☝️「長期の思考」が大切。
☝️たとえどんなに小さな行動でも、たしかな戦略をもって毎日続けていれば、たいていのものは手にはいる。
☝️手に入る報酬はだんだんと増えるものではない。ある瞬間に一気に増えるものだ。
余白
すでに満杯になっているコップにそれ以上液体を注ぐことはできない。
つまり、自分の時間とエネルギーを賢く使いたいなら、ある程度の「余白」が必要。
なぜ私たちはこんなにも忙しいのか?
・仕事しているアピール。
・深く考えずに済む。
どうやら私たちはこの忙しい状態を密かに歓迎している。例えばアメリカでは、忙しいことは社会的なステータスの高さにつながる。「自分は価値のある人間だ」と思いたい気持ちが、忙しさを求める強力なインセンティブになっている。
忙しさにはどうやら麻酔のような働きもあるようだ。忙しく、仕事に集中していれば、直視したくない答えが出るような質問を考える時間がなくなるからだ。
魅力的なことに対しても「ノー」と言う
ロングゲームのプレイヤーにとって「ノー」という言葉は究極の武器。
断ることによって自分の時間を確保しないと、目標を達成することはできない。
しかし、私たちは「相手を失望させたくない」「否定的に受け取られることが心配」という理由から「イエス」の魔力に負けてしまう。
「ノー」というためのコツ:自分にそれをして欲しい理由について、相手に質問する
この質問をすることによって、
「それだけで引き下がる人」が一定数いる。
「自分がどれだけその人を助けたいと思うか」を決められる。
例えば、「ちょっと電話できない?」「ご飯行かない?」と声をかけられたら、すぐに応じるのではなく、「どうしたの?」と理由を質問する。
する価値があるか判断するときに役立つ4つの質問
1. トータルでかかる時間は?
2. 機会費用は?※人間の選択行動において、ある選択を行うことで失ったものの価値。
3. 身体的・心理的コストは?
4. これをしなかったら1年後に後悔するだろうか?
例えば、セミナーの依頼がきた場合、①トータルでかかる時間は5時間(計画1時間、準備2時間、本番1時間、アフターフォロー1時間)。②セミナーをすることで5時間分他の作業ができるな。③セミナーは緊張するから心理的に負担がかかるな。④とはいえ、若いうちに人前で話す機会を増やすことによって場慣れすることができるいい機会だから断ったら後悔するな。
集中
余白ができても、限られた時間とエネルギーをどこに集中するのがベストなのか。
「20%ルール」で革命と安定を手に入れる
「20%ルール」とは、自分の時間の20%を使って新しい分野に挑戦すること。
「20%」はその分野が自分に合っているか、大きな可能性を秘めているかを知るには十分な時間。一方、うまくいかなくても悲惨な結果になるほどの時間でもない。
「20%」でリスクをとって、イノベーションを起こしつつ、「80%」で家族が安心して暮らせる安定も手に入れる方法。
3M社はイノベーションと創造性のために15%の時間を使うことを従業員に推奨し、「ポスト・イット」が誕生した。
ポイントは、たとえその20%の新しい挑戦が失敗に終わっても、手ぶらでは帰らないことだ。
想定する結果は得られなかったとしても、「新しいスキルを身につける」「新しい知見を得る」「人脈をつくる」などの土産を持って帰る意識を持つ。
また、新しい分野に挑戦するベストタイミングは「今の分野でうまくいっているとき」だ。
切羽つまり、すぐに「次の何か」を探さなければいけないような状況になってからでは遅すぎる。
「自分が強いときにやる。弱っているときにはやってはいけない。」
「波で考える」ことにより成果を最大化する
成果を最大化するには「最も大切な一つの目標に全集中する」ことが大事。
自分の分野で成果を出すためにはキャリアを「学ぶ」「創造する」「つながる」「収穫する」という4つの波に区切って考える必要がある。
①学ぶ
学ぶこと(インプット)。
学ぶことは重要だが、それ自体は収入を生まない。
②創造する
インプットしたことをアウトプット。
波をおこしたいなら「自分のアイデアを創造してシェアする」ことが重要。
創造を通して自分の分野に貢献し、同じような考えを持つ人たちと出会う必要がある。
③つながる
正しい人とつながれば、サポートしてもらえる。
自分の声をもっとたくさんの人に届けられたりする。
内向的な人や一匹狼を自負する人など、他人と「つながる」ことに興味をもてない人もいるが、狭い人脈しかないことは、いずれ成長の足かせになる。
狭い人脈は「新しい考え方に触れる機会」「自分のアイデアが多くの人に届く機会」「ビジネスのコツを知る機会」が少なくなる。
なぜなら、見ず知らずの人にはそういったコツや考え方は教えないからだ。
時間を作って他者とつながり、新しいコミュニティに参加することは成功への大きな足がかりになる。
④収穫する
自分の分野である程度の地位を築いたら、努力の成果をゆっくり楽しむ。
収穫には賞味期限がある。
期限がきたら、また新しいことに挑戦し、新しい何かを創造しなければならない。
「戦略的レバレッジ」で効率的に成果を上げる
「戦略的レバレッジ」とは「1回の行動で10回の行動と同じ成果を出すにはどうすればいいか?」と考えること。
例えば、ブログにアップした記事を他のSNSを活用して拡散する。
私たちは「あと一手間」を惜しんでいる。
一つのことをするとそこで終わりにしてしまう。
しかし、1回の行動で2回以上の効果を出すことができれば、競争で優位に立つことができる。
信念
障害や挫折を乗り越えて、それでも前に進んでいくための「忍耐強さ」を手に入れる必要がある。
「失敗」を「実験」と捉える
フルコミットする前にテストする。
酷い作品や中途半端な作品なら、まだ世に出すべきではない。しかし、これがずっと続くようなら問題だ。
初期の段階ではすべてを「実験」と捉えることが大事。
失敗を恐れるのは失敗すればそこで終わりだと思ってしまうから。
「実験」であれば、どんな結果になっても失敗にはならない。
狙った結果が出るまでに何度も挑戦するのは当然のこと。
つまり、ほとんどの人が失敗だと思うものは本当は役に立つデータの収集にすぎない。
「長期の思考」を身につける
長期の思考を身につけるためのポイントは3つ。
①他の人よりも長い時間軸で計画立てる。
「3年単位の目標ばかり追っていると、たくさんのライバルと闘わなければならない。しかし7年単位の目標にすると、ライバルは激減する。なぜなら、そんなに先まで考える企業はほとんどないからだ。時間軸を伸ばすだけで、短期では達成できないような大きな目標に取り組めるようになる」
長い時間軸で計画を立てることで、他の人や自分の想像以上に遠くまで到達することができる。
②成功するまでに本当に必要な時間や努力を知る
他の人が成果を出すまでに3年かかったのなら、自分なら1年でできると思うのは間違っている。
③小さく始める
どんな目標でも最初からゴールを見ていると不可能だと思ってしまう。
目標を小さく分割して成功体験を積み重ねていけば、前に進む勢いをつけることができる。
確固とした「レジリエンス」が必要
レジリエンス=立ち直る力のこと。
新しいことに挑戦することは実験と同じ。
うまくいくかどうかはやってみないとわからない。そしてほとんどが失敗に終わる。
失敗のたびに意欲をそがれてしまっては目標を達成できない。
偶然や運、個人の好みなどが状況を左右する力は思っているよりも大きい。
成功するかどうかは「打席に立つ回数で決まる」といっても過言ではない。
そのためには、常にプランB(プランC、D、E)を用意して、うまくいかなかったときは「これはダメだったけれど、他の方法を試してみよう」と言える「忍耐強さ」が必要だ。
まとめ
「忙しい人」=「自分のスケジュールさえコントロールできない人」と考える。
「自分のスケジュールを適切にコントロールする」ために、何でもかんでも「イエス」と言わず、20%程度は「ノー」と断ることによって余白を作る。
余白ができた「20%」で「新しい挑戦」をする。
「新しい挑戦」をしたら、「失敗」はつきもの。
それを「失敗」と捉えずに、「実験」と捉える。
60%の合格ライン(α版)で「実験」を繰り返して役に立つデータを収集する。
「実験」を繰り返して、「打席に立つ回数を増やす」
「打席に立ち続ける」ために、常にプランB (C、D、E、、)も用意して、「これはダメだったけれど、他の方法を試してみよう」と言える「忍耐強さ」をもつ。
これが、成功するために大事なんだと勉強になりました。
最後までご覧いただきありがとうございます‼️ 「サポート」していただけると、子犬のように懐きます(笑)🐕 「フォロー」していだだくと、子猫のように懐きます(少し気分屋)🐈
