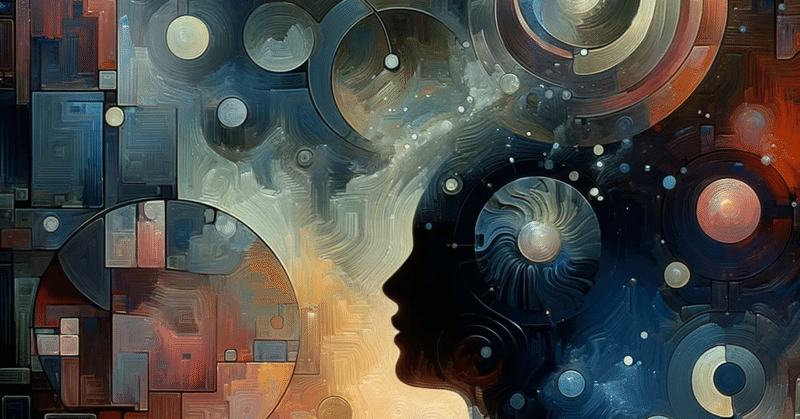
『痛みと悼み』 三十
あの家も、もう取り壊されているかもしれない。取り壊されて、分筆されて、小さな家がいくつも建って、あの家族の思い出は、跡形もなくなる。残されたのは、あのときに聡二さんが取りにきた、檀一雄全集の第6巻だけだ。その本は、かつての絶対的な神官に仕え続けた母が、一人寂しく暗がりのなかで、舟が頼る灯台のあかりのように手にしてきた本。そんな母がいて祖父が守ろうとした家は、今、無くなった。見事で完全な復讐。多恵さんの寂しさが伝わってくるように、それが自分の母の姿に共鳴して、急にめぐむの頬が熱く痺れる。その熱さに被せるように、聡二さんは結論めいたことを口にする。
「結局、僕も兄もそれぞれ期待を裏切って社会に出ると、復讐に自分が囚われるのを恐れて、自然と離れていってしまった。」
「その後、お母様にはお会いにならなかった。」
「祖父の葬儀の後、次第に疎遠になった感じかな。正確にいうと、母の方が会ってくれなかった。」
会ってくれなかった。多恵さんは、二人の息子を許さなかったのだろうか。でも、檀一雄を手にしていた母親が、その程度のことで、息子をそんな簡単に切り離せるのだろうか。
「お母様は、聡二さんを許さなかったということですか。」
聡二さんは、腕を組んで少し俯いて考え込む。それは、難しいナゾナゾを考える子供のように、懸命であどけなかった。
「まだ、僕にはわからない。特に僕が神学部を卒業して本当に牧師になったとき、母の静かな怒りはマックスになった。僕が家に近づくことさえ許されなかった。僕は、母が元気かどうか兄から伝え聞く程度しかなかった。でもその兄も、計画通りに疎遠になってたんだね。」
「でもきっと、お母様のお気持ちも、そんな単純なものではないような気がします。」
めぐむは、聡二さんの横顔に声をかける。
「母は、そんな態度で、僕に何かを伝えたかったんだと思う。そう思うと、暗がりで檀一雄を読んでいたあの姿が思い浮かぶんだ。」
母が示そうとした、単純な拒否や否定ではない何か。

「そのために、あの本が必要だと思って取りにお邪魔した。それが、あの本を欲しかった理由だよ。」
母が大事に一生抱きしめるように持っていた本の意味することは、無頼派と呼ばれる作家の無頼であることへの誠実さに関係するのだろうか。自分が大事に思う譲れないことに、誠実に向き合う。理解されないことであっても誠実に向き合う。逃げないこと、めぐむは何かを突きつけられているようで苦しくなる。顔を逸らすように、めぐむは言う。
「言いにく話をお話を聞かせて頂き、ありがとうございます。」
それを聞いて、聡二さんはニコリと笑う。
「君は、僕たちのようなことがないよう、お母さんとは仲良くしているかい。」
聡二さんがそういったとき、めぐむの耳の奥に、高い叫びのような悲鳴が響く。逆巻く波の轟音の間を、めぐむにはそれが泣いているようにも、めぐむを嗤っているようにも聞こえた。めぐむの頬に冷たい雨と涙の感覚が蘇り、避けてきた鋭い痛みが胸に走る。背後から突然に鋭い刃物で刺されたように。苦悶に歪む表情がおもてに出ていなければいいのにと、咄嗟に思う。しかし突然矢に射られた小鳥のように、めぐむは少し前屈みになる。目の前がぐらりと揺れたような気がする。
「大丈夫かい。」
聡二さんが心配してめぐむの肩を両手で支える。心臓の鼓動が激しくなり、聡二さんにも伝わったかもしれない。久しぶりのパニック症状。こんなときに。今の話のせいなのか。務めて呼吸に集中する。過呼吸にならないように、静かに悟られないように息を吐く。
めぐむはひきつったように微笑むと素早く軽く会釈して、急いで軽トラックが止めてある所に歩く。自分の足元に、意識を集中する。でも、その歩き方は、おそらく明らかにぎこちなかった。聡二さんも、気がついたはずだ。突然のめぐむの冷たい態度に、驚いたかもしれない。そう思いながら、余裕がないまま、足元に神経を集中させる。
