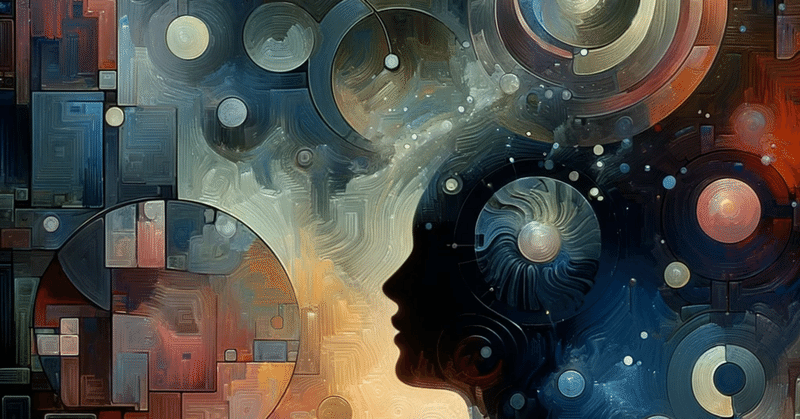
『痛みと悼み』 四十一
「その意味でも、兄も寂しい種類の人間かもしれない。ただ、兄は今はまだそんな自分を受け入れて、自分の足で立ち続ける強さを持っている。」
「それは、誰のため、何のためでしょう。」
「分からないなあ。だって、儲けたってその金の使い方が自分では分からないんだもの。」
聡二さんは、自分についた富永家の何かを確かめるように、両手を額にあててゴシゴシ擦り、そしてその手のひらを見て苦笑いをする。
「兄には、そんな金なら教会に寄付してくれよ、なんて冗談で言う。でも、嫌だってさ。ケチとかじゃなくて、多分、自分の金が教会や弟の思いを損なうかもしれないと思っているのかもしれない。恥ずかしそうに、そう言うんだ。兄弟だから分かるような気がする。」
「お金のために、働いているわけではない。」
「少なくとも、仕事を辞めても遊んで暮らしていけるくらいはもう十分に稼いでいるからね。だから、兄は、自分なりの訳があるんだろう。それは、人に言えない、何かの祈りのようなものかな。」
「祈るように、自分の業のようなものに魅入られながら、家庭も顧みずに働き続ける。」
めぐむは、広い机の上に、たくさんのモニターとそこに色々なチャートが表示された画面をじっと見つめ続ける瑛一さんの姿を思う。多分、部屋には、世界中から響く静かな絶望的な悲鳴と強欲の歓喜が何かの電気信号になって、モニターに表示されているんだろう。
「それほどまでに、少なくない犠牲を払った、膨大で寂しい資産だ。」
聡二さんが、天を見上げる。瑛一さんのために何かを祈っているよう。双子の兄弟、似ているようで似ていない、似ていないようで似ている兄弟。寂しかった母とそれを分かっていながら離れていった双子の兄弟は、今、何を考えているのだろう。
「聡二さんは、その寂しさを分かってあげられるんだったら、瑛一さんと一緒に、お母様に優しくしようと思わなかったのですか。」
めぐむは、その言葉に、口の中に血の味が広がったように思う。それはめぐむ自身への非難。天井を見上げていた聡二さんは、視線を落として、めぐむの顔をじっと見る。意味を理解した上で、答える言葉を慎重に整理するように、微笑みながら静かにじっとめぐむを見つめる。
「もっとやり方があったと思う。」
それだけ言うと、聡二さんは黙り込んむ。生きているときはできなかった優しさ。母の寂しさを分かって、私はもっと優しくできなかったのか。めぐむの求め続ける答え。
「でも、そのやり方の答えなんかないのかもしれない、答えのない問いを、間違った自分を抱え続けるんだ。」
聡二さんが続ける。
「若葉さんと啓介くんはね、親御さんからひどい扱いを受けた。そのため、公的に、親御さんと引き離されるという、つらい別れ方をしたんだ。それ自体は、そのときには仕方がないことかもしれない。でも、あの二人は、それが自分のせいだって思っている。なぜなんだろうね。」
めぐむは聡二さんを見る。
「二人は言うんだ、自分がいけなかったんだって。それが正しいことなのかどうか、僕にはわからない。でも、そんな二人が一緒になること、そしてそのいけなかったと思うことを共有する勇気を、僕は褒めてあげたいと思う。そして。」
息継ぎをすように聡二さんが続ける。
「僕も間違った。兄も間違った。二人とも、それをこれからも抱えていこうと思う。誰にも隠さず、みっともなくてもね。兄もそう思ったみたいだ。あんなに切り捨てるようにいっていたあの家の処分も、思いとどまったらしい。」
「でも。」
あの段ボール箱は処分されてしまったのではないか。
「君の会社に預けてある荷物も、兄が引き取りに行った。兄も、あのメモを見て、何かを許そうと思ったのかもしれない。そして、自分の失敗を見つめ続ける覚悟ができたのかな。だから。」
めぐむがアゴをあげる。
「君が、もし、自分の過去の何かを押し殺そうとしているのなら、そんな必要はないと思う。」
聡二さんはやっぱり見ていたんだ、めぐむが真っ青な顔で軽トラックに乗り込もうとしたあのとき、そこにあった影のようなものを。
めぐむは、押し殺そうとしてきた冷たい雨に彩られた黒い塊の正体を、思い出そうとする。音が消えてゆき、体の芯から身震いがする。
誰もいなくなった二人だけの教会の、静かな空気の流れる音だけが聞こえるような気がする。

同じ問いを突きつけられる聡二さんとめぐむ、そして、その問いから逃げるように走り続けた瑛一さん。呪縛のように、同じ言葉を吐き続ける富永兄弟の母多恵さんとめぐむの母藍子の幻。
めぐむは、空気の流れる音にたゆたう。
私の人生は失敗だった、あの悲しいメモの意味。それは、自分自身への悔悟なのか、二人の子供への詫び状なのか。分かることは、静かに誰かに伝えたかったという多恵さんの気持ち。
何も残せなかった母藍子は、死の間際、何を思ったのだろう。自分が事切れる瞬間まで、その死を待ち侘びていたようなあの人は、私に何を求めていたのだろう。あのとき、幼い私に何ができたのだろう。
今なら聞いてみたい。今、じっと静かになって、酒に逃げることもできなくなって、どんなに望んでも悪い事もできなくなった幻になった母に。今、広い海のどこかに、白い魚たちとともに静かに横たわっている、深海の冷たい水の流れに漂う母の白い骨片を思う浮かべる。
それは、今まで蓋をしてきている記憶。
あの遺骨を受け取った日の冷たい雨の感覚が蘇る。
冷たい雨の記憶。
母の死を知らされて検視の後で荼毘に伏されたという母を警察で受け取った日だった。めぐむが渡されたのは、小さな白い骨壷の入った白い布で包まれた木箱だった。母を確かめるように、両手で抱えて中の重さを確かめた。
