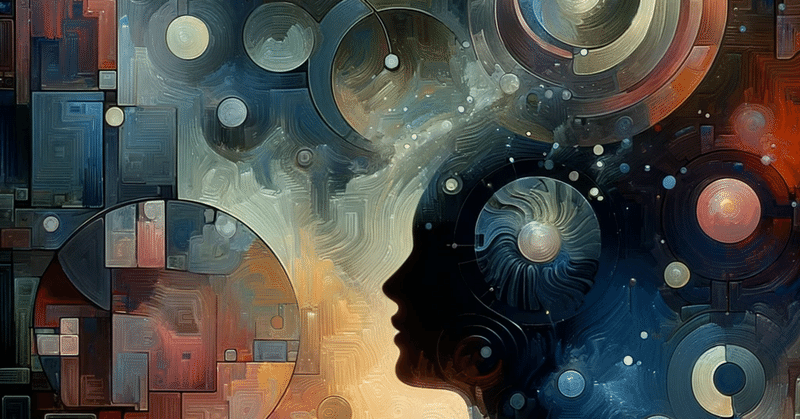
『痛みと悼み』 九
イスは、正面に見えたテーブルの一番奥で、弾かれたように一つだけ離れた位置にある。何かを思いついて、突然立ち上がった勢いで後ろに弾かれたように、テーブルに対してハスに構えている。それは、ビリヤードで最後にたまたま当たった玉が、思わぬところに運んでいかれたような唐突感、イス自体も呆然としているように見える。その呆然とした瞬間を捉えるように、足元に、小さな黒い影が見えた。黒い影。めぐむの心拍数が跳ね上がる。この1年半の現場作業でもう慣れてきたと思っても、ほんの僅かでも身構える集中が切れたとき、突然、フラッシュバックのように文化住宅の母の黒い跡が蘇る。走ってその場から逃げ出したくなる。めぐむは古代ギリシャの兜のように、目深にキャップ帽を被りマスクで目元しか見えない顔を意図的に凍らせる。そうして、自分の感情を押し殺して自分に暗示をかけるように平静を装う。駆け出しの研修医が、赤い血に慣れた優秀な外科医のように振る舞う。でも、隙を見つけて、その血の色はめぐむのまだ治りきれない肌を切り裂く。今までも、何度もあったこと。でも内面のめぐむの動揺に、菰田社長も気づかない。
「このイスで意識を失って、床に倒れ込んだろうと、警察の人の説明だった。」
男性は、スリッパで床に引かれた木製タイル−よく使い込まれ、長いときの経過で上品な木目の色を浮かび上がらせている−を足の裏で撫でた。しかし、そのスリッパは一ミリともその黒い影の部分には近寄ろうとしない。それは男性の、痕跡であっても母の物には近づかないという硬い何かの決意を感じさせる。
「警察の検証では、特に病変はなかった。外傷も持病もない。突然の心不全。何かをしようとして突然に立ち上がったところで、心臓に負荷がかかった。そこで意識を失い、倒れたんだろう。高齢者にはあり得る話らしい。」

めぐむは、キャップ帽の下の目だけで男性の説明を聞く。この男性の母親なら80歳を超えているだろう。でも、持病もない健康な体、まだ、自分自身も余命はあると思っていた。なのに、突然、訪れる終焉。人生は、常に私たちの予測を裏切る。
めぐむは、テーブルの上を見る。散乱した様子はない。広いテーブルの短い辺の中央の一箇所のみ、その弾かれた椅子のもともとあった所定の場所だけが使われていたのだろう。そこはめぐむたちが入ってきた部屋の入り口に向かう正面に位置して、まるで入ってくる者の身体検査をする保安検査場のように見える。新聞などもテーブルの上にきちんと整理され、数日分だけが見返すためなのか、脇に置かれている。いくつかの種類のメガネや拡大鏡のほか、使い込まれた辞書、そして、会社四季報と数冊の経済誌のようなものがその新聞の左右にテーブルの形と相似形の証明をするかのようにバランスの取れた位置に置かれている。興味のあることについてはあらゆるものを見ようとする、細部とバランスにまでこだわるこの家の主人と、限られた興味の対象が目の前に示される。それを見るめぐむに、つぶやくように男性がいう。
「母は、昔から投資が趣味でね。趣味というより、人生そのものと思っていたのかも。そして、子供たちも投資の対象だったのかな。」
自嘲気味にいう男性から、初めて、感情の揺れを感じる。それは、投資に結果が伴わなかったと思う自嘲からなのか。それとも、この人は、自ら選んで反発して期待を裏切ったのだろうか。人生は予測を裏切る。この人は、母から期待され、母のそれを裏切り、今も引き摺っているのだろうか。光を柔らかく反射する高級そうな濃紺のスーツの生地からうかがわれるこの男性の暮らしと私とでは住む世界が違うのに、ある意味で共通の後ろめたさを抱えているように思う。
「では、このお部屋をきれいにさせて頂き、残ったお荷物などは段ボールに仕分けしておけばよろしいですね。」
