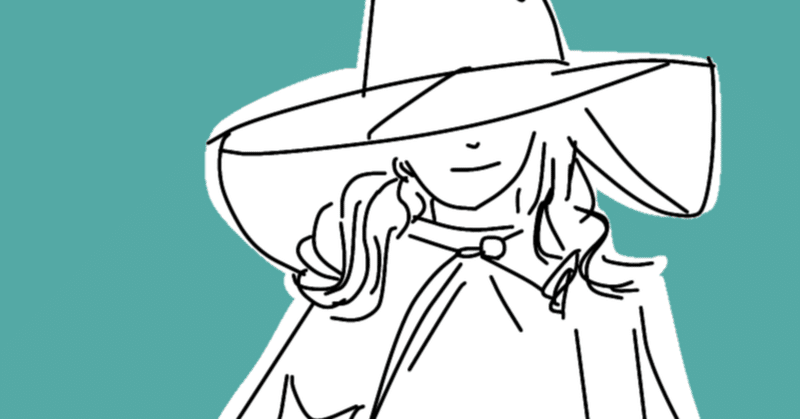
「男だったら言われないのに」というフェミニストの下らなさ
何か非常に不快な言葉を投げつけられて「男だったら言われないのに」と憤慨するフェミニストが居る。まぁ、それ自体は別に構わない。不快な言葉を不当に投げつけられて怒るというのは正当な怒りであるし、不快な言葉を不当に投げつけた人間に非があるのは疑い得ない。
しかし、フェミニストの考え方がおかしいのは、そこから飛躍して「男性だったら言われない言葉を女性である私は投げつけられた。だから、女性は男性よりも差別されている」と認識してしまうことにある。
もちろん、女性に投げつけられた言葉の内容が指し示す局面や、まさに言葉を投げつけられた局面自体に限定すれば、それらの局面に関しては「女性差別がある」と考えることは間違いではない。しかし、そこから総体的女性差別社会と認識することが所が飛躍しているのだ。
このフェミニストのおかしさについて、原理的な話をしよう。
■当事者性をもった「もしも自分と異なる性別であれば言われないのに」との感想を抱く体験の構造
男性ジェンダーと女性ジェンダーが分かれている社会においては、それぞれのジェンダーに適用される規範が異なっている。すなわち、男性限定で適用される男性ジェンダー規範は女性に適用されないし、女性限定で適用される女性ジェンダー規範は男性には適用されない。
したがって、男性ジェンダーと女性ジェンダーが分かれている社会においては、男女それぞれはそれぞれのジェンダーに対応したジェンダー規範から逸脱した場合にその各々のジェンダー規範からの逸脱を咎められることになる一方で、他方の異性限定で適用されるジェンダー規範に逸脱していても咎められることはない(註1)。
このとき、男性が男性限定で適用されるジェンダー規範から逸脱した場合に咎められたケースにおいては、男性は「女性だったら言われないのに」との感想を抱く経験をする。また同様に、女性が女性限定で適用されるジェンダー規範から逸脱した場合に咎められたケースにおいては、女性は「男性だったら言われないのに」との感想を抱く経験をする。
つまり、男女双方が「もし自分が他方の性別であれば、言われないのに(=咎められないのに)」という体験をしている。
そして当たり前の話ではあるのだが、人生のある時点で性別を変更するトランス女性あるいはトランス男性でもない限り、男性は自分に対する叱責に関して「男性だったら言われないのに」との感想を抱く体験はしないし、女性もまた自分に対する叱責に関して「女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験はしない。
つまり、男女双方が、他方の性別限定で適用されるジェンダー規範に照らしたならば逸脱行為となる自分の行為に対しては、その行為がジェンダー規範からの逸脱であるとして叱責されることは当然ないので、自分事として「もし自分側の性別であれば、言われないのに(=咎められないのに)」との感想を抱く体験は原理的に出来ないのだ。
この構造は、自己の痛烈な感情を伴う体験としての「もし男性だったら言われないのに」あるいは「もし女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験について、個々人の内面における非対称性が存在することを意味する。
つまり、男性であれば「もし女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験は自分事であるが、「もし男性だったら言われないのに」との感想を抱く体験はあくまでも他人事として存在する。また同様に、女性であれば「もし男性だったら言われないのに」との感想を抱く体験は自分事であるが、「もし女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験はあくまでも他人事として存在する。
このことは男女双方に関して、自分の内面における感情的インパクトを評価軸とした、「もし女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験と「もし男性だったら言われないのに」との感想を抱く体験の評価について、自分事として体験する「もしも自分と異なる性別であれば言われないのに」との感想を抱く体験の方が、他人事として体験する「もしも自分と同じ性別であれば言われないのに」との感想を抱く体験よりも、比較にならないぐらいに重大な体験となるのだ。
したがって、フェミニストがその妥当性に関して検討・吟味しているのかアヤシイ場合が少なくない、当事者性をもった体験というフェミニズムで重視される社会問題の認識の手段は、ジェンダー規範が押し付けられるという問題の男女の差異に関する認識において、「もしも自分と異なる性別であれば言われないのに」との感想を抱く体験の方が原則的に重要度の高い体験と評価してしまい、原則的に「自分の性別側の方が他方の性別側よりも強力にジェンダー規範が押し付けられている」と認識させてしまう構造を持っているのだ。
■当事者性をお題目とした自分の感情的インパクトの大小だけから判断する陥穽
ジェンダーレス的価値規範を自らの社会の規範とした現在において、男性に男性限定のジェンダー規範が適用されること、あるいは女性に女性限定のジェンダー規範を適用されることに対して、それらは「ジェンダー差別」という問題の現象であるとの認識が為されることとなった。
しかし、かつての男性ジェンダーと女性ジェンダーが分かれている社会において採用されていた、それぞれの性別に限定して適用されたジェンダー規範が、もはや時代遅れの規範となっているにも関わらず、それぞれの性別に適用されて、それぞれの性別限定で逸脱行為とされる行為に対して、叱責の声が飛ぶことがある。そして、その叱責の声に対して男女双方が自分事あるいは他人事として、「もし男性だったら言われないのに」あるいは「もし女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験をする。
もちろん、当然それらは「ジェンダー差別的体験」である。
残念ながら我々の社会は過渡期にあり、それらのジェンダー差別的体験をしばしば当事者として経験することになる。直接的に叱責を受ける側として、あるいはその場に居合わせる目撃者として、我々は「もし男性だったら言われないのに」あるいは「もし女性だったら言われないのに」というジェンダー差別的体験の記憶を蓄積していく。
このとき、当事者としての自分の内面における感情的インパクトを評価軸とした、「もし女性だったら言われないのに」との感想を抱く体験の評価と「もし男性だったら言われないのに」との感想を抱く体験の評価とに基づいて、「今現在の自分を取り巻く社会のジェンダー差別の状況」について無反省的に判断したらどうなるであろうか?
すなわち、常に「もしも自分と異なる性別であれば言われないのに」との感想を抱く体験の方が重大な体験となってしまう構造に関する自覚も無く、自分の感情が揺れ動いた記憶に基づいて「今現在の自分を取り巻く社会のジェンダー差別の状況」を認識したらどうなるだろうか?
そのような認識においては、自分と同じ性別に対するジェンダー差別的状況についても、自分と異なる性別に対するジェンダー差別的状況も正確には認識できない。そして、「もしも自分と異なる性別であれば言われないのに」との感想を抱く体験の方が感情的インパクトで判断して原則的に重大な体験となるのだから、自分達の性別側が酷い差別を受けていると判断してしまうのだ。
フェミニズムがその妥当性の検討も等閑にして「私がエビデンス」といったセリフと共に、当事者性という葵の御紋で自分の主観だけによる認識を無反省に正しいと考える、その認識枠組みによって、自分事の方が他人事よりも重要に感じるという当たり前の構造から最初から結論は決まっているのだ。すなわち、「(相手側は大したことがないのに)自分達の性別側が酷い差別を受けている」という、「自分は悪くなくて相手だけが悪い」といったフェミニズムお決まりの認識が繰り返されることになるのである。
つまり、他人事より自分事の方が自分にとって重要に感じるという、極々当たり前の人間の心理機序を、フェミニズム思考によって「社会において重大であるから私はそう感じたのだ」と認識し、その認識に基づいて「(常に)女性は差別されている」と騒ぐという下らない茶番劇を演じるという陥穽に嵌るのである。
■社会問題の性質とフェミニズムの認識枠組みの不適切さ
自己の内部世界だけで完結する問題を思考しているならば、主観オンリーの判断でも問題は生じないかもしれない。しかし、自分とは異なる他者が関係してくる社会問題においては妥当性の検討もなく「自分の主観ではこうだから!」で押し通せない。
もちろん、自分の主観と他者である相手の主観が偶然に最初から一致することは有り得る。その場合は、お互いの見解が一致するので、「(自分の主観では)この問題はこうだから!」という見解はお互いにとって異議は生じない。
だが、議論が為される場合とは一般的に見解や認識が一致していないからこそ議論が為されるのだ。とりわけ「社会問題」が議論される場において最初から自分の主観と他者である相手の主観が一致することを期待することは基本的に出来ない。それというのも、大抵の場合にそれぞれの主観による認識が異なっているからこそ「社会問題」として噴出しているのだ。
社会問題は、それぞれの主体の主観による認識が異なることによって解決困難性が生まれている問題、すなわち「一方がよい、あるいは問題が無いと思っていることが、他方にとって悪い、あるいは問題があると思っていることになっている事態」によって生じている問題なのであり、単なる技術的課題ではない。もしも、社会の構成員の主観の意見が一致している(※間主観性で考えると限りなく客観性に近い)にも拘らず社会においてなにか問題があるのであれば、その問題は「なぜ認知症を完治させることができないのか」といった問題や「なぜ現時点で核融合発電は実現していないのか」といった問題と同種の技術的課題なのだ。
したがって、社会問題に関する認識は、関係するそれぞれの主体の主観が(なにがしかの部分に関して)異なっているという認識からスタートする必要がある。そして、「ジェンダー差別」という問題は、そのようなそれぞれの主体の主観の認識が異なる社会問題なのである。それゆえ、妥当性の検討も無く「自分の主観ではこうだから!」という主張を押し通して問題の解決を図ることはできない。
さらに非常に根本的な話をしよう。
無条件で「自分の主観ではこうだから!」という認識が正しいとしたとき、自分と他者の主観での認識が両立不可能な形で異なっている場合において、どちらの認識が正しくなるだろうか。
たとえば、人物Aの主観による認識と人物Bの主観による認識がそのような両立不可能な認識であったとき、Aの視点でもBの視点でも「自分の主観による認識が正しく、相手の主観による認識が間違っている」となる。「『自分の主観ではこうだから!』によって正しくなる」とすればAの認識もBの認識も正しくなるが、Aの認識とBの認識が両立不可能な認識なのだから矛盾が生じてしまう。
それゆえ、矛盾した事態が同時に成立することはあり得ないのだから、それぞれの事態の前提が間違っているのである。つまり、「『自分の主観ではこうだから!』が無条件で正しい」とする前提が間違っているのだ。
とはいえ、フェミニスト達はこの矛盾に気づく様子がない。両立不可能な主観による見解が出る社会問題において、彼女らは「主観からの見解が(無条件に)正しいのだ」と嘯く。「ある前提から矛盾が導き出されたら、その前提は否定される」という、「最大の素数は存在しないことの数学の証明」でお馴染みの矛盾律もなんのそのといった態度である。
では、なぜフェミニスト達は「主観からの見解が(無条件に)正しいのだ」との前提が矛盾を導き出すにも関わらず、平気で正しいと認識できるのだろうか。
種明かしをするとツマラナイ話なのだが、フェミニズムは「女性側の主観からの見解が正しく、それと対立する主観からの見解は間違い」とする枠組みを置いているから、「主観からの見解が(無条件に)正しいのだ」との前提は(ほぼ)矛盾を導き出さないのである。結局のところ、最初から結論の決まっている「女性の主観的な見解は正しい」という宗教と同じ認識枠組みをもっているからこそ、彼女らの信念体系において矛盾が生じないのである。
一神教における「神は間違わない」という信条の「神」の部分を「女性」に入れ替えれば、フェミニズム思考の一丁挙がりである。そして、そんなフェミニズム信仰を共有できない人間からすると、フェミニストが社会問題について何か妄言を垂れ流したところで、フライング・スパゲティ・モンスター教の司教の聖句と何ら変わる所が無い。
実に下らない話である。
註1 もちろん、男性ジェンダーと女性ジェンダーが分かれている社会においてもジェンダーに関係のない社会規範は存在するし、それから逸脱すれば当然ながら男女関係なく咎められる。また、男性と女性で価値が傾斜しているジェンダー規範も存在する。すなわち、女性よりも男性が逸脱した場合に厳しく咎められるようなグラデーションをもったジェンダー規範もあれば、その逆に男性よりも女性が逸脱した場合に厳しく咎められるようなグラデーションをもったジェンダー規範もあるだろう。だが、そういった規範のバリエーション問題を考慮しても、本文の内容は変化しない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
