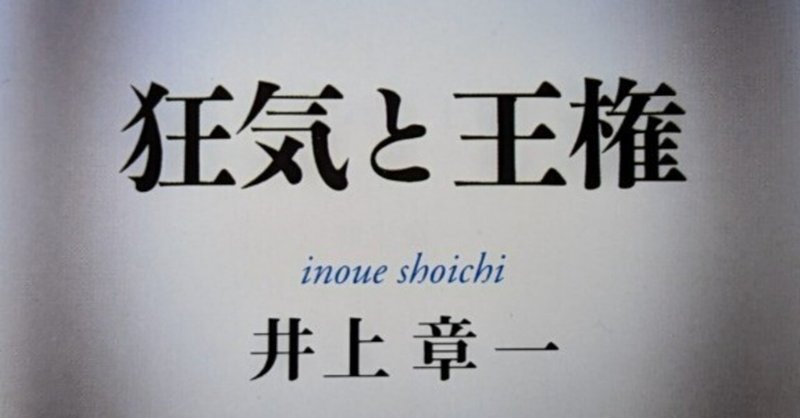
【本002】井上章一『狂気と王権』
1923年12月27日、第48帝国議会の開院式に向かう摂政裕仁(のちの昭和天皇)を狙撃した男がいた。
その―元の持ち主は伊藤博文であるというステッキ式散弾銃から発射された—弾ははずれ、裕仁は何らの傷を負うことはなかったが、彼は刑法(当時)第73条の大逆罪によって起訴され、大審院にて死刑判決が言い渡された。
アナーキスト、難波大助である。
ふとしたことから、難波大助について追ってみようと思った私が手に取ったのが、本書、井上章一『狂気と王権』である。
本書の主要なテーマは「精神鑑定のポリティクス」である。
本書では、検察側が難波大助を精神鑑定にかけ、「精神病」(ママ)であったということにして減刑、事実上の無期懲役とする計画があったことが示唆されている。
しかしながら、鑑定を行った医師呉秀三は難波の精神状態を「正常」と診断し、検察側の思惑は大いに狂い、また難波もいっさいの反省の態度も見せなかったため、死刑判決が確定した。
これを筆者の井上氏は「検察は裁判には勝ったが、勝負には負けた」としている。
では一体なぜ検察は「難波が狂人である」ということを「立証」しようとしたのか。
本書ではその理由を、幸徳秋水ら12名が死刑となった大逆事件で、当初24名が死刑を宣告されていたものの翌日に「天皇のご慈悲」によって12名が無期懲役に減刑されたことを引き合いに考察している。
その他、元女官長の島津ハルが祈禱師とともに不敬罪に問われた事件を題材にした「オカルティズムと宮廷人」、大津事件をとりあげた「ニコライをおそったもの」など、大変興味深い文章がならんでいる。
ぜひ、第一章から順番に読んでいただきたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
