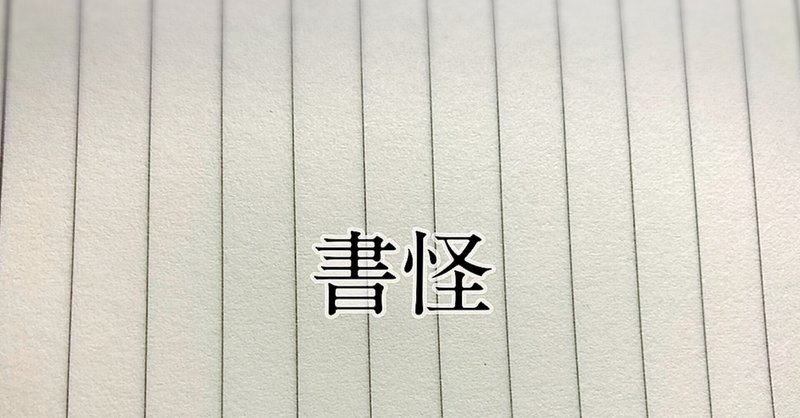
【創作】書怪
30週目の1文、”黒いインクの文字を食らう。”(2021/07/30)から。
「ぼく、本がすきだと言ったでしょう」
彼は気味の悪い笑顔をうかべていた。
これは、私が小説の新人賞をもらったばかりの頃で、日本中の人々が金持ちで、後先考えずに消費するような(実際、多くの者がそうであった)、バカげた時代の話である。
私はひとり、自らを祝うためバーへくり出した。未成年に間違われたりするので、ふだんはあまり近づかなかったのだが、念願の小説家というステージに立てたのだから、飲みたくてたまらなかった。眉を隠す前髪を持ち上げ、横髪もワックスをなでつける。うかれた学生に見られないように、おちついた男としていれるような、ブラックスーツ。シャツはダークグレー。ノーネクタイで、シャツのボタンを2個開けておく。
声をかけられて、一夜。いや、うまくいけばその後、交際につながるかもしれない。若い私は、そんなことも期待していた。
いい男(おとな)は、多くを語らず、背中で知らしめるのである。私はそう信じてならない人間であった。バーでは、カウンター席にかぎる。バーテンダーのいる中央から離れて、店を見渡せる奥のスツールに腰かけた。バーテンダーに「バーボンをロックで」と伝える。夜のおとなの社交場に行きなれてないことを隠すため、私はひかえめに笑う。相手のほうは気にするようすもなく、塊のような氷を入れ、ロックグラスに酒を注ぐ。ほんの少しの量の液体が入ったものをよこしてくる。真顔で相手を見るも、ほかの客のため酒を用意している。グラスを回すと、カラコロと氷が鳴った。
私が期待していたような出来事は一切起こらず、背中を丸めてちびちび飲むしかなかった。スーパーマーケットで、幾度も年齢確認のために運転免許証を見せている私は、酒とは縁遠い者だった。いちいち訊かれるのが面倒で、買って帰ろうとも思わないのだ。酒になじみがうすい私は、頭がぼんやりとしてきていた。熱っぽくふらつく頭を、肘のついた左手で額にふれて、支える。男女の言葉遊びが、ささやくような音量で耳に届いてくる。みじめである、とても。
「となり、よろしいですか」
頬杖をついて、相手を見上げる。オールバックによって目立つ、男らしい眉が印象的な人。それが、彼であった。アルコールの熱により、思考回路が正常ではなかった私の返事を無視して、彼はとなりの席に座った。上品に感じさせる三つ揃えで身を包んでいること、同性に対しておだやかな笑みをうかべていること、しかも初対面の相手であること、それら理由が重なり、男色かと勘違いしていた。そのため、私の表情はそうとう険しいものであったと思う。逃げ出したかったのだが、酔いによって踏ん張れなかったので、尻はスツールの上にあった。まことに情けないかぎりである。
「キミ、このあいだ小説の新人賞をとった子でしょう」
「え。なぜ、それを」
整った白い歯にまぶしさを感じながら、頭を支えつつたずねる。私よりも十ほど年上そうな彼は、グラスを置いて微笑んだ。
「ぼく、本がすきなんですよ」
「本……」
読書が、ではなく? 文章を書き連ねる人間として、妙な言い方だなと思った。私であったら、セリフをそのように記さないな、と。
バーカウンターのむこう、店の気合の入った酒瓶、ラベルたちを瞳に写す。夜に開かれる室内の独特な、淡いオレンジ色の光で、スーパーマーケットで売られている飲料とは違った輝きを放っている。酒瓶は、複数の照明……光量の少ない場所で、人間を惑わす灯火。
「酒瓶は、灯火か。なにか使えそうだ」
私はジャケットの内ポケットから、手帳を取り出した。若い頃から、中年になった今も変わらず、思いついた文章や表現、ときにはタイトルまでを、書きつけるくせがあった。
「キミ、ぼくのことを忘れていませんか」
「ああ、すみません。なにぶん、バーに来たのが久しくて」
拳を自身の高い鼻によせて、彼はハハハと笑った。肩をふるわせ、目尻には涙をためる。そんなに、おかしいものであったろうか。齢は二十歳をすぎており、立派かどうかはともかく、成人している。とはいえ、静かに酒を嗜む場が心から遠い私は、顔を赤くした。ロックグラスについた水滴の流れを追う。小説を描くことに没頭する前から、おとなしく物を眺めることがすきであった。
「失礼。気分を損ねさせてしまいましたか。キミは、マイペースでおもしろい男ですね。だからこそ、ほかの新人よりも優れていたのでしょう」
一拍おいて、彼は琥珀色の液体をうまそうに飲む。女のように長いまつげが、影をつくる。話しかけられてから、うすうす感じていたが、男の私から見ても美形であった。ドラマから抜き出てきたような容姿である。合コンの席で、共になりたくない。かっさわれるのが、目に見えている。
そこまで想像して、私は3杯目のバーボンをあおった。グラスが空になったので、みじめな男らしく、もう帰ってしまおう。それに、私が新人賞を獲得したことを知っている人(同性だが)もいたのだから。
「そうだ。サインもらえませんか」
カウンターに右手をついて、立ち上がろうとしていた私をとめるように、彼がサインをこうた。まだ作家とも言いづらい立場の私にとって、ききなれない単語であった。ゆえに、脳の伝達速度が遅くなって、脚に力が入らず、ふたたび着席せざるをえなかった。ふにゃふにゃとうずくまり、また頭を抱える。
「ぼくがサイン第一号ですかね。さて、どれに書いてもらいましょう」
了承と思ったようだ。カバンもない男の様相に、ほぼ一般人の名前入りにして良い物などないだろう。私が持ち合わせている物より高額な品ばかりで、価値が下がるに決まっている。彼がなにか見つける前に、バーから去ればいいものの、ぐわんぐわんと脳内が響き出して、身動きできない。
よほど見苦しいようすだったのだろう、バーテンダーが氷水の入ったグラスを私に差し出した。「すみません」とぼそぼそ声で礼を言い、受け取る。私が口づけたのを確認すると、べつの客のほうへ行く。こちらに気づいているわりに、相手にされない。水やりのときにだけ世話される、観葉植物になった心地だ。
「情緒を感じませんが、ノートにサインをいただけませんか」
スラックスの尻ポケットに入るサイズの、黒いシンプルなノートを広げた。罫線もない、無地の白がそこにあった。目に映えるページをつい、じっと見ていると、書かなければいけないような気がした。私は、愛用しているゲルインクのボールペンをノックする。有名人のような、シャレた文字など書けない私は、作家としての名前を丁寧に記した。
「キミの味、ぼくは期待していますよ」
彼はまた妙なことを言う。変な言い回しである。しかし当時の私は、作家のつくる趣きを指しているのだと解釈した。
それから、数ヶ月後。私は担当するという編集者の紹介で、またバーで出会った彼と再会した。「本のすきな、会社の株主のひとり」であった。私の物より上質そうなスーツであったのは、資産家であるからか。彼はやはり、高級そうな三つ揃えであった。
彼の家に招かれ、担当はポケベルが鳴り、席を外した。
「ぼくの書斎を案内しましょう」と言われ、私はおとなしくついて行くほかなかった。なぜなら、居住しているアパートの1フロア以上ある屋敷に、残されるわけにはいかず、そしてサラリーマンよりも遊ぶ金のありそうな男の提案を断る勇気はなかったのである。この選択は間違っていなかっただろう。
「ほんの一部ですが」
紹介された書斎は、20畳ほどの広さであった。壁一面、本棚。天井につくまで本を埋め尽くされている。芳香剤も、彼は香水もしていないので、純粋な書籍の匂いがした。古いのも、新しいのも、混じっている。この部屋は窓がなく、居心地が良いとも思えず、圧迫感がある。かるく頭を左右にふる。
しかし、「本がすき」という彼が、どんな小説を読んでいるのか気になり、思い切って本棚に近づく。
そこで不思議なことに気がついた。ハードカバーも文庫本も、背表紙にタイトルと著者名が記載されていないのだ。単なる印刷ミス? いや、それはないだろう。となりの本も上下の本も、そしてそのとなりの本もその上下の本にも、なにも書かれていないのだ。一冊、本棚から抜き出して、文庫本のページをめくる。一文字も印刷されていない。本の形をしたノートを、大量に所有しているのか。「本がすき」イコール「読書すき」とはならないようだ。ではなぜ、彼は私を書斎という場所へ案内したのだろう。べつに私はマニアではないのである。ノート収集家なら、どうして文具メーカーの株ではなく、出版社の株を保持しているのだろう。
サァーとページを飛ばしていき、奥付にたどりつく。
「『小泉八雲集』? ……昭和五十年発行」
最後のページだけ印刷されていた。ぽつんと取り残されている。手をうしろに組んだ部屋の主が言う。
「ぼく、本がすきだと言ったでしょう」
彼は気味の悪い笑顔をうかべていた。おだやかな表情しか見たことがない私の足がすくむ。彼が立つ奥の本棚には、酔っていたものの真面目に書いた私のサインが、立てかけられていた。
「キミの味は若者らしく、甘い。ですが、ほろ苦さもあり、まだ完成されているような出来ではありませんでした。しかし今まで味見してきた新人のなかでは、良い味でした。これからに期待ですね」
ひとりうなずき、私に話しかける。だが、さっぱりなんのことかわからない。
「バーでお会いしたときより、まぬけな顔をしていますよ。キミ」
おもしろいことはなにもないのに、おかしそうに声を上げる。腕を伸ばしてノートを取る。私よりもおとなの男を何年もしているだろうが、その動作はこどものように見えた。
彼がこちらをむいた。ノートのサインを親指と人差し指でつまむ。するすると文字が、うき出てくる。黒いインクが抜き取られ、紙から離された。アニメーションなのか、マジックに引っかかっているのか。彼は大道芸人が剣を飲み込むように、天を仰ぎ、口を開けて文字をそのなかへ入れた。口がもごもごとしている。それから水分が食道を通ったらしく、喉仏が動き、ごくんと鳴らす。
「……うん。あの日、キミはバーボンを飲んでいたようですね。氷が溶けて、味が薄いですが」
私のサインしたノートは、白紙になっていた。こすれやすいゲルインクの跡も消えている。手から『小泉八雲集』だった本が、滑り落ちる。床に敷かれた絨毯に当たって、パサリと軽い音がした。
「ぼくの食事には、良質な物語が必要なのですよ。キミの描く小説は、きっと到達してくれるでしょう」
目を細めて笑う。彼は人間ではなく、人の形をしたなにかであった。屋敷の一歩外に出ると、好景気で踊り狂う若者たちが、たくさんいることだろう。でもそんな若者たちと同世代の私は、世間とかけ離れた場所で、偽人間と共にしている。文字を食らうやつと、明るい夜を、勝手にくらべて、私の頭はクラクラした。
当時の私は、彼のことを忘れずにいても、とても思い返すことはできなかった。こうして記せるようになったのは、時の経過と今もまだ現役で作家をしているおかげである。
