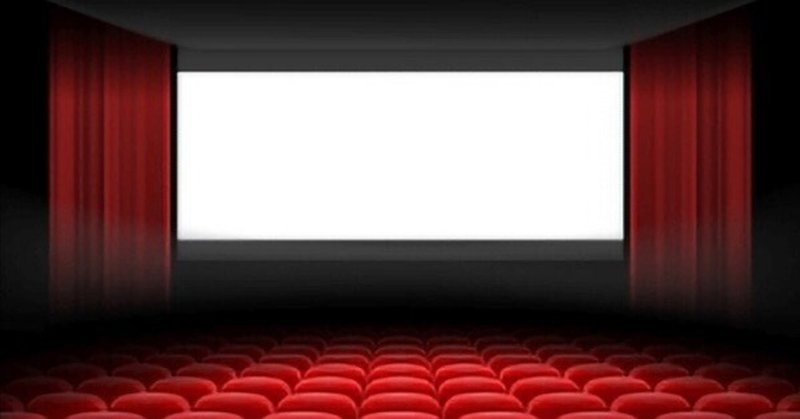
2023お気に入り映画・ドラマ10選 in 198
皆さま、明けましておめでとうございます。
本年も何卒よろしくお願い致します。
昨年見た映画・ドラマは計198本でした(ドラマは1シーズン=1本、リミテッドシリーズは全話=1本、同じ作品を複数回観た場合は1回=1本とカウント)。
その中で、私が2023年に初めて観た作品の中から、お気に入り作品を10本選んでみました(あくまでベスト10ではなく10選ですので、気持ち的にはだいたい順不同です)。
※以下、作品内容に触れていますので未見の方はご注意ください。
1:キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン
アメリカ大陸にあとから入植してきた白人が先住民族に働いた無数の蛮行の一つである「オセージ族連続怪死事件」の映画化。この企画は、レオナルド・ディカプリオが原作の出版前に映画化権を買い取り、マーティン・スコセッシに持ち込んで実現。事件解明のためにやってきた(のちのFBI)捜査官を主人公にした原作から、視点を大胆に変更。オセージ族女性と結婚し、彼女を愛しながらも、主犯である叔父の言いなりになって罪を犯し続ける、板挟み状態の実行犯を主人公にしたことで「いつものスコセッシ映画」の系譜になるという見事なアレンジ。悪の象徴たる叔父=ロバート・デ・ニーロに終始振り回され続ける、愚かで情けなくてみっともない子悪党を演じたディカプリオの、主体性がなく、身近な権力に逆らえず、言われるまま流されるままに悪事を働き、自分でも悪いことをしている自覚はありつつもそのことを直視しない卑俗な人間性は、自発的に思考停止した我々でもあり、「凡庸な悪」そのものにも見える。かつて、少女漫画から飛び出してきた王子様のようだったディカプリオが年月を経て、変な髪型とへの字口で、叔父から「おい!なんだその顔は!理解してんのか?それが理解してる顔か?」と言われてしまうような笑、呆れるほど愚かな俗物を見事に演じ切ったのは、改めて感慨深い。また、彼を見透かすようなアルカイックスマイルと理知的な瞳が印象的なリリー・グラッドストーンにも圧倒された。3時間半という長尺ながらダレることなく緊張感を持続させ、犯人を主人公にしつつ被害者側を丁寧に描き、終盤では「実際の事件を商業作品にすること」への倫理的葛藤に対する回答を、監督自らが見事に提示してくれる。当時の白人に根付いていた他人種への圧倒的な差別意識に基づく、「アメリカの原罪」とも言える残虐行為を、プロパガンダにならず、刺激的なだけの消費物にもならないよう、できるだけ誠実に語り継ぐことこそ、(いまだに存在する特権で守られた)白人である彼らが本作を作る動機の一つだったのかも知れない。その意図は見事に成功していると思う。しかし、エンドロールでは、不快な蠅の羽音と「ショミカシ」の声が聞こえ続けている。
2:イニシェリン島の精霊
『スリー・ビルボード』につづくマーティン・マクドナー監督最新作。シンプルかつ最低限の要素だけで、奥深く複雑なテーマを提示した本作には、面白さと滑稽さと怖さと苦さが同居している。牧歌的を通り越して神話的な雰囲気すら漂う、アイルランド辺りの架空の島に暮らす、中年から初老くらいの男二人の喧嘩がこじれにこじれてゆく様を通して、「知性や知的好奇心の差によるディスコミュニケーション」という、なんとも苦い主題を炙り出す。知的好奇心や向上心を持つ男と、そういうものとは無縁の素朴で善良な男。どちらも悪人ではない。どちらの願いも間違いではない。しかし、決定的に相容れない。今までの交流を続けるためには我慢や妥協や諦めが必要だ。しかし、我慢や妥協や諦めの上の友情が本当の友情だろうか。そのことに気づいてしまった男が、ついに思いを口にすることで争いは幕を開け、事態は深刻化してゆく(この「固い決意を持って行動を起こす主人公」は『スリー・ビルボード』にも通じる)。しかし、二人の争いを一歩引いて見守る素朴な男の妹は、小さな島の外の世界を知っており、本を友とする知性の持ち主である。彼女にはきっと、二人の争いは滑稽かつ哀れに見えているだろう。しかし、小さな島には、知性や好奇心を持つ者の居場所はなさそうだ。この狭い世界で、異なる欲望を持つ者どうしが共存する道はあるのだろうか。この問いかけはそっくりそのまま、争いが絶えない我々の現実への問いかけだと感じた。
3:TAR/ター
『リトル・チルドレン』以来16年ぶりのトッド・フィールド監督作は、ケイト様の名演を堪能しつつ、キャンセルカルチャー問題の複雑さを、安易に簡略化せずに描き出す、緊迫感に満ちた傑作。手にした権力を都合良く悪用してきた人物が世間にキャンセルされる過程は、たしかに自業自得ではある。が、人並外れた努力と才能で成功をつかみ取り、自信と実績を積み上げた果てに手にした「権力」は、本人には「当然の権利」と見分けがつかないのかも知れない。権力を倫理的かつ抑制的に行使することは、きっとかなり難しい。一方、彼女をジャッジする世間(or 観客)も常に危うさを孕んでいる。大衆はしばしば間違える。ケイト様の凛とした佇まいや「レズビアンであることを公表している女性」という属性のせいか、ある時点までは「高圧的な振る舞い」が「自信に満ちた振る舞い」に見えかねないというあたりにも、他人を裁く側の判断力への危惧が仕込まれているように見える。企画段階では、主人公はレナード・バーンスタインをモデルにした男性指揮者であったが、それをケイト様に変更したのは、テーマの深みを増す意味でも見事な判断だったと思う。人が人を裁くことは正しいのか。作品と作者を同一視しても良いのか。それらは確かに難しいが、人が人を裁くことのトライ&エラーの繰り返しで、社会が少しずつマシになって行ってる側面もなくはないはずだ。そして、唖然とすること必至のラストシーンは、新たなるスタート地点。なのかも知れない。
4:SHE SAID その名を暴け
ジャニー喜多川や松本人志の性加害報道が明るみに出たことで、改めてタイムリーになってしまった感もある本作は、権力者による性加害の実態を暴き出し、#MeTooムーブメントのきっかけにもなった世界的大スクープ誕生の過程を描く。長年に渡りハリウッドで絶対的権力を振るったプロデューサー、ハーヴェイ・ワインスタインの性加害容疑を追う二人の女性ジャーナリスト(キャリー・マリガン&ゾーイ・カザン)が、一歩一歩着実に本丸に近づいてゆくリアルな調査報道の様子は、一見地味極まりないが非常にスリリング。主人公二人も決して完全無欠なヒーローではなく、日々の生活に追われつつも被害者たちに寄り添い、そのか細い声を集めてゆく。二人をバックアップする編集部とのチームワークも胸熱な「ザ・お仕事映画」。そして何より、本作に描かれた現実は、映画への夢や情熱を食い物にされた被害者たちの勇気がなければ生まれなかったという事実は、忘れてはならない。権力に忖度しまくる腰抜けメディアに、ルドヴィコ療法方式で1000回観せたい作品。あと、うっかりペアルックもチャーミングでした。
5:ウーマン・トーキング 私たちの選択
メノナイト(キリスト教の一教派)信者が暮らすボリビアの共同体で実際に起こった連続レイプ事件の顛末を映画化。幽霊の仕業だと信じ込まされてきた強姦被害の犯人が村の男たちだと知った女性たちは、男たちが村を空ける二日間の間にこれからどうするかを話し合う。何もしないか、村に残って男たちと闘うか、出ていくか……。ルーニー・マーラ、クレア・フォイ、ジェシー・バックリー、フランシス・マクドーマンドなど、錚々たる役者陣が演じる、決して一枚岩ではない女性たちが様々な意見をぶつけ合いながら結論へと至る、切実なディスカッションドラマ。監督・脚本を務めたのは、女優でもあるサラ・ポーリー。この問題に対する、彼女の真摯な姿勢に敬服。感情に任せず、理性的に、論理的に、腰を据えて、情理を尽くして、優しさと共感を忘れず、丁寧に話し合うことの困難さと大切さと崇高さを教えてくれる。民主主義の大切さ、熟議の大切さを全く理解せず、嘘や胡魔化しばかり垂れ流す政治家どもに、ルドヴィコ療法方式で1000回観せたい作品。
6:スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース
もし淀川長治さんが観たら、「凄いね〜、アクション、アクション、アクション! キャラクターが、画面全体が、映画全体が、アクションの洪水ですね。そして、色彩も、洪水ですね。色彩の洪水ですね。目がチカチカしますね。絵に生命が宿って、躍動します、まさにアニメーションですね!」と言いそうなほど、映像的情報量が、人間の脳容量の限界を押し広げつつ突破するような、未来からやって来た作品のような、アニメーションの快楽に溢れた傑作。しかしもちろん、絵が派手なだけではない。場面ごとにタッチが目まぐるしく変わるこの映像でしか表現し得ないエモーションも、見事に描かれている。続編も楽しみです。
7:RRR
あ、繰り返しになりますが、私が2023年に初めて観た映画の中から選んでおります笑。というわけで、今更説明するまでもない、『バーフバリ』シリーズのS・S・ラージャマウリ監督による超弩級エンタメ作品! 「えっ!? 一瞬のアイコンタクトでそこまでの意思疎通が!?」なビームとラーマの出会い、「ナートゥ ナートゥ」の圧倒的祝祭感&高揚感、「んなワケあるかい!」のさらに上を行く、リアリティ度外視のキメキメアクション、それらのつるべ打ちで問答無用にブチアガる。役者の肉体からカメラワークに至るまで、映画全体が躍動しまくっててとにかくパワフル。退屈する暇が全くない3時間。楽しませていただきました。
8:別れる決心
パク・チャヌク監督の最新作は、濃密な大人のラブロマンス。色気と艶やかさと奥ゆかしさともどかしさを優先した結果、いわゆる「リアリティ」は度外視しているように見えつつも、現代的なガジェットはフル活用で、映っている物は妙に現実的で生々しい。現実を演劇的・戯画的に切り取り、妄想や幻想をリアルに描くところも含め、この奇妙なバランス感覚こそ、パク・チャヌク映画だな〜と感じる。生真面目な韓国人刑事と、韓国語が苦手な中国人容疑者の、「翻訳」を介したコミュニケーションにもエロスが溢れかえる。恋が始まり、恋の深みにはまってゆく二人の間に霧のように立ち込める、圧倒的に濃密な「雰囲気」こそが重要な映画だと思うが、その「雰囲気」を映像で描くための画面設計や色彩設計がものすごく緻密で、繰り返し観たくなる。リップクリーム+ヘッドライト=エロい!
9:ザ・キラー
「え〜っと……これは……笑って、良いん、です……よね?」と、コメディであることを受け入れるまでにだいぶ時間がかかってしまった、クールすぎるコメディ映画。だって、デヴィッド・フィンチャー×マイケル・ファスベンダーで、まさかドジっ子コメディが来るだなんて思わないでしょーよ笑! でもコメディと言い切るには構図も色彩も演技も音楽もバッキバキにキマり過ぎてて、謎の新食感。「計画通りにやれ。予測しろ。即興はするな」と心の中で唱えながらもことごとくうまく行かない、凄腕の(はずの)殺し屋による、自分の失敗の尻拭いツアー。完全におバカなドジっ子でもなく完璧に凄腕でもない、描いている自己イメージと実像が微妙にズレちゃってるマイケル・ファスベンダーが超キュート。「犬が思ってたよりもデカい」で爆笑してもた。
10:フェイブルマンズ
監督本人が「この映画は私の記憶です」と述べているので、虚実の客観性については魅力的な謎のまま。監督の過去作を想起させる様々なシーンにニヤリとしつつ、しばしば言及されてきた、フィルモグラフィにおける「父の不在」に対して、意外なほど存在感を見せる父との関係性にも驚き。技術屋の父と芸術家の母の見事なハイブリッドとして生まれ育ち、映画の中の「破壊」に魅せられた少年は、「映画に愛された」を通り越して「映画に呪われた」レベルで凄いものが撮れてしまう男になってゆく。その苦悩は、凡人が簡単に共感できないものではあるが、作り手になりたい者には羨ましくも映る。そして何より、「軽妙洒脱なラスト部門」堂々の第一位!と言いたくなる見事なラスト。監督本人が、先達や後輩や観客に向かって子供っぽい笑顔でウインクしているような、愛らしくておしゃれでカッコよくてウィットに富んだ幕切れで、強引に「あ〜良いもん観た!」と思わせる恐るべき力技は、やっぱり「映画ウマ男」(©︎BLACKHOLE)。
その他お気に入り作品。
エンパイア・オブ・ライト
ザ・クラウン(全6シーズン)
君たちはどう生きるか
ミッション:インポッシブル/デッド・レコニングPart1
BEEF/ビーフ(リミテッド)
終わらない週末
最後の決闘裁判
ふぞろいの林檎たち(シーズン1)
映像ディレクター。自主映画監督。 映像作品の監督・脚本・撮影・編集などなどやっております。
