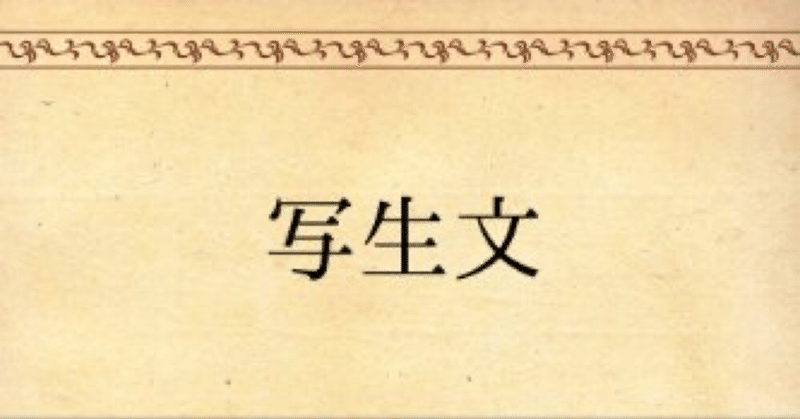
子規の写生文(2019)(3)
第3章 公私分離とスケッチ
明治期の画家は、西洋の美術に影響を受けつつも、近代の本質の理解はお寒いのが実情である。近代の最も根本的な原理は政教分離、すなわち公私分離である。ところが、明治の画家は公的思惑に私的嗜好を従属させてしまう。西洋の画法は、当初、設計図・地図の作成や写真の代用など実用的理由から受容されている。その芸術性が次第に理解されたものの、洋画家は国家のための美術にからめとられる。明治政府は美術が外貨獲得に役立つと芸術政策を進める。その際、欧米人の需要に応えるため、黒田清輝を始め洋画家も和洋折衷の作品を描くようになる。
近代の是非を問う前に、その理論的基礎づけを知らねばならない。前近代社会はさまざまな事情によって世界各地で各々出現・発展しており、標準型はない。だが、近代は違う。近代はそれ以前からの流れを一旦断絶した上で、人為的に構築した社会である。市民革命・産業革命の英国を標準型とし、社会契約論・共和主義・功利主義などによって基礎づけられている。理念や原則、制度はこうした理論に根拠を持っている。前近代の伝統は近代制度の解釈の違いとして現われるものでしかない。何をもって政教分離とするかの理解は国によって異なるとしても、それを無視した近代国家はそう呼ぶに値しない。政教分離は西洋の発想であるから、受容せず、独自の近代を目指すなどという主張はたんなる無知でしかない。
前近代が暗黙知とすれば、近代は明示知の世界である。その社会で日常的に暮らしていれば、近代の仕組みを理解できるわけではない。理論を知ることによってそれは認識できるものだ。
古代より政治の目的はよく生きること、すなわち徳の実践である。その認識を覆したのが16世紀の宗教戦争だ。自らの道徳の正しさを根拠に凄惨な殺し合いが欧州各地で繰り広げられる。17世紀英国のトマス・ホッブズは、これを教訓に、政治の目的を平和の実現に変更する。平和でなければ、徳の実践もままならない。
ホッブズは、その際、政治から宗教を切り離す。政治を公、信仰を私の領域として両者を分離する。いずれもお互いに干渉してはならない。それは公私の区別へとつながる。この政教分離は近代の最も重要な原則である。
信仰や道徳が私的領域に属し、公が干渉しないということは、価値観の選択を個人に委ねたことを意味する。それにより価値観は多様化する。近代は価値観の多様性を前提にしている。
政教一致は価値観が一元的である。欧州の中世の民衆は情報をもっぱら教会から得ている。中世は人口が減少傾向で、農産物の生産性も低い。世俗権力は税収が上がらず、民衆への影響力が大きくない。民衆は移動や職業選択の自由が制限され、識字率も低い。そんな民衆が情報を入手するとしたら、どんな村落にもある教会に依存するほかない。一元的価値観は実際にも教会による情報の独占がもたらしている。
近代において価値観が多元的であることは社会に複数の人々がいることを指し示す。個々人がそれぞれの価値観に基づき効用を欲する。そのため、個人と社会の効用は必ずしも一致しない。個人が多様性だけを追求したのでは、社会がバラバラになってしまう。価値観の多様性に基づきながら、社会的共通基盤が必要になる。
社会は、理念上、自由で平等、自立した個人によって成り立っている。近代は個人が先にいて社会が形成されるとする。ただ、複数の人がいれば利害対立も起きる。そうした社会における諸問題の調整・対処のために、ジョン・ロックによれば、国家、すなわち政府が必要とされる。共同体があって個人がいるとする前近代と違い、個人主義に近代社会は立脚している。個人が優先しているのだから、義務の対価として権利が国家より付与されるものではない。近代は権利の社会で、国家にそれを保障する義務がある。
そこで複数が意見を交換する議論の場が社会に生まれる。それは公と私の重なり合う共の領域である。自分の意見を述べ、他の主張に耳を傾け、よりよい考えを模索する。こうした話し合いには情報が不可欠である。複数の情報源がなければ、価値観の多様性は確保できない。そのため、表現の自由が権利として保障されていなければならない。
近代美術はこうした理論によって基礎づけられた社会の中にある。西洋の絵画技法を学んだり、近代化の風景を描いたりすれば、近代美術になるものではない。公私の区別を理解しないまま、絵を描いたとしても、「皮相上滑り(夏目漱石)」な近代絵画もどきでしかない。公私分離により価値観の選択が個人に委ねられているにもかかわらず、国家の推進する芸術政策に乗っかり、公的要請を私的嗜好より優先した絵は近代美術に値しない。
日本美術史を見ると、近代の咀嚼の点で江戸後期の渡辺崋山よりも明治の洋画家は後退している。洋画の技法を学んだ崋山の『四州新景図』(1825)や『芸妓図』(1838)は明治の用が以上に近代絵画である。スケッチを手控えて本画にするのが従来の過程であるが、崋山はそうした習慣に縛られず、前者を自由に描いている。また、後者の女性は顔を苦痛で歪めている。これはスケッチをそのまま完成作にしたことを物語る。しかも、我慢する表情であり、美しくない。それは公的規範ではなく、私的嗜好を優先させた造形であることを意味する。講師が区別され、前者に対する後者の顛倒がそこにある。既存の価値観から自立し、公から私の領域を解放、自由な表現に挑む崋山の絵画は近代の精神を持っている。
このように見てくると、子規の写生文の理想は崋山の絵画にこそ具現している。扱う対象は公的ではなく、私的価値に基づいて選び、従来の規範から自由であるために、即興的に文章を仕上げる。自由で平等、自立した近代人として文章を書く心得が写生文である。
その子規が写生文を考案した理由は文学研究における関心事の一つである。江藤淳は、『リアリズムの源流』において写生文運動に注目しており、写生文運動を夏目漱石の登場につながる「活きた」文章を考案したと述べている。リアリズムが輸入されたので、それに飛びついたわけではない。近代化によって新しいものが出現した時、それとの言葉の結びつきを求めて生み出したのが写生文である。また、渡部直己は、『リアリズムの構造』(1988)において、江藤淳を踏まえ、子規が分類から俳句に入っていったことを重視する。子規が「とらわれぬ眼で認識することの必要性」を痛感していたのは、彼が「ものに直面」していたからだと江藤淳は記す。だが、子規は何よりまず言葉そのものにとらわれすぎる自分自身の過剰さに「直面」していたとしている。さらに、柄谷行人は、両者を敷衍しつつ、『内面化されない他者性』(1992)で、写生文が日本語に差異化と多様性をもたらしたと論じている。
こうした議論にはそれぞれ一理ある。しかし、写生文がスケッチの発想からの援用であり、近世の画家渡辺崋山がその理想を実現していたとすれば、見落としがある。
渡辺崋山はさまざまな流派の技法を学んだ後、蘭画に出会っている。崋山は両者を比較して相対化、従来の規範になかった洋画のスケッチの発想に着目する。それは政治と道徳が一体化した体制においてはあり得ない公私の区別が潜んでいる。崋山はスケッチを大胆に活用した絵画を実践する。
子規もおそらく同様だろう。子規は伝統的詩歌に精通し、写生文の構想の発端は俳句の革新である。俳句は抒情詩に属する。視点を世界の外部に置く叙事詩に対して、抒情詩はそれが内部にある。叙事詩の声が鳥瞰的・・客観的とすれば、抒情詩は局所的・主観的である。しかし、前近代は共同体主義で、政治と道徳が一体だ。価値観が一元的であるので、その私は公の認める規範に則ったものでなければならない。伝統的な俳句はこうした前提に則っている。
近代は公私が分離され、両者の干渉は禁止、価値観が多元的である。近代の俳句はこの認識に基づいていなければならない。子規は西洋美術のリテラシーに触れ、スケッチにその原則の具現を見出す。スケッチを用いれば、従来の規範から自立して私は公の干渉を受けずに自由に表現できる。それを文章作成に移植したのが子規の写生文である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
